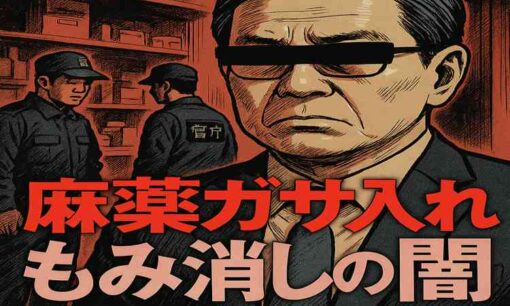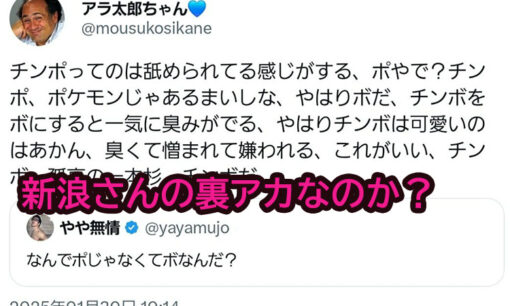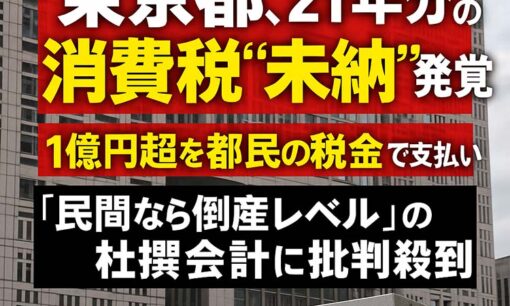サントリーは「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造する」という企業理念を掲げ、「水と生きる」をコーポレートメッセージに据える生活文化企業である。創業から一貫して“水”を核に事業を広げ、環境・社会・文化の面で独自の価値提供を続けてきた。本稿では、創業の歩みから環境目標2030・2050、森と水の取り組み、容器包装の革新、人権・調達、文化貢献、ガバナンスまで、サステナビリティの実像を事実で描き出す。
サントリーを牽引、新浪剛史について:“外から来た社長”が推し進めたグローバル経営
新浪剛史氏は慶應義塾大学経済学部を卒業後、三菱商事に入社し、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得。経営戦略や流通分野で経験を積んだのち、2002年にローソン社長へ就任し、コンビニ業界にカフェや健康志向を持ち込み再生を果たした。その手腕が評価され、2014年、サントリー初の創業家外からの社長に抜擢された人物である。
サントリーでは、米ビーム社買収後のグローバル統合を指揮し、世界的プレミアムスピリッツ企業へ飛躍させた。スローガン「One Suntory」を掲げ、日本発の飲料・酒類企業から真のグローバル企業への変革を推進したのが大きな功績である。加えて、気候変動・プラスチック問題への対応を加速させ、グローバル・サステナビリティ経営を強化。現場視察や社員との対話を大切にする姿勢も特徴的だ。
2025年3月には会長兼CEOに就任し、創業家の鳥井信宏社長との二頭体制で次の成長を担っている。経済同友会代表幹事や政府の経済財政諮問会議の民間議員も務め、産業界を代表して政策提言を行う存在でもある。グローバルな視座と日本的な「現場主義」を兼ね備えたリーダーとして、サントリーを持続可能な成長へ導いている。
サントリーってどんな会社?
「水と生きる」を実装するサステナビリティの現在地とこれから
創業1899年、世界へ広がる飲料企業グループ
サントリーの起点は1899年。創業者・鳥井信治郎が大阪で「鳥井商店」を開き、ぶどう酒の製造販売を始めた。以降、国産ウイスキーづくりへ挑戦し、1923年には山崎に蒸溜所を開設。現在はソフトドリンク、スピリッツ、ビール、ワイン、健康領域まで多角展開するグローバル企業だ。2024年にはスピリッツ事業のビームサントリーが「Suntory Global Spirits」に改称し、プレミアムスピリッツとRTDの成長を軸に世界展開を加速している。
企業理念と価値観:「人と自然と響きあう」「やってみなはれ」
グループ理念は「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命(いのち)の輝き』をめざす」。価値観として「Growing for Good」「やってみなはれ」「利益三分主義」を掲げる。コーポレートメッセージ「水と生きる」は、水の恵みに生かされる企業として水資源を守り、社会に潤いをもたらす決意を簡潔に表す。同社は2023年に理念体系を刷新し、メッセージの意味を改めて社会に示している。
「水」を起点にした環境経営:森を育てて水を育む
サントリーの環境経営の中核が、工場の水源域で生態系を再生させる「サントリー 天然水の森」である。2003年に阿蘇から始まり、国内各地で拡大。総面積は約12,000ヘクタール(2024年時点)に及ぶ。森の土壌を“フカフカ”に整えることで雨水を地下へ浸透させ、良質な地下水を育むという科学的な発想に立ち、社内の水科学研究所(2003年設立)と連携して保全・再生を進める。さらに、自然本位の水源管理に関する国際指標AWS(Alliance for Water Stewardship)でも先行し、奥大山、九州熊本、南アルプス白州の3工場が日本初のAWS認証取得、現在は3拠点すべてがPlatinum認証に到達している。
「水理念」と2030の水コミットメントで教育・還元・効率化
グループは2017年に「水理念」を制定し、①流域の科学的理解、②節水の3R、③水源保全、④地域との共創を柱に行動する。2030年に向けては、自社工場の水使用原単位35%削減(2015年比)、自社工場の半数以上で「使用水量の100%超を流域へ還元」、水に関する教育・安全な水アクセスの提供を合計500万人以上へといった目標を掲げ、水教育「水育(みずいく)」は2004年開始以来、2024年末で延べ119万人超が参加。同年、教育の到達人数目標は当初の100万人から500万人へ上方修正されている。
気候変動への対応:1.5℃目標整合のSBT、2050ネットゼロ
サントリーは2050年にバリューチェーン全体でネットゼロ、2030年には自社拠点のGHGを50%削減、バリューチェーン全体を30%削減(いずれも2019年比)という目標を公表し、SBTiの1.5℃目標認証を取得している。進捗として2024年度時点でScope1+2を32%、バリューチェーン全体で13%削減。63の主要拠点で電力の再エネ100%(2022年)も達成した。加えて内部カーボンプライシング(2021年導入)を用いて2030年までに約1,000億円を投資、再エネ化・高効率設備の導入等で年間約100万トンの排出削減を見込む。TCFDには2019年に賛同し、取締役会監督のもと四半期ごとに進捗をレビューする体制を敷く。
容器包装のイノベーション:2030年「ペット100%サステナブル」へ
プラスチックでは2019年に「プラスチック基本方針」を策定。2030年までにグローバルで使用する全ペットボトルを、リサイクル素材と植物由来素材に100%切替(化石由来の新規使用ゼロ)を掲げる。ボトル軽量化や“ラベルレス”の普及に加え、「ボトルtoボトル」水平リサイクルを加速。2018年にはKyoei Sangyo、EREMA、SIPAと連携し、回収PETフレークから直接プリフォームを製造する「F-to-Pダイレクトリサイクル」技術を共同開発して実装した。理念面では「2R+B(Reduce/Recycle+Bio)」戦略を明示し、資源循環の実効性を高めている。
人権・サプライチェーン:方針の改定と実装の深化
社会面では「サントリーグループ人権方針」(2019年制定、2024年6月改定)を最上位方針として掲げ、国際人権章典やILO中核的労働基準に整合。サプライチェーンには「サステナブル調達基本方針」(2011年制定)とパートナーガイドラインを適用し、Sedex活用やサプライヤー対話・調査の仕組みを整える。原料面では再生型農業(Regenerative Agriculture)の実証や、コーヒー・大麦・トウモロコシ・サトウキビなど重点原料の人権・環境リスク評価を推進。砂糖サプライチェーンでは国際プログラムVIVEにも参画する。
文化・自然への貢献:「音楽」「美術」「愛鳥」で社会の土壌を耕す
サントリーは環境だけでなく文化・社会への投資も続けてきた。サントリーホール(1986年開館)は“世界一美しい響き”を掲げる日本を代表するクラシックホールであり、公益財団法人サントリー芸術財団(2009年設立)は音楽と美術を核に新たな価値創造を支える。また「サントリーの愛鳥活動」は1973年にスタートし、啓発広告や助成、バードサンクチュアリの整備等で生物多様性保全を長年リードしている。これらは同社のサステナビリティ・ビジョンにある「生活文化(Enriching Life)」の具体像でもある。
ガバナンス:ボード監督と体制更新
サステナビリティは取締役会監督のもと、Global Sustainability Committee(GSC)とGlobal Risk Management Committeeが連携して進める。気候・水・容器包装といった重点領域の戦略をGSCが策定し、四半期ごとに進捗をボードへ報告する枠組みだ。経営体制は2025年に更新され、代表取締役社長に鳥井信宏氏が就任(2025年9月1日付役員一覧より)。創業家のリーダーシップの下、「One Suntory」でグローバル経営とサステナビリティを統合的に推進している。
数字で見る環境目標(2030→2050)
- GHG:2030年に自社50%/バリューチェーン30%削減、2050年ネットゼロ。SBTi 1.5℃認証済み。進捗:2024年度でScope1+2を32%、全体13%削減。
- 水資源:自社工場の水原単位35%削減(2015年比)、工場の半数超で100%超の水還元、教育・安全な水アクセス合計500万人以上。AWS認証は3工場がPlatinum。
- 容器包装:2030年に全ペットボトルを100%サステナブル素材化(リサイクル+植物由来、化石由来の新規使用ゼロ)。ボトルtoボトルやF-to-Pで実装を加速。
評価の視点:”いい会社”と言えるのか
①自然資本と本業の直結
水を最重要資源と位置づけ、森の再生や流域単位のステュワードシップを事業と一体で運用。教育「水育」やAWS認証の取得など、地域と科学に根差した活動が継続している。
②検証可能な目標と外部認証
SBTiの1.5℃整合、TCFDへの2019年賛同、四半期レビューなど、“目標→実装→検証”の筋が通っている。進捗の定量開示も適切だ。
③技術と協働での資源循環
F-to-Pダイレクトリサイクルやラベルレスなど、実効性のある容器包装イノベーションを社外連携で実装。政策・他社・自治体とも協働して水平リサイクルを広げる姿勢が明確である。
④人権・調達の基盤整備
人権方針(2024年改定)とサステナブル調達の仕組みを整え、Sedexや国際プログラムを活用してリスク低減と価値向上を両立させている。
⑤文化・社会への継続投資
音楽ホール、芸術財団、愛鳥活動など、文化資本の厚みは国内屈指。自然・文化・人をつなぐ「生活文化」への貢献が企業の顔になっている。
まとめ
サントリーは、「水」を軸に自然と社会に向き合う固有の企業像を築いてきた。天然水の森に代表される流域再生、水育による次世代教育、SBTi認証に裏打ちされた気候目標と内部カーボンプライシングを伴う実装、ボトルtoボトルやF-to-Pなどの循環技術、人権・調達の基盤、そして文化・芸術・愛鳥活動に至るまで、“よい会社”の根拠を数字と制度で語れる稀有な存在である。サステナビリティを経営の中枢に置き、「人と自然と響きあう」という理念を実務で体現し続ける——それがサントリーの現在地だ。
【参照】