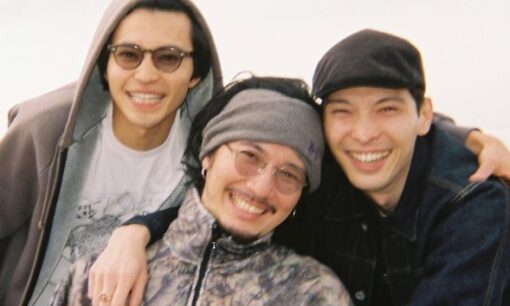夜が明けると、スマートフォンに通知が届く。「昨夜の電力使用量は平均より15%高。エアコンのタイマー設定を見直しませんか?」――都内に住む共働き世帯の一家は、朝のコーヒーを淹れるタイミングでこのデータを確認し、リビングの設定を変更する。日常の些細な選択が、エネルギーの効率化につながっていく。
一方、地方の自動車メーカーでは、製造ラインの画面に「このリチウム電池は人権リスクが高いため、優先順位を下げてください」との警告が表示された。新たな仕入れ先の選定が検討され、サプライチェーン上での“倫理的トレーサビリティ”が再評価される。背景には、欧州電池規則への対応と、日本企業としての信頼性確保がある。
これらのシーンはすべて、経済産業省が推進する「ウラノス・エコシステム」によって実現される可能性の一端である。同省は5月9日、この構想のもとで優良な取組を選定・奨励する新制度「ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度」において、初の先導プロジェクトとして2件を選出したと発表した。データはもはや単なる記録ではなく、暮らしや産業をつなぐ“社会インフラ”となりつつある。
「ウラノス・エコシステム」とは何か
ウラノス・エコシステムは、経産省が関係省庁やIPA(情報処理推進機構)デジタルアーキテクチャ・デザインセンターとともに推進する横断的データ連携の枠組みである。人手不足、災害の激甚化、脱炭素といった社会課題を乗り越えるために、企業、業界、国境を越えて安全かつオープンにデータを連携できる空間(データスペース)の構築を目指す。
本構想の黎明期にあたる現在、先進的な取り組みを先導・挑戦の2分類で奨励するため、2025年度から新たに「ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度」が開始された。異なる事業者間で行われる、コントロール可能性の高いオープンなデータ連携を評価・選定するのが特徴である。
2件の「先導プロジェクト」を選定
今回、先導プロジェクトとして選定されたのは以下の2件。
ひとつは、一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC)が主導する「自動車・蓄電池のCFP・DDデータ連携プロジェクト」だ。カーボンフットプリント(CFP)およびデューデリジェンス(DD)に関するデータを、欧州の電池規則への対応も視野に入れながら、安全・安心に企業間で連携する仕組みの構築が進められている。これにより、車載電池の製造・供給に関するCO₂排出量の可視化や、人権リスクを含む原材料調達の透明化が可能になる。
もうひとつは、一般社団法人電力データ管理協会が運営する「電力データ提供プロジェクト」である。全国約8000万台に設置されたスマートメーターから、30分単位で収集される電力使用量や売電実績などの情報を、一般送配電事業者(データ提供会員)からデータ利用会員に提供する取り組みだ。これにより、電力需給の最適化、再エネの効率的利用、需給調整市場の高度化など、複数の分野に波及する可能性がある。
生活や経済の「見えなかったもの」が見える社会へ
経産省が強調するのは、ウラノス・エコシステムを通じて「これまで個社や業界内に閉じていたデータが、信頼を前提に安心して共有される社会基盤を築くこと」だ。企業にとっては競争力と透明性の両立、市民にとっては生活の質と選択肢の向上という形で、その恩恵は確実に波及していく。
すでにサービス化されたプロジェクトを「先導」、今後の社会実装を目指すものを「挑戦」として分類し、段階的な発展を見据える同制度。今後、再エネ、物流、都市インフラ、医療など、他分野への拡大も予測される。
ウラノスの名が示す、天のように広がる連携の未来
ギリシャ神話における「ウラノス(Ouranos)」は天空の神である。制度名にこの語が選ばれた背景には、産業や国境、立場を超えて広がる“見えないつながり”への願いが込められている。今回選ばれた2つのプロジェクトは、その第一歩である。
静かに幕を開けた「データ連携の社会実装」は、やがて日々の暮らしや意思決定の在り方を根本から変えていくかもしれない。今後の展開に注視したい。