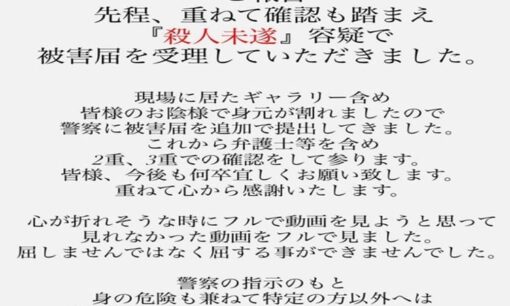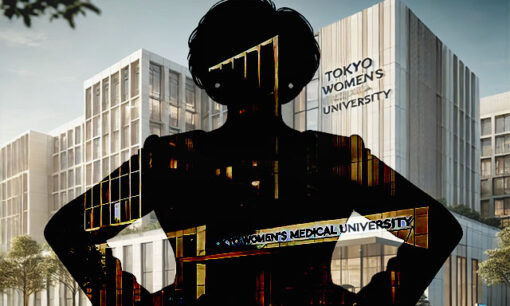トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」)は、自動車の鉄廃材を活用し、山形鋳物の伝統技法を用いた急須・冷酒器を製作した。この取り組みは、山形県山形市の老舗鋳物工房「菊地保寿堂」との協力によるもので、廃材に新たな価値を与える「アップサイクル」を通じ、地域の伝統工芸と環境保全を両立する試みとなる。
山形鋳物とは
山形鋳物(やまがたいもの)は、日本の伝統的工芸品であり、山形県山形市とその周辺に伝わる鋳物産業である。1975年に経済産業省(当時の通産省)から伝統的工芸品に指定された。平安時代中頃、前九年の役で山形を訪れた源頼義の従軍職人が、鋳物に適した土壌を見つけたことが始まりとされる。その後、戦国時代の最上義光が産業を支援し、江戸時代には仏具や日用品として広く普及。現代では伝統工芸品だけでなく、機械部品鋳物の生産も盛んに行われている。
「捨てるところのないモノづくり」への挑戦
トヨタ構造デザインスタジオでは、経済軸(コスト効率)、技術軸(高性能・軽量化)に加え、環境軸(地球環境への配慮)を取り入れた「Geological Design(ジオロジカルデザイン)」を推進している。リサイクルできない鉄廃材に新たな命を吹き込むことを目的に、地域の職人やアーティストと協力し、アップサイクルを実現する仕組みを構築している。
今回の急須・冷酒器の製作にあたっては、自動車の製造工程や廃車から生じる鉄廃材を再利用。通常、アップサイクルが難しいとされる鉄廃材を伝統技術と融合させることで、工芸品としての価値を持たせることに成功した。
「新伝統と創造」 山形鋳物の技術を生かした製品
製品の外側には自動車廃材を、内側には食品衛生基準を満たした鋳物ホーローを使用。日本を象徴する「ジャパンブルー」とも呼ばれる藍色の焼きつけ塗装に銀チップを散りばめ、夜空をイメージしたデザインとなっている。また、形状は山形県の霊峰・月山をモチーフにしており、伝統と革新を融合させた一品に仕上がった。
急須としてだけでなく、紅茶や中国茶の茶器、さらにはコーヒードリップ用ポットや冷酒器としても利用可能。直火は避ける必要があるものの、幅広い用途での活用が期待されている。
伝統工芸と環境保全の融合
創業1604年と日本で一番古い鉄瓶屋の菊地保寿堂15代当主の菊地規泰氏は「廃材にはマイナスイメージがあるが、人や自然に優しい製品へと昇華させることが重要」と述べ、たたら製鉄法を応用した独自の鋳造技術によって、環境と調和したものづくりの可能性を示した。
また、トヨタ構造デザインスタジオのテーマプロデューサーである大學孝一氏も「本取り組みが山形鋳物のさらなる認知向上や地域の活性化につながることを期待している」と語り、今後も職人との共創を進める考えを示した。
今後の展望
トヨタは今後も、持続可能なモノづくりを追求し、地域工芸との連携を強化していく方針だ。環境負荷の低減を目指しながら、伝統技術の継承と新たな価値創出を両立させる取り組みが、国内外での評価を高めることが期待される。