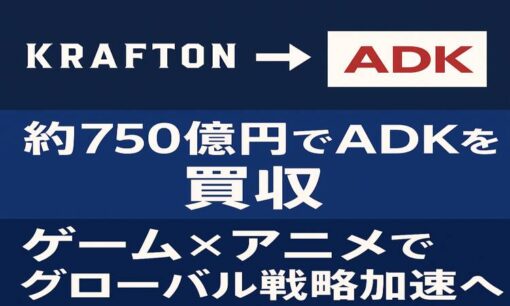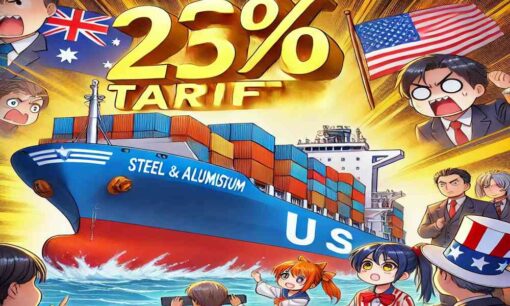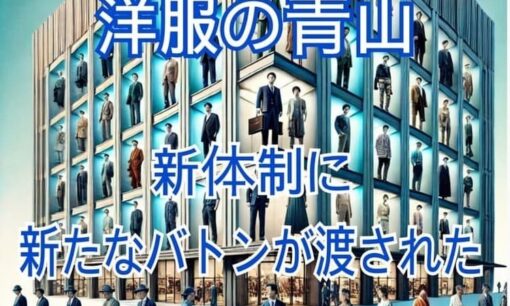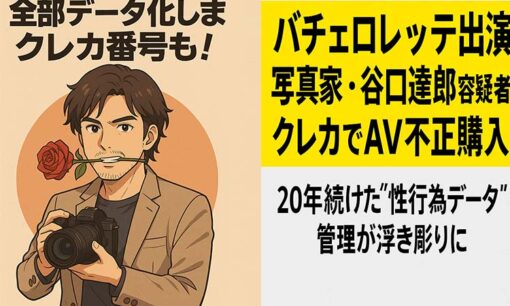AIベンチャー「オルツ」、売上の9割が循環取引 報告書で粉飾確定

東京証券取引所グロース市場に上場するAIスタートアップ、株式会社オルツが7月28日に公表した第三者委員会の調査報告書は、2021年から2024年までの売上の大半が架空だったという衝撃的な事実を明らかにした。累計約119億円、4期分の売上高の8〜9割が、広告宣伝費の名目で外部業者に支出し、その資金を「販売店」経由で売上として計上するという循環取引によって捏造されたものだった。
同日、創業者である米倉千貴社長が辞任し、モルガン・スタンレー出身でCFOを務めていた日置友輔氏が新社長に就任した。
しかし報告書では、両者ともに不正関与の責任を問われており、統治体制の混乱は不可避とみられている。
CFO・日置友輔氏は“共犯”か
報告書では、粉飾の主導者は米倉前社長であるとされているが、後任の代表取締役社長に就いた日置氏についても、「捏造資料を主幹事証券や東証に提出していた」「第三者委員会の調査をかいくぐるための工作も主導した」との報告書の内容を読むに、無実とは言い難い。
米倉氏が“主犯”なら、日置氏は“実行犯”。CFOとして金融知識を駆使して資料を改ざんし、証拠を消していたと読み取ることができ、今後米倉氏同様、逮捕の可能性も含め「共犯関係」が成立する関係とも言える。そうした人物が社長に留まることのリスクを思うと、オルツは危うい会社だし、彼らも当然それはわかっているだろうことを考えると、社長を引き受けてくれる人材がいなかったのかとも読み取れる。
VCと外部取締役も“見て見ぬふり”か
また、報告書では名指しされていないが、ジャフコベンチャーズなど複数のベンチャーキャピタル(VC)にも疑惑の目は向くだろう。アクティビストの田端慎太郎氏は、「知ってて売り抜けたなら悪、知らずに放置してたなら無能。どっちにしても責任は免れない」と断じ、VCが社外取締役として取締役会に出席していた可能性にも言及。「循環取引の構造は、社内からすでに上場直後に証券取引等監視委員会へ資料が提出されていた」と述べ、内部告発の存在にも触れている。
第三者委員会報告書に“消された名前”がある
ところで、報告書には、粉飾取引の主な経路として「広告代理店」「販売代理店」「主幹事証券」「監査法人」などが具体的に言及されているが、極めて不可解な点が一つある。過去にオルツと公式に提携を結んだADKホールディングス(旧アサツー ディ・ケイ)、そして主幹事証券を務めた大和証券の名前が、本文中で一切登場しないのである。
オルツは2023年、ADKと共同で人格生成プラットフォーム「CLONEdev」を活用し、大山俊哉CEOのAI分身「AI-CEO」を開発。ADK入社式ではAIが新入社員にパーソナライズされたメッセージを送る演出を行った。両社の蜜月関係は当時広く報道されていた。
また、上場の主幹事は大和証券であり、同社は上場審査に深く関与したはずだ。今回の報告書では、主幹事証券について「AV証券」などと匿名化され、名指しは避けられている。
“なぜ名前が消されたのか” 3つの推察
この「不在」は偶然なのか。それとも、報告書作成者による意図的な“抹消”なのか。ここでは、いくつかの合理的な推察を提示する。
推察① 名誉毀損リスクの回避と“法的配慮”
調査報告書が企業名・個人名を記載する際は、確実な証拠や責任の明確化が求められる。ADKおよび大和証券が、少なくとも現時点では「意図的な関与」や「違法行為」とまで断定されていない以上、報告書作成者が名誉毀損リスクを避けて匿名表記とした可能性がある。
特にADKは6月、韓国資本のグループに買収され、法人としての統治体制が移行している。法的責任の帰属が不明瞭になっているタイミングと報告書作成の時期が重なった可能性は否定できない。
推察② 市場秩序への“忖度”と象徴企業への配慮
広告業界3位のADK、大手証券2位の大和証券は、それぞれ日本の資本市場・広告市場における“象徴的存在”でもある。報告書が公表されたタイミングで、両社を名指しで記載することは、株式市場や金融庁・証券取引等監視委員会に波及するリスクを孕む。
それゆえ、報告書作成チーム(弁護士ら)が業界内の“波風”を抑えるため、あえて匿名にしたとすれば、それは単なる法的判断というより、市場秩序を守るための“実務的政治判断”とも読み取れる。
推察③ 実質的共犯性を持ちつつも“形式的適法”だった取引構造
循環取引はオルツ側が主導したものであり、ADKや大和証券は「関与はしていたが形式的にはルールに従っていた」とも受け取れる立場にあった可能性がある。たとえば、ADKは「広告宣伝費」としての発注を受けただけであり、それをどのように使うか、どのように戻ってきたかを「知らなかった」あるいは「営業担当者レベルの判断だった」と主張する余地がある。
同様に大和証券も、上場審査のプロセスにおいてオルツから提出された資料を「正当」と判断したに過ぎないとすれば、法的な責任追及の対象になりにくい。報告書側としても、「名前を出すが、責任は問えない」という矛盾を避けるために匿名化を選んだと考えられる。
オルツ事件は何を問いかけるのか
売上の9割が虚構だった企業が、堂々と上場を果たし、監査法人(シドー)・証券会社・広告代理店・VCがすべてその周囲に存在していた。これは単なる一企業の粉飾ではなく、日本のスタートアップ制度、証券審査、監査体制の「構造的緩さ」を象徴する事件である。
この構図を誰よりも早く看破したのが、アクティビスト投資家の田端信太郎氏である。2025年4月末、田端氏は自身のYouTubeチャンネルで「AIベンチャー・オルツの売上の9割は架空」との内部資料と証言を元に、循環取引スキームの全貌を告発。その中では、「広告宣伝費としてADKに1.2億円を発注 → ADKがジークス(ZYX INTERNATIONAL Inc.)に1.1億円送金 → ジークスがオルツのSaaS『AI GIJIROKU』をバルク購入(1億円)」という三角取引の存在を暴いていた。
実在しないプロダクトに、存在しないユーザー、流れるはずのない資金――それでも帳簿は“成立”していた。その“帳簿の物語”を、誰も疑わなかった。おそらく知っていた人は多かったろうが。
罪深い事件である。