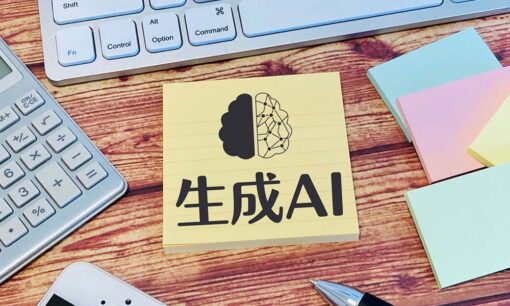欧州連合(EU)が策定した「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」が、2024年から段階的に適用を開始する。これに伴い、「欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)」も公表され、EU域内の上場企業はもちろん、日本企業でも欧州に一定規模の子会社を持つ場合などに対応が必要とされる見通しだ。
欧州委員会によると、CSRDは「環境・社会・ガバナンス(ESG)」に関する幅広い情報開示を義務づける強力な規制として、欧州域内の事業活動を中心に世界的な影響を及ぼす可能性があるという。
本稿では、CSRDおよびESRSの概要、並びに国際的なサステナビリティ報告基準との比較、そして企業が今後求められる対応について整理する。
国際的なESG情報開示の動向
近年、サステナビリティ開示に関する基準づくりが世界各地で活発化している。代表的なものとして、グローバル基準を目指す「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)」の基準、欧州連合(EU)のCSRD、および米国証券取引委員会(SEC)の開示規則が挙げられる。
- ISSB
国際会計基準審議会(IASB)の姉妹組織として設立され、投資家への情報提供を念頭に「気候関連開示(S2)」をはじめとする基準を公表している。今後は、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)のほかの領域にも段階的に拡大するとされる。ただし現時点では、投資家向けの財務的影響(ファイナンシャルマテリアリティ)を重視するシングルマテリアリティ志向が特徴である。 - SEC
米国の証券取引所に上場する企業を対象に、気候変動リスクなどを投資家に開示するよう求める規則案を公表している。州レベルではカリフォルニア州の気候関連情報開示法なども進行中であり、連邦と州で規制整備が並行しているかたちだ。 - CSRD
2024年1月以降、EU域内の上場企業に対して強制力のある形で適用が始まり、2025年からは大企業(非上場を含む)にも拡大していく予定だ。CSRDは投資家に限らない幅広いステークホルダーに向けた開示を重視し、企業が環境・社会に与える影響(インパクト)まで包括的に評価・開示を求める「ダブルマテリアリティ」が要となる。この点でISSBやSECの基準とは大きく異なる。
CSRDとESRSの概要
CSRD成立の背景と適用時期
歴史をおさらいすると、もともとEUでは「NFRD(非財務情報開示指令)」によってサステナビリティ報告を促してきた。しかしNFRDは法的拘束力が弱かった。各企業が独自に報告を作成する形式であったため、情報の比較可能性に課題が残った。そこで2019年に打ち出された「欧州グリーンディール」を背景に、環境と経済成長の両立を図るため、より厳格で統一的な開示ルールを課すCSRDが新たに成立。
2024年から上場企業で適用が始まり、2025年には大企業(上場企業でない場合も含む)に適用が拡大する。
具体的には以下のようなステップが予定されている。
- 2024年1月1日以降開始事業年度
EU上場企業が順次CSRDに基づく開示を開始。最初の報告は2025年に公表される見込み。 - 2025年1月1日以降開始事業年度
EU域内の大企業(売上高や総資産、従業員数などに一定基準)についても適用範囲を拡大。日本企業であってもEUに該当規模の子会社を有する場合、2026年からの開示が求められるケースがある。 - 2028年1月1日以降開始事業年度
EU域外に拠点を持つ企業(EU子会社を連結する親会社など)にも適用を広げる方針が示されている。適用の詳細は2026年6月までに整備される予定である。
CSRDの特徴
- 幅広いステークホルダーを重視
投資家に限らず、企業活動から影響を受けるあらゆる個人やコミュニティに対して開示する視点を導入している。 - ダブルマテリアリティ
企業が気候変動などから被るリスク・機会(ファイナンシャルマテリアリティ)だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響(インパクトマテリアリティ)も重要課題(マテリアリティ)として扱う。これは投資家中心のISSBなどが採用するシングルマテリアリティとは異なる。 - バリューチェーン全体への配慮
自社のみならず、サプライチェーン(上流・下流)全体で生じる重要なインパクトやリスク・機会を開示する必要がある。ただし、企業負担に配慮して初年度に一部免除措置も設けられている。
ESRS:CSRDにおける具体的な開示基準
CSRD自体は基本的な枠組みを定めた指令であり、実際の開示項目は「欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)」で詳細に規定されている。
- 基準の構成
全般的な要求事項を定めるESRS1・ESRS2に加え、環境(E)領域5本、社会(S)領域4本、ガバナンス(G)領域1本の計12本の基準書で構成される。 - 開示項目数
合計82の「開示要求事項」があり、さらに細分化された「データポイント」は700を超える。ただし、すべてを一律に開示するわけではなく、ダブルマテリアリティに基づいて重要と判断された項目のみを開示すればよい仕組みになっている。 - 段階的適用
GHG排出量(スコープ1・2・3)のうち、ファイナンシャルインパクトの定量報告を初年度は訂正的開示にとどめるなど、企業の負担を踏まえた段階的な免除規定が存在する。
CSRDと連動するEUタクソノミー
CSRDの適用対象企業は「EUタクソノミー規則」に基づくグリーン活動の割合(売上高・設備投資・経費に占める比率)なども開示しなければならない。EUタクソノミーは「何が環境的にサステナブルな経済活動か」を詳細に定義しており、企業は自社活動がどの程度グリーンに該当するかを算定・報告する。すでにEU上場企業では開示事例が出始めており、今後、日本企業のEU拠点でも対応が必要となる見通しだ。
CSRD・ESRSとISSB・SECの違い
大きな相違点は、CSRD・ESRSが「ダブルマテリアリティ」を採用し、投資家以外のステークホルダーや企業の外部影響も重視する点だ。これに対して、ISSBやSECは基本的に投資家向け情報の充実に重点を置き、企業の財務リスクや機会に焦点を合わせている。
ISSBとの関係
ISSBの開示基準(特に気候関連のS2)とESRS(E1)には類似点も多く、国際的な整合性を図るために相互運用可能だと両機関は表明している。ただし、ESRSのほうが企業による社会・環境への影響面を含め、より広範な項目が規定されている。一部異なる基準項目があるため、両方への対応が必要な企業は開示項目の重複・差異を精査する必要がある。
SEC基準との違い
SECは米国内の上場企業を対象とし、投資家保護を目的として気候変動リスクなどの開示を義務づける姿勢を強めている。CSRDと比べると対象範囲や開示内容が投資家向けに特化しており、EUにおける社会課題への配慮やバリューチェーン全体のインパクト開示などは、CSRDのほうが格段に包括的といえる。
今後の動向と企業対応
ムービングターゲットとしてのCSRD
CSRDは2024年から大企業に順次適用されるが、適用範囲の拡大だけでなくセクター別基準の策定や、第三者保証に関するレベル強化なども予定されている。さらに、CSRDに連動する「EUタクソノミー」や「企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)」、森林破壊防止規則などの新法令が相次ぎ導入される見込みだ。企業側にとっては、CSRDへの最初の対応がゴールではなく、刻々と更新されるEUサステナビリティ規制全般への継続的なフォローが必要となる。
日本企業への影響と対応プロセス
日本企業でも、EUに一定規模の子会社を持つ場合には2025年1月以降開始事業年度からCSRDが適用され、翌年に報告書を公表しなければならない。グループとして適用になってる日本企業もそろそろマテリアリティの分析を進めていることだろう。また、EU企業のレポートは出始めるハズで各社参考にしたいハズだ。
日本企業がCSRDおよびESRSへの対応を進めるにあたっては、一般的に以下のようなプロセスが取られる。まず、初期段階では、自社および関連子会社のサステナビリティ情報開示の現状を棚卸しし、EU基準との間にどのようなギャップが存在するかを明らかにする。このギャップ分析を通じて、具体的な対応が必要となる課題を洗い出す。
続いて、必要なデータ収集や組織体制の整備、さらにはシステム導入を視野に入れたロードマップを策定する。この段階では、目標達成までの具体的な行程表を作成することで、実行可能性を高めるとともに、取り組みの方向性を明確にすることが重要だ。
その後、実務に対応するための体制構築とプロセス整備が進められる。具体的には、サステナビリティ経営を統括する部署の設置や、リスク管理プロセスの見直しが含まれる。また、バリューチェーン全体の情報把握に向けた仕組みづくりを進めることで、ESRSで求められる広範な情報開示に備える。
さらに、こうした準備を経て、実際のデータ収集やステークホルダーとの連携を通じた開示書類のドラフト作成が試行段階として行われる。このプロセスでは、具体的な内容の検証を行い、必要に応じて修正を加えながら、本番に向けた実装を進める。
最終的に、本番開示を迎えた後も、企業は単に規制への対応で終わるのではなく、取り組みの成果や目標に対する進捗をモニタリングすることが求められる。PDCAサイクルを回すことで、開示内容を継続的にブラッシュアップし、実質的なサステナビリティ経営の強化を目指す。このように、制度対応を超えた戦略的な運用が、企業価値向上の鍵を握るといえる。
サステナビリティ経営への展望
CSRDをはじめとする各種開示基準は、単なる規制対応にとどまらず、企業が中長期的にサステナビリティ課題と向き合う契機となる可能性が大きい。環境負荷の削減、人権尊重、ガバナンス体制強化など、課題に対する実質的な取り組みが進めば、企業のレピュテーション向上だけでなくリスク回避や新たな事業機会の創出にもつながるだろう。
そのため、サステナビリティ開示を「経営戦略の一部」として位置づけ、明確なKPI設定や責任体制の構築を進める企業が増えている。欧州規制への対応は継続的な見直しが必要とされるが、これを将来的な競争優位や企業価値向上の好機と捉えて先行投資する動きはさらに広がっていくとみられる。
CSRDの下で実施される包括的なサステナビリティ報告は、企業活動を見つめ直し、社会や環境との共生を図るうえでの指針となる可能性を秘めている。世界的にも報告基準の整合化が進展しつつある今、日本企業としてもグローバルスタンダードを踏まえた「持続可能な経営」の実践が問われているといえよう。
【関連するおすすめ記事】
CSRDの対象となる日本企業の説明などは以下記事を。