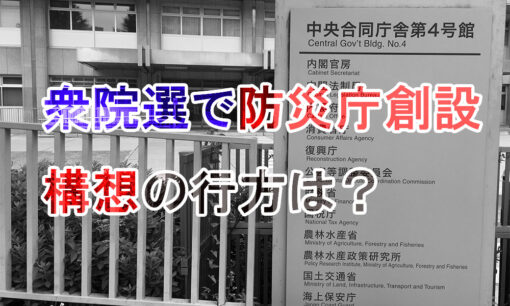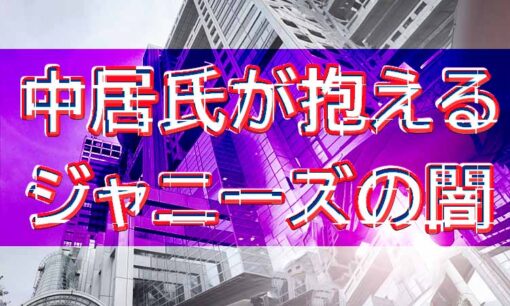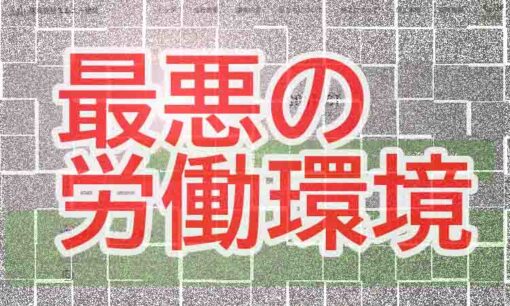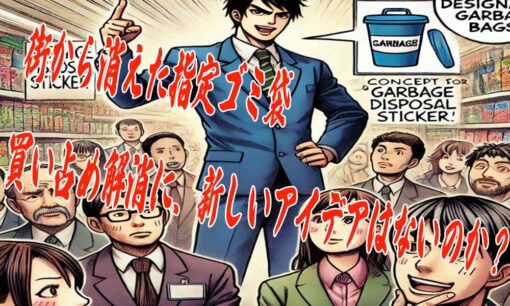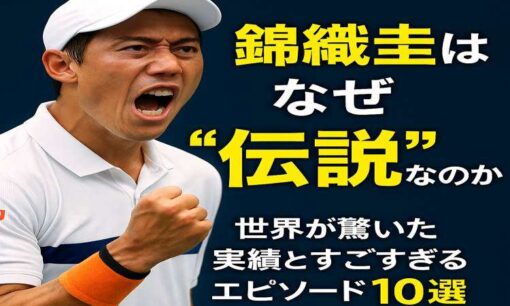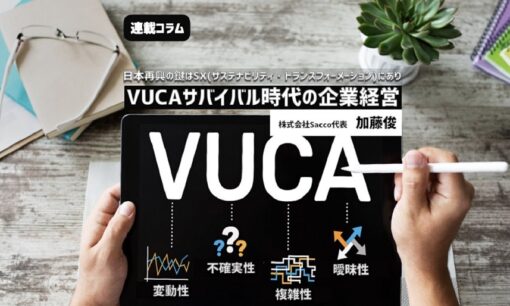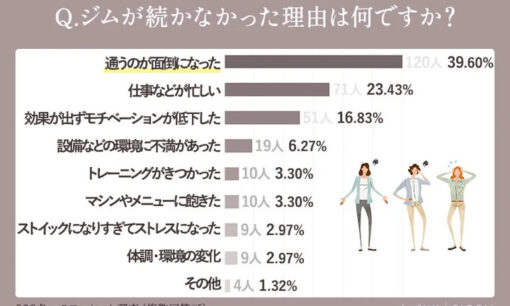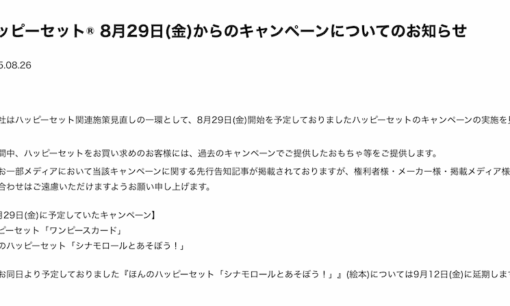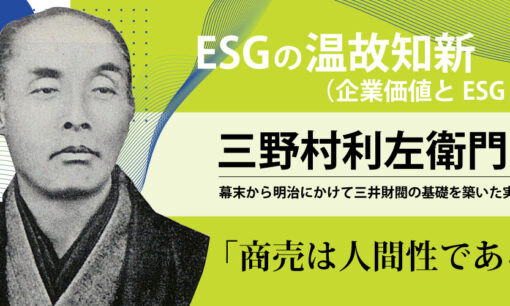石破首相が提唱する「地方分局」構想、防災庁の地方展開に注目集まる

政府が2026年度中の設置を目指す「防災庁」を巡り、全国の自治体による誘致活動が活発化している。石破首相が地方分局の設置を示唆したことを受け、これまでに12の道府県市と関西広域連合が名乗りを上げた。背景には、災害リスクの分散や地方創生への期待がある。
福島・石川・富山が強力に名乗り 自治体による誘致合戦が加速
福島県いわき市では、東日本大震災と福島第一原発事故の教訓を活かすべく、防災庁誘致を目指す期成同盟会が発足。小野栄重・いわき商工会議所会頭は「膨大な教訓や知見を国に還元するのは私たちの責務だ」と述べた。また、人口減少に歯止めをかける地方創生の成功モデルとしての期待も寄せられている。
能登半島地震の被災地である石川県も誘致に名乗りを上げた。馳浩知事は小松空港周辺への設置を求める要望書を提出し、「訓練、教育、バックアップ機能にふさわしい地政学的な立地だ」と強調した。
富山県の新田八朗知事も昨年12月に首相官邸を訪れ、県内設置を直談判。北海道や岐阜県、兵庫県なども産官学連携や防災人材の育成を理由に誘致を表明している。仙台市も政策要望書に設置を求める項目を盛り込む予定だ。
地方創生の切り札に?防災庁設置がもたらす経済波及効果
防災庁は石破首相の肝いり政策であり、昨年11月には内閣官房に「設置準備室」が発足。今年度の内閣府防災関連予算は昨年度の約2倍となる146億円に増額され、職員数も110人から220人に倍増された。政府は6月中に組織の概要を発表する予定で、誘致合戦はさらに激化する見通しだ。
一方で、誘致活動には課題もある。防災庁の機能や役割が明確でない中での誘致は、地域間の競争を過熱させる可能性がある。また、設置後の運用や人材確保、地域との連携体制の構築など、実効性のある組織運営が求められる。
海外の防災庁制度に学ぶ:FEMA・NEMA・CCSとの比較から見える教訓
海外の事例を見ると、アメリカの連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、災害対応の専門機関として機能している。FEMAは全国10か所に地域事務所を設置し、州や地方政府と連携して災害対応を行っている。また、イギリスの民間緊急事態事務局(CCS)は、各省庁との調整を担当し、緊急事態への対応を支援している。韓国では、国家緊急管理庁(NEMA)が災害対応の中心機関として機能している 。
日本版防災庁に立ちはだかる障害とは?実効性確保への課題
これらの事例から、日本の防災庁も地方分局を設置し、地域との連携を強化することで、災害対応の迅速化や効果的な支援が期待される。しかし、組織の設計や運用においては、明確な役割分担や情報共有体制の構築が不可欠である。
防災庁の設置は、災害大国・日本にとって重要な一歩となる。地方創生や地域の防災力強化にもつながる可能性があるが、実効性のある組織運営と地域との連携体制の構築が求められる。今後の政府の動向と各自治体の取り組みに注目が集まる。
さて、以下では福島県・いわき市に実際に防災庁が設置されたらというシミュレーションをしてみよう。
もし「福島・いわき市」に防災庁が設置されたら? 災害の記憶と知見を未来につなぐ街へ
仮に防災庁の本庁舎が、福島県いわき市に設置されれば、同市は「防災のまち」として国内外から注目を集めることになるだろう。東日本大震災と東京電力福島第一原発事故という複合災害の経験をもついわき市は、災害の現場で蓄積された知見を実地に継承する最適地といえる。
設置後は、大学や高専に防災工学や危機管理を学ぶ学科が新設される可能性がある。全国から若者が集まり、彼らは卒業後に市内の研究機関や公的機関に就職することで、慢性的な人口減少と若年層の流出に悩むいわき市に新たな定着の流れが生まれる。
また、防災庁が国際的な災害対応の拠点としての役割を果たすようになれば、いわき市では国際会議や研修事業が頻繁に開催されるようになるだろう。アジア各国の行政官や研究者が集い、被災地としての経験と教訓を共有する場としての機能も期待される。こうした動きは市内の宿泊・飲食産業、交通インフラにも波及し、観光との相乗効果による経済効果も小さくない。
さらに、いわき市は首都圏から電車で2時間半という距離にあり、首都直下地震などの大規模災害発生時には、東京の中央省庁の一部機能を受け入れる「臨時官庁都市」としての役割も担うことができる。これは、防災庁が単なる地方分局ではなく、「国の中枢機能の分散拠点」として構想されている場合にとりわけ重要となるだろう。
本当に地方創生につながるのか?
ただし、防災庁の設置が地元にとって恩恵ばかりとは限らない。地域住民の間では、官庁街ばかりが整備されても、雇用創出には直結しないのではないかという疑念や、復興予算との線引きが不明確になり、地域の自治に影響が出ることへの懸念も聞かれる。また、防災庁に勤務する職員の多くが中央からの出向や転勤者である場合、地域に根ざした人材が育たないまま、単なる「通勤都市」になってしまう危険性もある。
それでも、いわき市が防災庁誘致を目指す背景には、自らが背負ってきた災害の記憶と、それに対峙してきた人々の経験を、次の災害に備える国家の知見として昇華したいという切実な思いがある。もしこの構想が実現すれば、いわき市は「被災の地」から「防災の中枢」へと歩みを進めることになるだろう。その歩みは、全国の被災地にとっても、新たな再生モデルとなり得る。