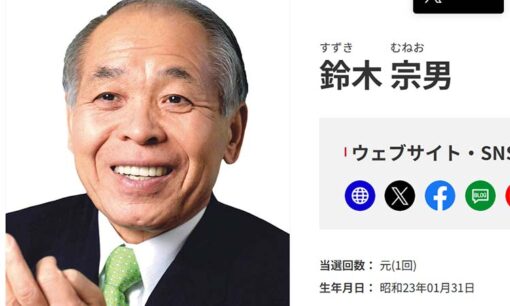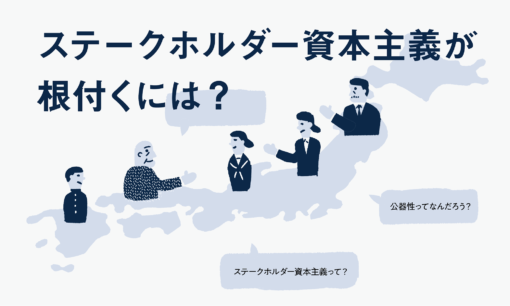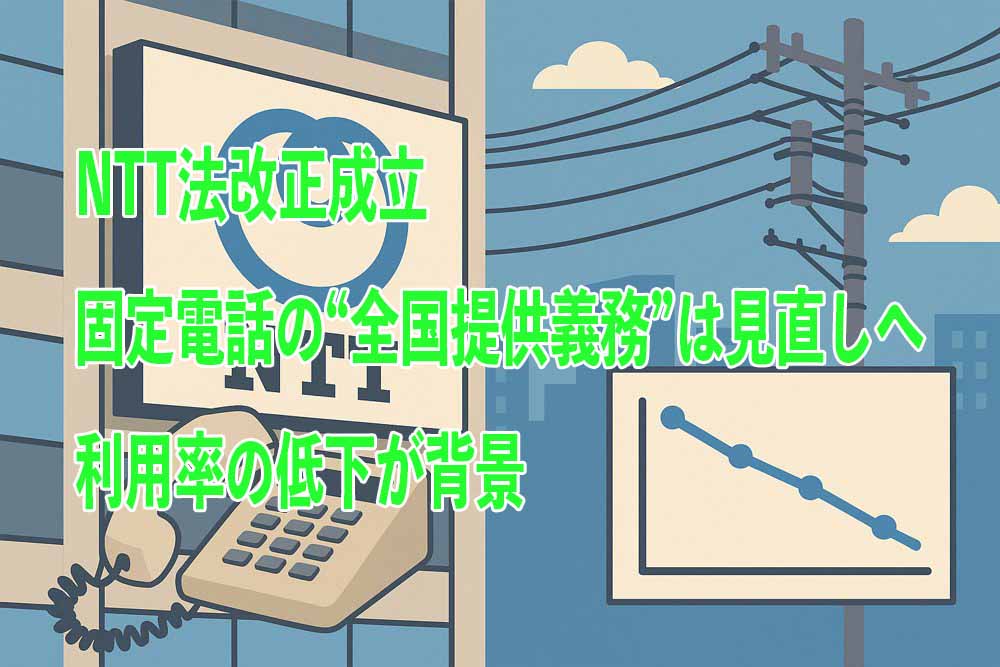
NTTが全国一律で固定電話サービスを提供する法的義務が見直されることになった。2025年5月21日、NTT法などの改正案が参院本会議で可決され、成立した。改正により、固定電話の提供義務は「他に通信事業者がいない地域」に限定される方向へと転換する。
■ 固定電話の「全国義務」見直しの背景
NTT(日本電信電話株式会社)は、旧・電電公社を前身とし、長らく全国の固定電話網を整備・維持してきた。しかし、スマートフォンの普及やインターネット通信の発達により、固定電話の利用者数は大きく減少。NTT東西が担う固定電話事業は、近年赤字が続いている。
こうした状況を受け、政府はNTTに課されていた「全国一律での固定電話提供義務」を見直す必要があると判断。今回の法改正により、今後は「NTT以外に固定電話サービスを提供する事業者が存在しない地域」に限定してNTTがその提供義務を負うことになる。
■ 利用率の低下が続く固定電話
実際に、固定電話の利用率は顕著に低下している。総務省などの調査によれば、2022年時点での全世帯における固定電話の保有率は58.1%。これは前年の66.5%から2.5ポイントの減少を示しており、固定電話を保有しない世帯が増加している。
さらに、年齢層別に見るとその傾向は顕著であり、20代の世帯主を持つ世帯では固定電話の保有率はわずか5.4%にとどまる。代わりに携帯電話やスマートフォンが主たる通信手段となっており、通信環境の主流が大きく変わっていることが分かる。
契約数の推移もこれを裏付ける。固定電話の契約数は2001年度末の約6,105万回線をピークに減少を続け、2014年度末には約2,556万回線にまで落ち込んでいる。一方で、携帯電話やPHSの契約数は同期間で倍増しており、通信市場全体が移動体通信中心にシフトしている。
■「通信のセーフティネット」は維持
一方で、すべての固定電話義務がなくなるわけではない。携帯電話の電波が届きにくい山間部や離島など、他の通信事業者による代替サービスが存在しない地域については、引き続きNTTが最後の砦としてサービスを提供することが求められる。
総務省はこの変更にあたって、いわゆる「通信のセーフティネット」を崩さない方針を強調している。具体的には、対象地域の明確化やモニタリング体制の構築を進める予定だ。
■ 電柱や管路の譲渡に「認可制」導入へ
また、今回の法改正では、NTTが保有する電柱や管路などの通信インフラについて、譲渡の際に政府の「認可制」を導入することも盛り込まれた。
これらのインフラは旧電電公社から受け継がれた公共的性格の強い資産であり、NTTが仮にそれらを第三者に譲渡した場合、地域の通信基盤に重大な影響を及ぼす可能性がある。そのため、一定の管理を国が引き続き行う必要があると判断された。
■ 外資規制・国の株式保有は継続
NTTに対しては現在も政府が約3分の1の株式を保有し、外国資本による過度な影響を防ぐための外資規制が設けられている。今回の改正でも、これらの制度は維持されることとなった。
■ 施行時期は最大で2年後に
法改正の施行は、原則として公布から1年以内とされているが、NTTの提供義務の変更に関する部分については、準備期間を考慮し「2年以内」の施行とされている。今後、詳細な施行スケジュールや対象地域の判断基準について、総務省が具体的な制度設計を進めていく方針だ。