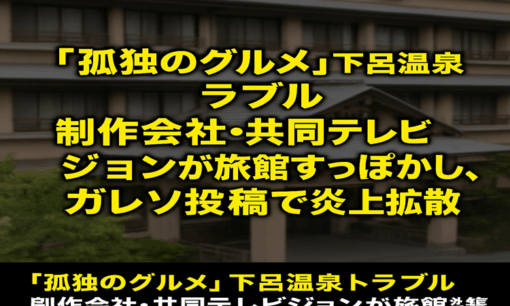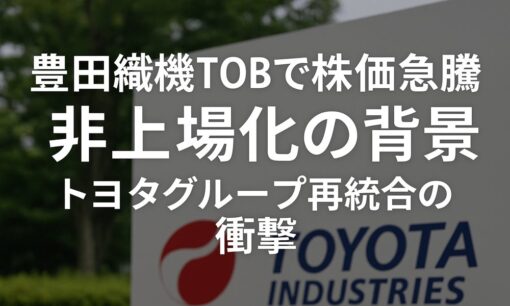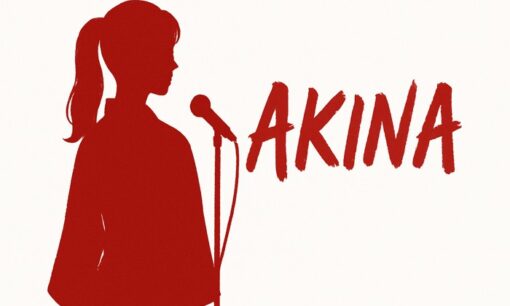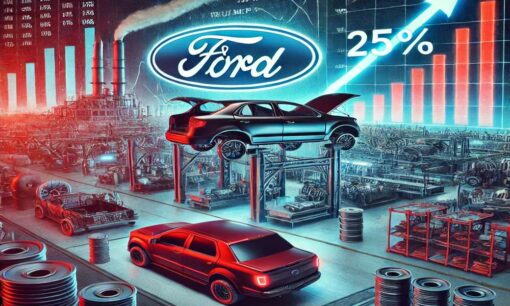バチカン、復活祭直後の訃報
バチカン(ローマ教皇庁)は4月21日朝、ローマ教皇フランシスコが同日7時35分、教皇公邸カサ・サンタ・マルタで死去したと発表した。88歳だった。2月中旬から肺炎などで38日間にわたり入院し、先月下旬に退院。20日には復活祭ミサに合わせてサンピエトロ広場に姿を見せたばかりだった。
1936年12月17日、アルゼンチン・ブエノスアイレス生まれのホルヘ・マリオ・ベルゴリオは2013年3月、史上266代目、初の南米出身のローマ教皇に選出され、在位は12年1か月。貧者への連帯と教会改革を旗印に、平和外交にも力を注いだ。
教皇を彩った逸話 質素と行動力の人
フランシスコ教皇には、就任翌朝に自ら宿泊費を支払いに出向いた逸話がある。教皇専用車を避け、一般車フィアットで移動した司祭時代の習慣を生涯貫き、アルゼンチンでは地元クラブ「サン・ロレンソ」の優勝を路線バスでファンと祝ったという。選出直後、40年来新聞を届けてくれた売店に電話し「紙はもう要らない、少し忙しくなる」と告げた笑い話も残る。
復活祭の足洗い儀式では刑務所を訪れ、イスラム教徒や女性受刑者の足にも口づけした。深夜に私服でバチカン外を歩き、路上生活者へ食事を配っていたと伝えられ、同性愛者をめぐっては「私が裁くなどありえない」と発言して世界の喝采と保守派の反発を同時に呼んだ。
機上では自らの黒い布製ブリーフケースを携え、黄金ではなく鉄製の指輪を選び、防弾パパモビルを拒んで開放式ジープに乗る姿勢も象徴的だった。質素、行動力、ユーモアが同居する人柄がカトリックの枠を超えて共感を呼び続けた。
イエズス会とは? 知と奉仕のグローバルネットワーク
イエズス会は1540年、元兵士イグナチオ・デ・ロヨラが教皇パウルス三世の承認を得て創設した。「より大いなる神の栄光のために」を標語に掲げ、厳格な霊操と教皇への特別誓願を特色とする。会員は“教会の先遣隊”と呼ばれ、フランシスコ・ザビエルやマテオ・リッチらがアジアで宣教と学術交流を展開し、天文学や地図学の発展に寄与した。
現在は約200校の大学・高校を運営し、難民支援や人権擁護にも注力。「知」と「社会正義」を両輪に動く国際ネットワークはときに「教会の外交官」あるいは「黒衣の権力集団」と評されてきた。例えば、日本には上智大学があるが、これはイエズス会の支援により設立された大学である。いまも上智大学に併設されるイグナチオ教会は、日本のカトリック教会においては最大規模の教会として有名であり、イエズス会の神父や修道士たちが運営している。
イエズス会は、18世紀末に王権と衝突して一時解散に追い込まれたが1814年に復活。20世紀以降は中南米の軍政と対峙した解放の神学で注目を浴びるなど、体制批判の尖兵としても機能する。「軍隊的規律と知的自由を両立させる稀有な組織」と評されるゆえんであり、フランシスコ教皇の改革志向はまさにこの伝統の延長線上にある。
SNSに広がる惜別の声
政治学者の白鳥浩・法政大学教授は「心を痛める出来事の多かった時代に命の重みを問い続けた教皇の影響力を改めて痛感する」とSNSに投稿。国際関係学者の三牧聖子・同志社大学教授は、米国の排外的政策に言及し「教皇がどれほど憂慮していたか想像に難くない」と記した。
一般ユーザーからも「最後の力を振り絞った復活祭ミサは“職務を愛し抜く覚悟”そのもの」「改革途上で逝ったが、その意思を受け継ぎたい」といった弔意が相次ぎ、ハッシュタグ #GraciasFrancisco が世界のトレンド上位に浮上した。