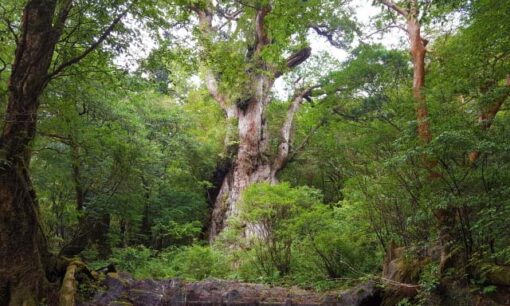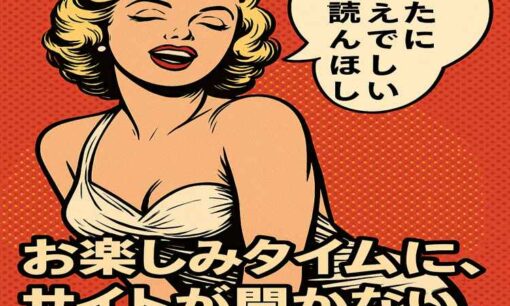2024年7月3日、20年ぶりに刷新された新紙幣(1万円札、5千円札、千円札)の発行が始まった。これを契機に、一部の事業者の間では「現金対応をやめ、キャッシュレスへ完全移行する」という動きが広がりつつある。
政府は将来的にキャッシュレス決済の利用比率を8割まで引き上げる目標を掲げ、2024年の実績では42.8%(経済産業省)と過去最高を記録した。消費者の間ではキャッシュレスの利便性が日常に浸透する一方で、現場の小売店や中小事業者からは「手数料負担が重い」との声も上がっている。キャッシュレス決済がもたらす光と影について、改めて整理する。
消費者にとっての利点:利便性とポイント還元
キャッシュレス決済の最大の利点は、利便性にある。現金を持たずにスマートフォンやカード一枚で決済が完結し、レジ待ち時間の短縮や釣銭ミスの防止にもつながっている。QRコード決済やクレジットカードではポイント還元がある場合も多く、消費者にとっては経済的メリットもある。
また、感染症対策の一環として非接触型決済が推奨される場面が増え、利用機会も急増した。
店舗側の利点:業務の効率化と売上増加
ITジャーナリストの三上洋氏によれば、キャッシュレス決済の導入により店舗運営の効率化が期待できる。現金管理の手間や偽札リスクが軽減され、セキュリティ面での負担も減る。また、キャッシュレス対応店舗というイメージが、消費者からの選択肢として有利に働くケースもあるという。
一方で、キャッシュレス未対応店舗が近隣にある場合、「機会損失」が目に見える形で生じることもある。実際に、自動販売機の事例では、1台がキャッシュレス化されたことで他の9台も追随したという報告がある。
導入率は全国で8割超も、地域差や業種によるばらつき
経済産業省が2021年に実施した調査では、全国の中小企業におけるキャッシュレス決済の導入率は約80%に達している。特に飲食業、小売業、宿泊業では導入が進んでおり、東京都の調査によれば、都内のキャッシュレス決済比率(2023年度)は57.6%に上昇している。
一方で、地方部では依然として現金決済が主流であり、導入が進まない業種も存在する。設備投資の負担や手数料への抵抗感が背景にある。
手数料が重荷に 小規模店舗の現実
キャッシュレス導入に慎重な声として最も大きいのが「加盟店手数料」である。一般に決済手数料は2~3%程度で、これが低利幅の商売にとっては大きな負担となる。
例えば、1,000円の商品を売って100円の利益を得る場合、3%の手数料が取られれば利益の約3割が消える計算になる。さらに振込手数料や月額固定費が発生する決済事業者もある。
新紙幣で現金対応にコスト増 キャッシュレス移行の後押しに
2024年7月の新紙幣発行により、紙幣を読み取る機器の更新が求められている。自動販売機、券売機、両替機などの旧型設備ではソフトウェアの対応が難しく、物理的な機器交換が必要となるケースも多い。
こうした機器の更新コストを抑える目的で、「現金決済をやめ、キャッシュレスに一本化する」という判断をする事業者が出てきている。JR東海バスでは、新紙幣に対応した運賃箱の導入を見送り、現金払いを縮小する方針を採った。飲食店でも、現金非対応のキャッシュレス専用券売機を導入する例が増えている。
とはいえ、高齢層やスマートフォンを使い慣れない層にとって、完全キャッシュレスは必ずしも歓迎されるとは限らず、導入には一定の配慮が必要とされる。
利用者と店舗、双方にとって「良い仕組み」にするには
キャッシュレス決済を真に「誰にとっても便利な仕組み」とするためには、以下のような制度整備と工夫が求められる。
- 手数料の透明化と見直し
手数料の内訳を明示し、規模に応じた柔軟な体系を提供することで中小事業者の負担を軽減する必要がある。 - インフラ整備への公的支援
自治体や商工会を通じてPOSレジや端末の導入支援、無料研修などを行い、導入のハードルを下げる。 - セキュリティ体制の強化と補償制度の整備
スマホ紛失時のロック機能や、返金保証制度の標準化など、利用者が安心して使える仕組みが求められる。 - 高齢者・デジタル弱者への配慮
アプリの簡素化や使い方の説明会など、地域と連携した啓発活動が効果的である。 - 現金との併存を前提とした運用
完全キャッシュレス化ではなく、選択肢を用意する“併存型”の設計が現実的である。
自分に合った決済方法を選ぶ時代へ
キャッシュレス決済は、効率化と利便性を備えた現代の決済インフラとして期待される一方、制度的なサポートや文化的受容がなければ、普及が一部にとどまる可能性もある。重要なのは、利便性を一方的に押し付けるのではなく、使う人・提供する側の両者が納得できる形で共存できる環境をつくることである。