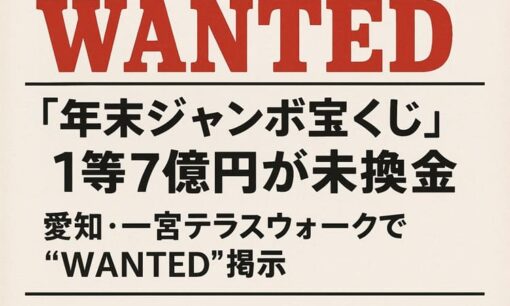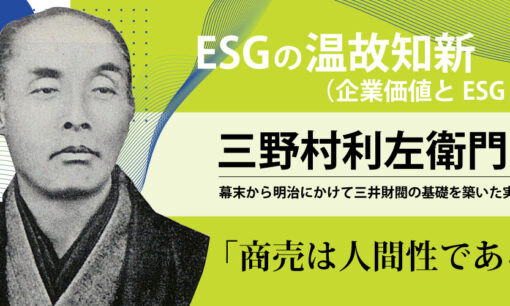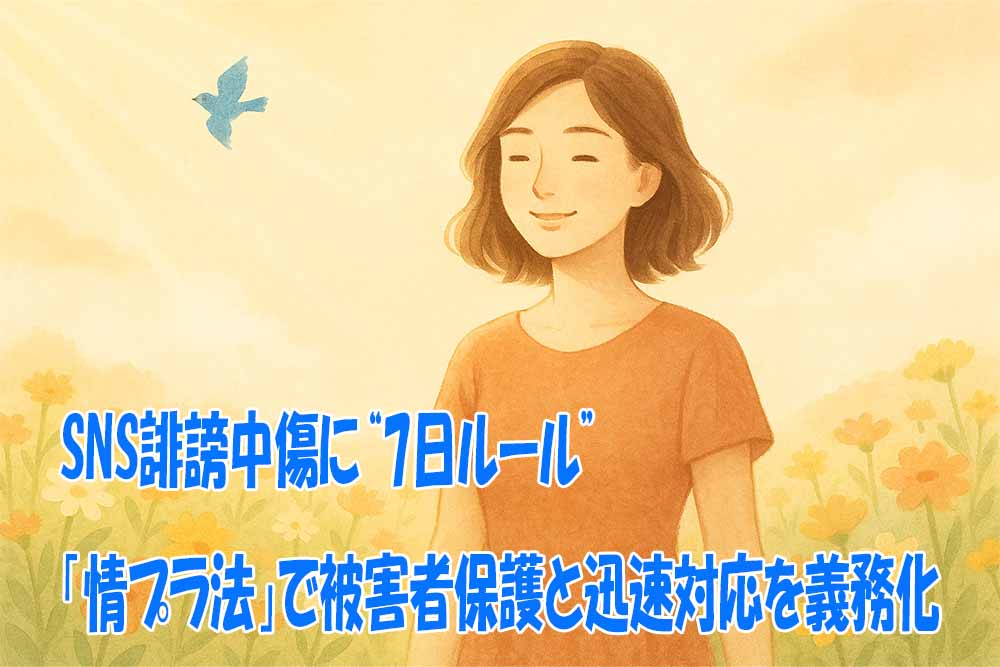
2025年4月1日、SNS運営事業者に法的義務と罰則を課す新たな法律「情報流通プラットフォーム対処法(通称:情プラ法)」が施行された。
この法律は、X(旧Twitter)、Instagram、YouTubeなどの大規模SNS事業者を対象に、投稿削除対応や通知義務を定め、違反時には最大1億円の罰金が科されるという日本初の仕組みを導入している。
この法律は、誹謗中傷の被害を受けた利用者が適切な救済を受けられるようにすることを目的としており、背景にはこれまでの制度上の課題と、深刻な事件の発生があった。
新法が生まれた背景 “被害者が声を上げても、支援も処罰も届かない”現実
情プラ法が施行される以前、SNS上での誹謗中傷やプライバシー侵害に対しては、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、民法の不法行為責任などで対処されていた。しかし、加害者の特定には多くの手間と時間がかかり、SNS事業者による情報開示もスムーズとは言えなかった。
また、被害者が投稿削除を求めた際には、「削除依頼の窓口がない」「削除基準が曖昧」「申請後に返答がない」などの問題が頻出し、解決までに数か月を要する例も珍しくなかった。
こうした制度の隙間により、誹謗中傷の被害を受けても声を上げられず、心身に大きな影響を受けるケースが後を絶たなかった。
その象徴的な出来事が、2020年5月、フジテレビ系の番組「テラスハウス」に出演していた木村花さんが、SNS上の誹謗中傷を受けて自ら命を絶った事件である。社会に衝撃を与えたこの事件以降、SNS上の人権侵害への対応強化を求める声が急速に高まった。
加えて、総務省によると、「違法・有害情報相談センター」には2023年だけで6463件の相談が寄せられており、誹謗中傷や不適切投稿に関するトラブルは深刻な社会問題として浮上している。
情プラ法とは ――何が義務になり、どう変わるのか?
今回施行された「情報流通プラットフォーム対処法」は、既存の「プロバイダ責任制限法」(2002年施行・2021年改正)を補強し、投稿削除の対応義務を明文化した点に特徴がある。主なポイントは次の2つに分かれる。
① 発信者情報開示に関する規律(既存法の延長)
加害者の特定や損害賠償請求を行うため、SNS事業者に対して、発信者の氏名やIPアドレスなどの開示を求める制度。これはプロバイダ責任制限法のもとでも存在していたが、今回の法律で対象事業者がさらに広範に指定されることになる。
② 投稿削除に関する新たな規律(今回新設)
- 被害者本人または代理人から投稿削除の申し出があった場合、大規模SNS事業者は7日以内に削除するかどうかを判断し、その結果や理由を通知しなければならない。
- 対応が7日以内に困難な場合は、その理由を説明する通知を出す義務がある。
- 日本語で分かりやすい削除窓口の設置、判断基準の策定と公表、年1回の報告義務(削除依頼件数・対応数など)も義務づけられる。
もしこれらの命令に従わなければ、最大1億円の罰金が科される。これは日本国内で初めて、SNS事業者に対して明確に金銭的な罰則を規定した法律となる。
対象となる「大規模SNS事業者」とは?
情プラ法の対象は、以下いずれかの条件を満たすSNS事業者である。
- 月間アクティブユーザー数が1000万人以上
- 月間投稿数が200万件以上
今後、総務省が対象事業者を指定し、指定から3か月以内に必要な体制整備や届け出を行う必要がある。主に、X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、Facebookなどの主要SNSが想定されている。
削除依頼が認められるのは「本人からの申請」のみ
本法律において注意すべき点として、削除申請の対象は「被害者本人」またはその代理人に限られることがある。第三者による申請については、明確な権利侵害が確認できる場合に限り、対応が望ましいとされるが、法的義務は発生しない。
専門家「表現の自由を脅かすものではない」
SNSの規制が強まることで「表現の自由が脅かされるのでは」との懸念に対し、国際大学の山口真一准教授は次のように指摘する。
「この法律は政府が恣意的に投稿を削除するためのものではない。むしろ事業者に適切な対応を促す枠組みであり、迅速な対応が被害拡大の防止につながる。表現の自由を脅かすものではないと考えている」
利用者にとって「安心できるSNS環境」へ一歩
SNS事業者に対する明確な法的責任が規定されたことで、被害者が泣き寝入りせずに済む環境が整い始めた。今後は、対象事業者が体制をどう整備し、削除対応をどれだけ迅速かつ丁寧に行うかが、実効性を左右する鍵となる。
情プラ法の本格的な運用を通じて、表現の自由と被害防止を両立したSNS空間が実現するかが注目されている。