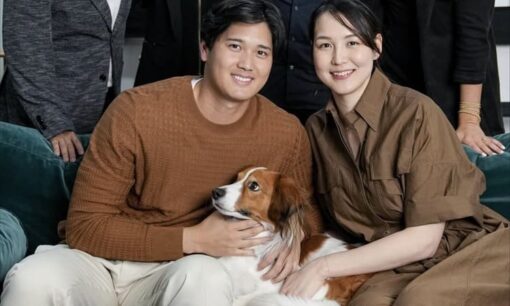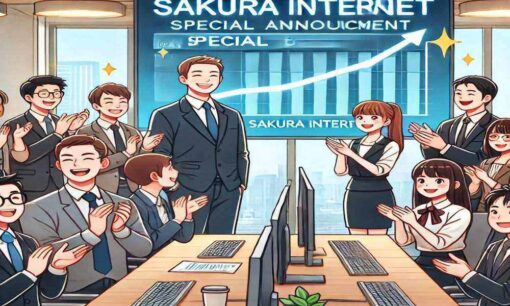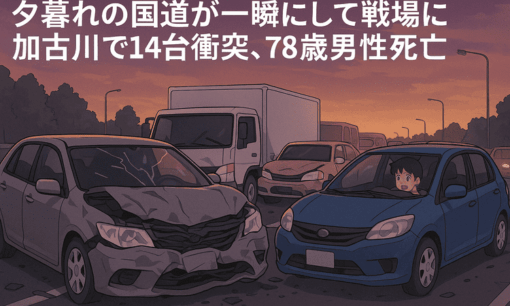災害時の通信手段として注目される「特設公衆電話」の設置が全国で増加している。2011年の東日本大震災を契機に事前設置の必要性が高まり、設置台数は10年余りで約10倍に拡大した。通信障害が広範囲に及ぶ可能性がある南海トラフ巨大地震などの事態を見据え、目立たぬ存在ながら「最後の通信手段」としての役割が改めて評価されている。
災害時専用、公衆電話とは異なる特設回線
特設公衆電話は、NTT東日本およびNTT西日本が避難所や防災拠点などに事前に設置している災害対応用の電話である。災害時には無料で通話ができるほか、停電時でも使用可能で、一般回線よりもつながりやすいという特長がある。東日本大震災では、最大約190万回線の固定電話が不通となり、携帯電話の基地局も多数停止した。通信の集中による規制も行われ、多くの地域で連絡手段の確保が困難となった。
この経験を踏まえ、特設公衆電話は従来の「災害後に設置する」方式から「平時から設置しておく」方式へと転換された。2023年度時点での設置台数は約8万9千台となっており、2011年度の約9千台から大きく増加している(NTT西日本による)。
見えない電話、目立たぬ存在
特設公衆電話は、一般的な公衆電話とは異なり、街頭などには設置されていない。多くは小中学校や公民館などの避難所に設けられており、施錠された倉庫や管理室などに格納されている。外観も一般の公衆電話と同様のため目立ちにくく、地域住民でもその存在に気づいていないケースが多い。
例えば京都市では、指定避難所431カ所のうち、各学区の小学校を中心に224カ所に1台ずつ特設公衆電話が設置されている。滋賀県においても、2016年度には36台だった設置数が2023年度には122台まで増加している。また、2024年の能登半島地震では、避難所などで187台が実際に活用されたという(京都新聞による)。
設置場所はどこにあるのか
多くの特設公衆電話は、災害時に避難所として機能する小学校や公民館、市民センターなどに設置されている。NTT東日本およびNTT西日本は、特設公衆電話の設置場所をそれぞれのウェブサイト上で公開しており、市区町村名や郵便番号を入力することで、最寄りの設置箇所を確認できる。
- NTT西日本「災害用公衆電話設置場所検索ページ」:https://www.ntt-west.co.jp/saigai/denwa/
- NTT東日本「災害時公衆電話一覧」:https://www.ntt-east.co.jp/saigai/telephone/
NTT西日本は「特設公衆電話が設置されている避難所をあらかじめ把握し、災害時の連絡手段として活用してほしい」と呼びかけている。
利用方法の周知と課題 特設公衆電話の使い方
特設公衆電話は、災害時に開設された避難所などで使用可能となるもので、平常時には使用できない。基本的な操作は公衆電話と同様だが、いくつかの注意点がある。
以下は、災害時における特設公衆電話の使用手順と注意点である:
- 使用可能かを確認する
- 避難所の開設に伴い、NTTが回線を開通させた場合にのみ使用可能となる。
- 防災担当者に確認するのが確実である。
- 電話機の場所を探す
- 管理室、防災倉庫、校舎の廊下など、目立たない場所に設置されている。
- 受話器を上げてダイヤル
- 硬貨やテレホンカードは不要。
- 通話先の市外局番を含む番号をそのまま入力する。
- 携帯電話、固定電話、災害伝言ダイヤル「171」などにも発信可能。
- 通話は簡潔に
- 多くの避難者が利用する可能性があるため、できるだけ短時間で通話を終える。
- 通話後は受話器を戻す
- 正しく戻すことで、次の人が使用しやすくなる。
- 停電時でも使用可能
- 電力供給が停止している状況でも、通信手段として利用できる設計となっている。
このように、特設公衆電話は「使い慣れた公衆電話」の延長線上にあるが、使用条件や設置場所については事前の理解が必要となる。
南海トラフ巨大地震の被害想定では、最大580万回線(固定電話)が不通になると見込まれており、特設公衆電話は通信インフラの補完策として欠かせない存在である。
普段の生活の中では目にすることのない特設公衆電話。しかしその存在を知り、設置場所を把握しておくことは、いざという時に家族や地域を守る力となる。