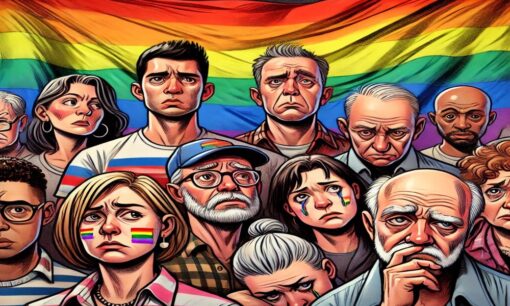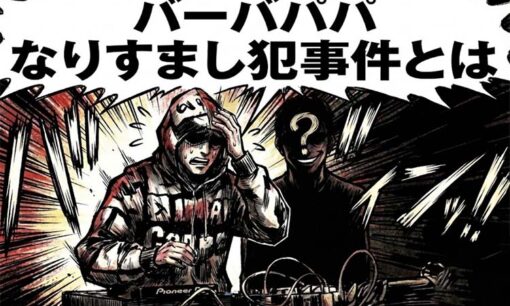立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3党は10月15日、党首会談を約1時間実施したが、連立の枠組みや基本政策で折り合えず、幹事長協議を挟んで週明けに再会談する方針とした。テレビ朝日系(ANN)によると、立憲の野田佳彦代表は「野党候補一本化」の政権構想を提示した一方、国民の玉木雄一郎代表は参院で過半に届かず少数与党になる現実を指摘。安全保障・原発・憲法観の隔たりも埋まらなかったという。
政策の“距離” なぜ合意できないのか
今回の不調は、個別論点での「妥協不足」ではなく、3党のベースとなる政策座標の違いに起因する。立憲は「原発ゼロ維持」「改憲に慎重」「抑制的な安保」を掲げ、価値軸はリベラル寄りに位置づく。維新は「憲法改正・統治改革」「市場原理・規制改革」を推進し、中道右派の改革志向が強い。
国民は「現実的改憲議論」「エネルギーミックス重視」など中道路線で、与野党いずれにも橋を架けうるが、だからこそ両極の間で合意形成コストが高まる。ANNの報道で示された“安保・原発・憲法”という3点セットは、各党の座標を最もくっきり浮かび上がらせる検査項目であり、一本化交渉の「関門」になっている。
1993年“非自民連立”の記憶。今回とどこが違うのか
30年前の細川連立政権は、非自民・非共産の8党派が「政治改革」という明確な単一アジェンダで結束し、短期の“特命政権”として成立した。選挙制度改革という到達点を共有できたからこそ、思想信条の差異を一時的に棚上げできたのである。
公明党の党史資料や研究論文、当時の整理でも、連立の要は“共有する目的の明確さ”にあったことが確認できる。現在の3党協議は、物価・賃上げ・安全保障・エネルギー・統治改革と論点が多岐に広がる一方、単一の「旗」が立っていない。この差が、歴史的再現を阻む最大要因だ。
「野党一本化」という物語 メディアは何を映してきたか
政治イベントのたびに“野党一本化”というフレーズが先行しがちだが、今回も事前のテレビ解説やライブ配信は「会談が野党連携にどうつながるか」を見出しに据え、構造的な政策距離の説明は相対的に乏しかった。ライブ中継は可視性を高める半面、「連携成否」という勝敗の物語へ焦点を収斂させやすい。結果として、視聴者は“誰が組むか”を追う一方で、“何を共有できるか”という本質議題が置き去りになりがちである。
今回の会談後の報じ方でも、時間軸(参院の議席現実)と政策座標の二重の制約が並立している事実こそが核であり、そこへの解像度を高めるのが報道の役割だ。
“誰と組むか”から“何で組むか”へ
次の党首会談までに、3党が合意の土台に据えうる“単一かつ限定的な旗”—たとえば「家計の実質所得回復に直結する税・社会保険料の当面措置」や「規制改革の優先10案件」など—を持てるかどうかが試金石となる。30年前の教訓が示すのは、理念の全一致ではなく、期限と範囲を限定した“特命合意”の設計である。逆に言えば、それが描けない限り、野党協議は政局の物語に消費され続ける。