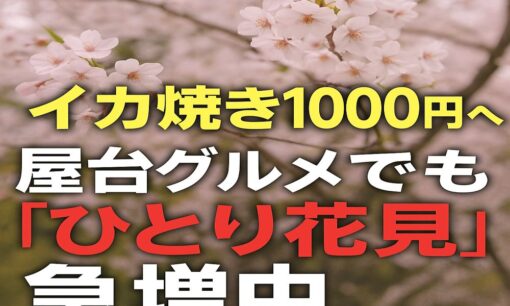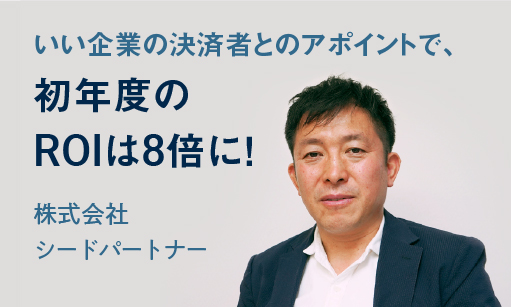東京世界陸上第7日の男子400メートル障害決勝で、米国のライ・ベンジャミンに起きた「金メダル→失格→金メダル復活」という波乱は、競技場を混乱させただけでなく、審判判定の透明性やスポーツの公正さにも疑問を投げかけた。最終的にベンジャミンは金メダルを手にしたが、その過程で残された課題は少なくない。
金から失格へ 理由は「ハードルの移動」
決勝では序盤から飛ばしたベンジャミンが圧倒的リードを築いた。しかし最後のハードルに足を引っかけてバーを倒し、スピードを落としながらなんとかトップでゴール。ところが直後に失格が告げられた。理由は「自分または隣レーンのハードルを移動させ、他選手に影響を与えた可能性がある」というものだった。
この時点で、2位のブラジルのアリソン・ドスサントスが一度は金メダルに繰り上がった。
抗議で判定覆る 金メダル復活の舞台裏
ところが米国チームが抗議を行い、数十分後に失格は撤回。最終的にベンジャミンが金、ドスサントスは銀に確定した。抗議が認められた背景には、「隣のレーン選手への実害が確認できなかった」ことがあるとされる。
ベンジャミンは「DQと聞いた時は『What?』と驚いた。もちろん故意ではなかったが、自分の責任でもある。こんな経験は初めて」と胸中を明かした。
敗者の心境「奇妙な気持ち」
一時は金に繰り上がったドスサントスは「奇妙な気持ちだった。一瞬だけ金を取ったような感覚になった」と複雑な思いを吐露。その上で「金を取るなら失格ではなく速さで勝ちたい」と潔く語った。勝負の世界で、真に欲しいのは「自力で掴む金」であることを示した。
会場と世論が揺れた理由
判定が二転三転したことで、報道エリアの海外記者も規則を確認し合い、場内は騒然となった。観客やSNS上では「アメリカだから覆ったのでは」「日本人選手の抗議は通らなかったのに」といった不満も噴出。
同じ大会では、男子3000m障害の三浦龍司が接触を受けて失速した場面で日本の抗議が棄却されており、「なぜ今回は通るのか」という比較も議論を呼んでいる。
公正性をどう担保するか
今回の一件は「妨害か否か」を巡る判定基準の曖昧さを浮き彫りにした。ハードル走では接触やバーの倒壊は珍しくなく、故意か偶発かの判断は難しい。しかし一度の裁定がメダルの行方を大きく左右する以上、説明責任や透明性は不可欠だ。
公平性を疑う声が広がれば、選手も観客も競技への信頼を失いかねない。世界陸上の権威を守るためには、今後のルール整備や判定基準の明確化が急務となる。
混乱の先に求められるものは透明性
最終的にベンジャミンは金、ドスサントスは銀に落ち着いた。しかし観客やファンの記憶に残るのは、表彰台の順位ではなく「判定が二転三転した混乱」だっただろう。競技者の努力を正当に評価するためにも、国際陸連には公正な裁定と説明の徹底が求められている。