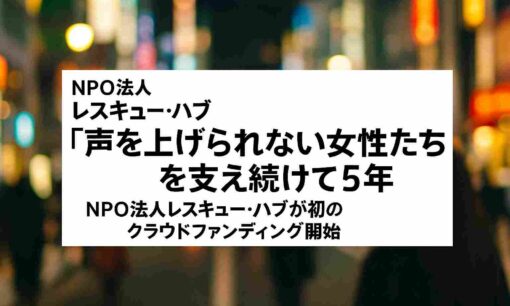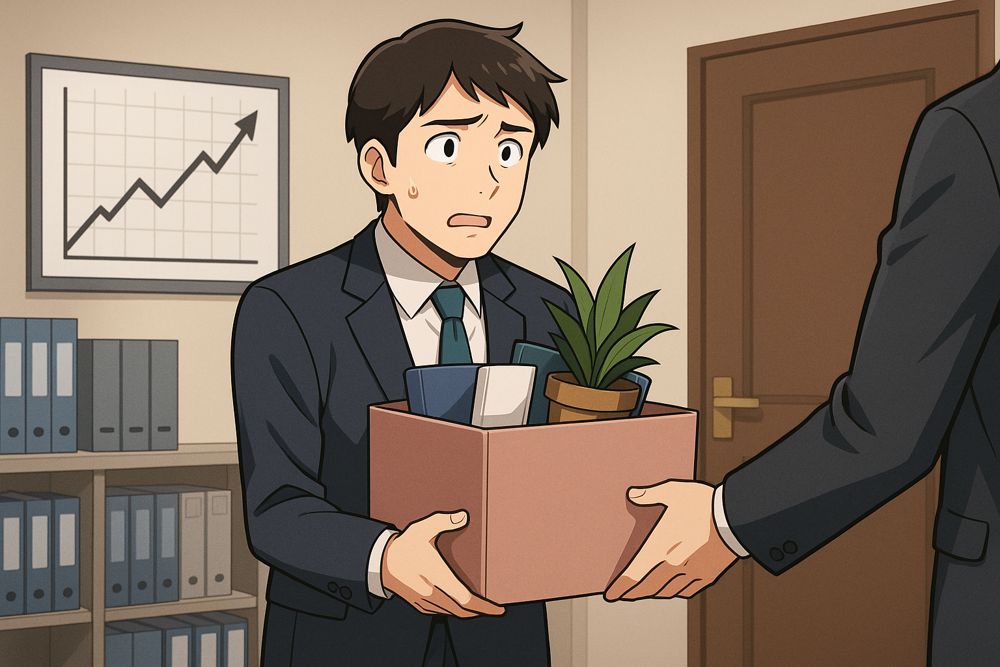
三菱電機をはじめ、業績好調な企業でなぜ人員削減が起きるのか?「黒字リストラ」が急増する背景を徹底解説。従来のリストラとの違い、企業側の真意、そして働く側が知るべき対策とは。
「儲かってるのに、なぜ?」急増する「黒字リストラ」の真実と知っておくべきこと
2025年9月、三菱電機が、過去最高益を更新する見通しにもかかわらず、53歳以上の社員を対象にした希望退職の募集を発表。長年、日本の雇用を支えてきた大手メーカーのこの決断は、「黒字リストラ」という、今、日本企業で急速に広がる現象を改めて浮き彫りにした。
かつてリストラと言えば、経営不振に陥った赤字企業が、会社の存続をかけて行う「最終手段」というイメージが強かった。しかし、なぜ今、業績が好調なはずの企業が、自ら率先して人員削減に踏み切っているのか。これは一部の特殊な事例ではなく、もはや多くの企業で起こりうる現実なのだ。この新たな時代の潮流は、私たちの働き方、そしてキャリアプランに、根本的な変化を突きつけている。
この記事では、「黒字リストラ」の真実に迫る。なぜ、儲かっている企業がリストラを行うのか。その背景にある経営者の思惑と、私たち働く側が知るべき対策を徹底的に解説していく。
黒字リストラとは何か?従来とは全く異なるその本質
まず、黒字リストラの定義を明確にしよう。それは、「業績が良好な黒字企業が、将来の企業成長のために行う戦略的な人員削減」である。
従来のリストラ、いわゆる「赤字リストラ」が、コスト削減を主目的とした「後ろ向きな延命策」であるのに対し、黒字リストラは、未来への投資という側面が強い。現在の事業が好調なうちに、新たな成長分野への経営資源の再配分や、組織の新陳代謝を促すことを目的としているのだ。
信用調査会社である東京商工リサーチの調査によると、2024年に早期・希望退職を募集した上場企業は57社に上り、そのうち実に6割が直近で黒字決算の企業であったという。また、大規模な人員削減を行った企業に目を向けると、その大半が黒字企業であったことが明らかになっている(東京商工リサーチ調べ)。
このデータが示すように、もはや黒字企業がリストラを行うことは、決して珍しいことではないのだ。これは、企業の事業環境がかつてないスピードで変化していることの証左とも言える。
なぜ今、黒字リストラが急増しているのか?経営者が明かさない本当の理由
では、なぜ企業は「儲かっている今」に、あえて社員をリストラするのだろうか。そこには、外部からは見えにくい、経営者だけが知る深い理由が複数存在する。
1. 赤字になる前に先手を打つ「健全な経営判断」
現在の利益が将来も続く保証はどこにもない。経営学の基本である「プロダクトライフサイクル理論」は、製品やサービスには必ず「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」があることを示している。
現在の黒字は、その事業が「成熟期」にあることを意味するかもしれない。だが、もしその事業が「衰退期」に入り、赤字に転落してから対策を講じていたのでは、手遅れになるリスクが高い。
例えば、製薬企業は現在、増収増益の企業が多いが、将来的な薬価引き下げによる事業環境の悪化を想定し、人員削減を含めた構造改革を急いでいるケースが見られる。これが、黒字リストラの典型的な例だ。
企業は、まだ体力がある黒字の段階で、次の成長分野に適応できる体制を整えようとしている。そのためには、新しい事業に対応できない人材や、従来の事業で余剰となった人員を削減し、新たな人材や設備に投資する必要があるのだ。これは、企業を永続的に存続させるための、合理的な経営判断なのである。
2. 年功序列から成果主義への「企業の体質改善」
日本企業の多くに根付いている年功序列型賃金体系は、長年の雇用を支えてきた一方で、企業の体質を重くしてきた側面も否定できない。バブル期に大量採用された中高年層は、勤続年数が長くなるにつれて人件費が高騰し、企業にとって大きな固定費となっている。
しかし、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAIの急速な進化により、企業が求める人材像は大きく変化した。もはや、長年の経験や知識だけでなく、新しい技術や発想力を持ち、柔軟に対応できる人材が求められている。
黒字リストラは、この古い体質を根本から見直す手段として利用される。人件費が高止まりしている中高年層を対象に早期退職を募ることで、コストを削減し、その分を若手やデジタル・グローバル人材の獲得・育成に回そうという狙いがあるのだ。年功序列から実力主義へと企業文化を移行させるための、戦略的な一歩と言えるだろう。
3. 団塊ジュニア世代の定年問題と「再就職の支援」
現在、日本の多くの企業は、人口の多い団塊ジュニア世代(1971~74年生まれ)を多く抱えている。彼らが今後、定年を迎え、さらに国が主導する「70歳定年法」によって雇用継続が求められるようになると、企業にとって人件費の負担はますます大きくなる。
企業としては、60代、70代の社員を第一線で活用し続けるのは難しいと判断する場合も少なくない。そこで、まだ再就職の可能性がある50代という早い段階で退職を促し、将来的な人件費の増大を防ごうとしているのだ。
退職金の割り増しや、再就職支援といった手厚いサポートを提供することで、従業員にとっても円満な形でセカンドキャリアへ移行できるよう配慮しているのも、黒字リストラの特徴である。これは企業側の論理ではあるが、従業員がより良い条件で再出発できるチャンスを提供しているとも考えられる。
働く側が知っておくべき「権利」と「生き抜くための方法」
このような黒字リストラの潮流は、私たち働く側にとって、他人事ではない。では、私たちはこの変化の時代をどう生き抜けばよいのだろうか。
1. 執拗な退職勧奨は「断る権利がある」と知る
リストラは、「整理解雇」「希望退職」「退職勧奨」という3つの手段で行われることが多い。このうち、大手企業が行う黒字リストラの多くは、法的なリスクが少ない「希望退職」や「退職勧奨」という形が中心となる。
退職勧奨とは、企業側が従業員に退職を促す行為のこと。これはあくまでも「お願い」であり、従業員が合意して初めて退職が成立する。企業が一方的に契約を打ち切る解雇予告とは異なり、従業員にはこれを断る権利があるのだ。もし、企業が執拗に退職を迫ったり、嫌がらせを行うなどした場合、それはパワハラなどの問題に発展する可能性もある。万が一に備え、労働組合や弁護士に相談することも視野に入れておくべきだろう。
2. 「専門能力」を磨き、替えのきかない人材になる
終身雇用が当たり前ではなくなった今、会社に依存する働き方から脱却する必要がある。リストラの対象になりにくい人材とは、年齢や役職ではなく、「この人がいないと仕事が回らない」と周囲に思わせる人材だ。
AIが定型業務を担うようになる中で、私たちは「自ら新しい知識やスキルを学ぶ」「柔軟に対応する」という姿勢を持つ必要がある。「〇〇のことなら、あの人だ」と思わせるような、専門的な能力や実績を積み重ねることが、最大の防御策となる。
3. 社内・社外の「関係性」を築くことの重要性
意外に思うかもしれないが、リストラの対象になりやすいのは、上司や同僚との関係性が希薄で、職場内で孤立している従業員である。チームでの行動が難しかったり、コミュニケーションが不足していると、組織の新陳代謝を図る際にリストラの候補に挙げられやすくなる。
日頃から積極的に周囲とコミュニケーションを取り、良好な人間関係を築くことは、働きやすさだけでなく、いざという時の助けにもなる。また、社内だけでなく、異業種交流会やSNSを通じて社外の人脈を築いておくことも重要だ。これにより、自分の市場価値を客観的に把握できるだけでなく、転職という選択肢を常に持つことができる。
まとめ:終身雇用の終わりではなく、「キャリアの始まり」へ
黒字リストラの増加は、日本の雇用システムが大きな転換期を迎えていることを示している。企業側は、市場の変化に迅速に対応できる、よりスリムで柔軟な組織を目指している。
一方で、これは私たち働く側にとっても、自分のキャリアを会社任せにせず、自律的に築いていくという意識の変革を迫るものだ。
安定した大企業に勤めているから安心、という時代はもう終わった。しかし、これは絶望を意味するわけではない。むしろ、自分のスキルや能力を武器に、会社という枠を超えて活躍できる時代が来たとも言える。
「黒字リストラ」という言葉に漠然とした不安を感じるのではなく、これを「新しい時代のキャリアの始まり」と捉え、未来に向けて主体的に行動することこそが、この変化の時代を力強く生き抜く鍵となるだろう。