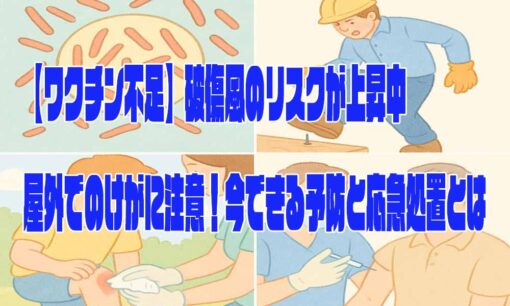カメラのフラッシュが一斉に光る中、ミニストップの堀田昌嗣社長は深々と頭を下げた。消費期限の偽装が全国25店舗に拡大し、最大14時間もの延長が確認された。客2人が体調不良を訴え、信頼は大きく揺らいでいる。本部は「食品ロス削減や効率化が背景」と説明するが、果たしてそれだけなのか。コンビニを取り巻く構造的な問題と再発防止の行方を追った。
25店舗に拡大した「消費期限偽装」の全貌
問題が最初に公表されたのは8月18日。埼玉や大阪、福岡など7都府県23店舗で、おにぎりや弁当の消費期限が偽装されていたことが明らかになった。その後、全店舗調査を経て9月1日、新たに埼玉と福岡の2店舗でも同様の不正が判明。合計25店舗に拡大した。
手口は、調理後すぐに貼るべきラベルを数時間後に貼ったり、一度陳列した商品のラベルを貼り替えるというもの。中には、14時間近く消費期限を延長した事例も確認された。
健康被害はあるのか
今回の偽装に関連して、店内調理品を食べた客2人から「腹痛」の申し出があった。ただし、不正との因果関係は確認されていない。それでも「消費期限」という生活の安心を支える基本ルールが破られたことで、消費者の不信感は強まっている。SNS上では「もう買えない」「カメラ設置だけでは不安」といった声が相次いだ。
背景に潜む食品ロス圧力とフランチャイズの矛盾
なぜ、これほど多くの店舗で同様の不正が行われたのか。
ミニストップは「店舗オーナーや従業員の判断」と説明するが、数年にわたり複数地域で同様の手口が広がっていた点を考えると、現場だけの問題とは言い難い。
背景にあるのは、コンビニ経営の厳しい現実だ。廃棄を減らさなければ利益が出にくい一方、本部からの販売ノルマやロイヤリティは変わらない。「期限切れで捨てるくらいなら」と考え、偽装に手を染める店舗が出てきても不思議ではない。
過去にも雪印牛肉偽装事件や船場吉兆の消費期限改ざんなど、食品業界を揺るがす事件があった。今回のミニストップ問題は、そうした“老舗の不正”とは異なり、フランチャイズ経営の歪みが表面化した事例とも言える。
再発防止策は実効性を持つのか
ミニストップは再発防止策として、
- 調理場への監視カメラ導入
- 専任の品質管理担当者の配置
- 内部通報窓口の新設
- 店内調理マニュアルの見直し
を発表した。しかし、カメラ設置については「店舗を信用しないことの表れ」「根本原因に向き合っていない」といった批判もある。真に必要なのは、現場が偽装に追い込まれない仕組みづくり、すなわち経営モデルそのものの改善ではないか。
信頼回復への道筋
一度失った信頼を取り戻すには、単なる制度強化だけでは不十分だ。
- 消費期限と賞味期限の違いを消費者に正しく伝える啓発
- 廃棄ロスを抑えるための値引き販売やフードバンク連携
- 本部と加盟店の負担を調整する経営改革
こうした「構造改革」と「消費者への透明性確保」があって初めて、再び安心して商品を手に取ってもらえるだろう。
事件が映し出すもの
消費期限の偽装は「小さなごまかし」ではなく、企業と消費者の信頼関係を根底から揺るがす行為だ。今回の問題は、単なる一部店舗の不正にとどまらず、食品ロス・経営ノルマ・フランチャイズ制度といった大きな矛盾を映し出している。ミニストップが本当に変わることができるのか。それは、今後の行動がすべてを物語るだろう。