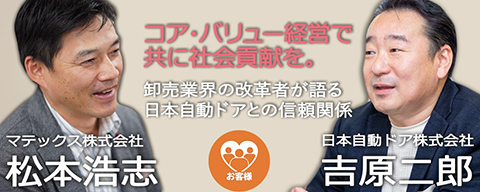セルフレジの普及に伴い、万引きの手口にも変化が生じている。
店舗スタッフの目が届きにくい無人レジの仕組みを悪用し、商品をスキャンせずに袋へ入れる、別の商品コードで登録するといった「見えにくい万引き」が増えているのだ。
警視庁のまとめによると、2023年、都内で確認されたセルフレジ関連の窃盗事案は前年に比べ約25%増加。小売店各社も、「スキャン漏れ」を含む商品ロスの増加を報告しており、深刻な損失につながっている。
スキャン漏れの判断は難しく、摘発も困難
都内のある大手ドラッグストアでは、セルフレジ導入以降、店舗あたりのロス率が1.3〜1.5倍に増加したという。
同社の広報担当者はこう話す。
「故意かどうかの見極めが非常に難しいのが現状です。商品がレジを通されていなくても、お客様が『操作ミスでした』と説明すれば、それ以上の対応は困難です。注意喚起はしていますが、明確な証拠がない場合は慎重にならざるを得ません」
特に問題となっているのが、操作ミスと万引きの境界が曖昧である点だ。中にはスキャンせずに袋へ入れた商品を、客が店外で気づいて戻ってくるケースもあるが、繰り返されると「常習性があるのではないか」と疑念が生じるという。
高齢者と若年層で異なる傾向も
スキャン漏れの傾向には、年齢層による違いもある。
高齢者に多いのは、セルフレジの操作に不慣れなことによる無意識のミスだ。
「読み取ったと思っていたが、実際には反応していなかった」など、本人が気づかないまま会計を終えてしまう事例も報告されている。店舗側では、こうした客には付き添いながら案内を行うが、混雑時には対応が追いつかないこともある。
一方で、若年層には意図的な誤操作の事例が目立つ。
安価な商品のバーコードを使用して高額商品を登録する、2人組で注意をそらしながらスキャンせずに商品を袋へ入れる、といった「確信犯的」な手口も確認されている。
対策進むも、技術的・人的限界も
こうした事態を受け、大手チェーンではAIカメラや重量センサーを用いた対策が進んでいる。
たとえば、スキャン時の動作をAIが分析し、不審な動きを検知するとアラートを出すシステムが導入されつつある。また、レジ台の重量センサーと連動し、スキャンした商品の重さと実際の袋詰め商品の重量に差がある場合、確認画面が表示される仕組みもある。
しかし、こうしたシステムの導入にはコストがかかるため、すべての店舗で一律に実施できるわけではない。とくに中小規模の店舗では、人的リソースに頼らざるを得ないのが実情だ。
あるスーパーの店長は、「セルフレジの横に立つスタッフの存在そのものが、最大の防犯になる」と語る。現場では、無人に見えても見られているという意識を客に持たせることが、今なお有効な抑止力となっている。
セルフレジ普及と信頼のバランス
セルフレジは、顧客の利便性を高め、レジ待ちのストレスを軽減する手段として定着した。一方で、その仕組みは「利用者の良識と信頼」に支えられている。
だが、その信頼が破られる事態が続けば、セルフレジ自体の維持も困難になる。実際、一部の店舗ではセルフレジの運用を縮小し、有人対応へ戻す動きも見られる。
誰にも見られていないとき、自分がどう行動するか。
セルフレジの問題は、便利さとモラルの関係、そして「無人社会」における人間性を問い直すきっかけとなっている。