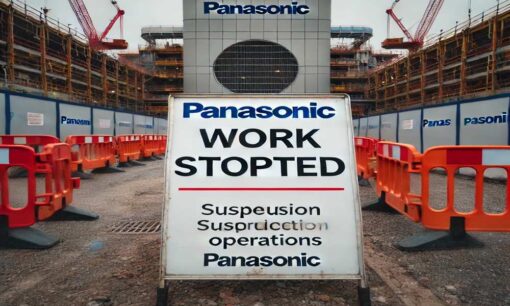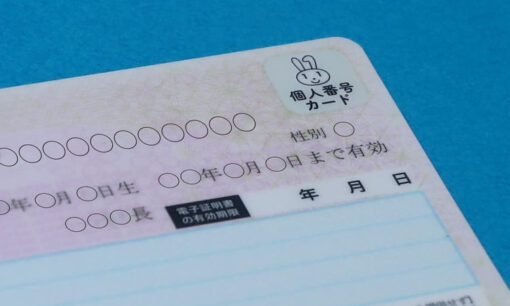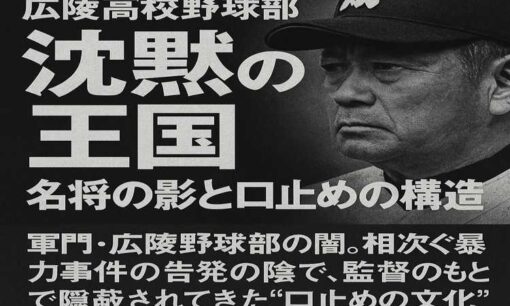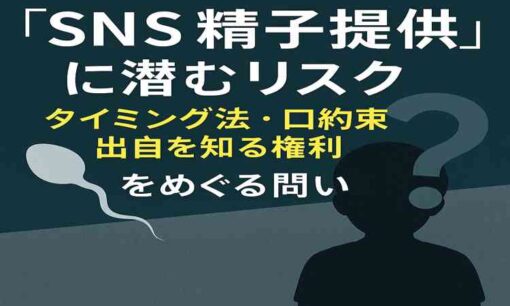七夕の夜空に、天の川が見えない。そんな現実に慣れてしまった私たちは、何を見落としているのか。星の見えない社会が抱える“静かな不平等”と、未来への問いを掘り下げる。
天の川が見えない七夕。理由は「季節」と「暮らし」
東京を含む多くの都市では、7月7日に天の川が見えることはほとんどない。
最大の理由は、七夕がちょうど梅雨のまっただなかにあること。
気象庁のデータによれば、首都圏の過去30年で「七夕の夜に晴れた」のは30%以下。空を見上げれば雨雲、という年が多い。
そこにもう一つ、「光害(こうがい)」という静かな原因がある。
街の灯り、ビルの照明、24時間営業のコンビニの看板…こうした都市の“当たり前”が夜空を明るく染め上げ、かすかな星の光をかき消してしまう。
天の川は、都市生活者にとって「想像の中にしか存在しない風景」となりつつある。
“かつて見えた星”という記憶の資源
昭和30年代、東京23区でも天の川が見えたという記録がある。
古い天文台の観測ノートや、当時の新聞記事には「目が慣れれば白く流れる帯が見える」といった記述が残る。
つまり、星が見えないというのは自然の変化ではなく、社会構造の変化である。
この「かつて見えた風景」を、単なる郷愁で終わらせるのか。
それとも、失われたがゆえに価値を持つ記憶の資源として再評価するのか。
天の川は、見えないまま、私たちの選択を問うている。
光害は“空の格差”を生み出している
光害にはもうひとつ、見過ごされがちな側面がある。
それは、「空の格差」を生むということだ。
たとえば、同じ国に住んでいても、星空が見える地域と見えない地域がある。
夜の暗さを守るために努力している地域(例:長野県阿智村・石垣市)と、絶え間なく光を放ち続ける都市。
天の川を体験できるかどうかは、場所や経済状況によって左右される。
これはある意味で、「見えない不平等」とも呼べるのではないだろうか。
光があふれる社会は、同時に“暗さを持てない社会”でもある。
そしてその暗さこそ、星を見るという行為にとって不可欠な要素なのだ。
「旧暦の七夕」星が本当に見える季節とは?
本来の七夕は、旧暦の7月7日。現代の暦ではおおよそ8月中旬の新月前後にあたる。
この時期になれば、日本列島の多くの地域で梅雨は明け、空気も澄みわたる。
天の川を観察するには絶好のタイミングだ。
都市生活では「夏の終わり」だと認識される8月の夜。
そこに、かつての人々が星に願いをかけた原風景が息づいている。
旧暦を忘れた現代人にとって、七夕とは「季節感のずれ」を静かに突きつける行事とも言える。
見えないからこそ、願うという文化
面白いのは、天の川が見えなくても七夕の文化は続いているということだ。
子どもたちは短冊を書き、大人も願いをこめる。
見えない空に向かって、見えない星へ願いを託す。
その姿勢には、「見えないものに価値を与える力」が宿っている。
星が見えない夜にこそ、自分の内側にある「本当に見たいもの」が浮かび上がる。
それは、都市に暮らす私たちにとっての“想像力の試金石”でもある。