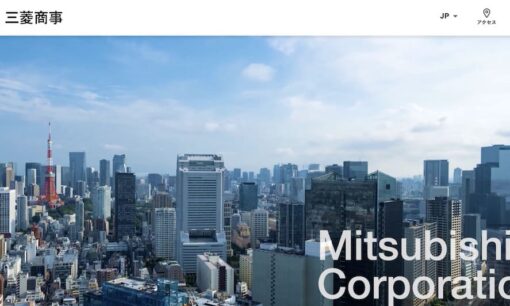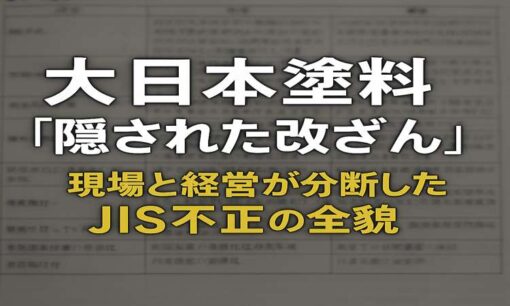公安部の違法捜査を高裁が明確に断罪

神奈川県横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐる冤罪事件で、東京高等裁判所は5月28日、警視庁公安部と東京地検による違法な捜査・起訴を認定し、東京都および国に対し計約1億6600万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。2022年の一審・東京地裁判決(約1億6000万円)に続く判断であり、賠償額は増額された。
判決では、「公安部の捜査には犯罪の嫌疑の成立に関して根本的な問題があった」とし、東京地検についても「起訴するための合理的な根拠を欠いていた」と厳しく批判した。
証拠となった“捜査メモ”と内部証言
本件は、同社が開発・販売していた噴霧乾燥機が「軍事転用可能」とされ、中国などへの不正輸出の疑いで、2020年に社長ら3人が逮捕・起訴されたことに端を発する。しかし、初公判を4日後に控えた2021年7月、東京地検は突然、起訴を取り消し、無実が確定。大川原氏らは冤罪被害者となった。
控訴審では、原告側が新たに提出した警視庁公安部の捜査メモに加え、証人として出廷した現役警察官が「立件の必要はなかった」「決定権を持っている人の“欲”が動機だった」と証言。組織の内部から、捜査そのものが不適切であったことを裏付ける証言が飛び出した。
“外事”評価の象徴から冤罪事件へ
大川原化工機事件は、当初、警察組織内部では高く評価されていた。公安部外事1課は「警視総監賞」や「警察庁長官賞」を受賞し、警察白書では経済安全保障に資する捜査事例として紹介された。
だが、冤罪が確定し、証言で「捏造」が語られた2023年には、警察白書から事件の記述が削除され、賞は返納された。評価は一転し、「組織ぐるみの誤り」として扱われるに至った。
問われぬ“個人責任”と税金による賠償の矛盾
今回の判決によって、都と国には多額の賠償責任が生じるが、その原資は国民の税金である。一方で、違法捜査に関与した個々の警察官・検察官は、法的にも財政的にも一切の責任を問われていない。
SNS上では、「なぜ個人の欲で起きた事件に税金が使われるのか」「責任は組織ではなく個人に問うべきだ」といった怒りの声が相次いでいる。「これでは公務員は何をしても責任を問われないのではないか」という根本的な疑念が噴出している。
公務員個人に責任を問う制度は可能か?
現行の国家賠償制度は、公務員個人ではなく国や地方公共団体にのみ賠償責任を課す設計となっている。この仕組みは、一定の合理性を持つ一方で、明らかに職務の範囲を逸脱した行為や、重大な過失が認定された場合でも、「個人責任」が問われない構造となっている。
これに対し、一部の法学者や政策提案者からは、**「限定的な公務員個人賠償責任制度」**の導入を求める声が上がっている。
たとえば以下のような制度設計が考えられている:
- 捜査や行政処分で故意または重大な過失が認定された場合に限り、当該公務員に対して国や自治体が求償権を行使できる。
- 国家賠償の請求とは別に、懲戒処分の重さに応じて賠償金の一部を個人が分担する。
- 被害者が公的機関と並行して個人にも訴訟を提起できるよう、手続を整備する。
このような制度は、欧州の一部の国や国際機関で既に運用されており、「職務上の行為であっても法を逸脱した場合は責任を負う」という考え方に立脚している。
冤罪がもたらす深い傷と制度設計の再考
大川原化工機の大川原正明社長は、判決後、「違法性が再び認められた。警察と検察には、このようなことが二度と起きないよう検証していただきたい」と語った。
しかし、現時点で警視庁からの正式な謝罪も、捜査過程の検証報告も出されていない。制度上の限界と組織的無責任が並存するこの構図は、冤罪を“例外的失敗”ではなく“構造的リスク”へと変質させている。
東京高裁の判決は、冤罪という司法の暗部を明らかにすると同時に、国家賠償制度の抜本的見直しを突きつけるものでもある。責任の所在をあいまいにしたまま、私たちの税金だけが支払い続ける構造に、そろそろ終止符を打つべき時が来ているのかもしれない。