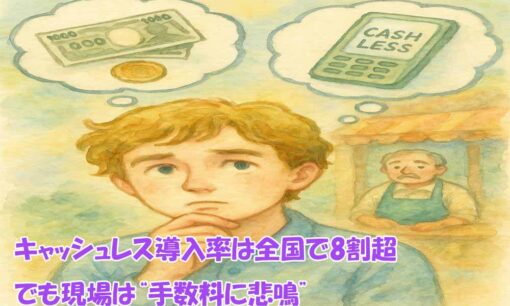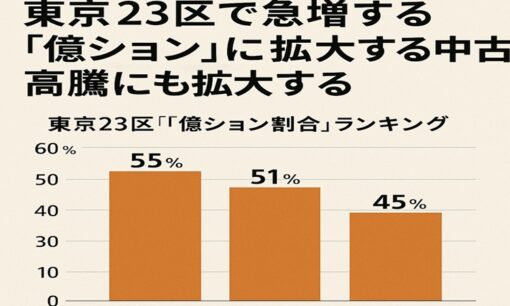大中忠夫(おおなか・ただお)
株式会社グローバル・マネジメント・ネットワークス代表取締役 (2004~)、CoachSource LLP Executive Coach (2004~) 三菱商事株式会社 (1975-91)、GE メディカルシステムズ (1991-94)、PwCコンサルタントLLPディレクター (1994-2001)、ヒューイットアソシエイツLLP日本法人代表取締役 (2001-03)、名古屋商科大学大学院教授 (2009-21)
主な著書:「日本株式会社 新生記 第1~13巻」2025.5.15. 改訂新版
「日本株式会社 人的資本総覧」2025.2.11
「持続進化経営力構築法」2023.4.7
「創造力プログラミング」(共著) 電子書籍 2022.9.17 改訂新版
「持続的進化を実現する企業経営戦略体系」電子書籍 2014.10.23
「持続的な進化を実践するマネジメント技術体系(上・中・下) 」電子書籍2014.8.8
筆者が今月上梓しました改訂新版「日本株式会社 新生記」 第1~13巻の第1巻のご紹介です。
いま企業社会に持続進化経営力が必要な三つの理由
(「日本株式会社 新生記」2025.5.15 改訂新版 「序章」抜粋)
三つの理由には、まず常識的な第一の理由と、つぎに経済的な第二の理由、そして社会的な第三の理由があります。
1.常識的な第一の理由:現代社会最大の資本家は年金生活者
今を遡ること30年以上前の1993年に、ドラッカーも著書「ポスト資本主義社会」ですでに指摘している事実ですが、現代社会最大の資本家は「年金生活者」です。そして彼らから委託を受けているすべての年金基金も、その最終必達使命は年金の未来長期保証です。現代社会最大の投資家である年金基金の世界最大のスポンサー、資本家、である年金生活者は、未来を犠牲にした短期業績最大化など望んではいません。
すなわち、年金基金が自己の株式市場での運用評価を維持するために、株主第一主義経営の名目のもとで、投資対象である企業群の未来に向けての持続可能性を犠牲にしてまで、ひたすら短期投資回収の最大化をめざしていることは、白昼の下に照らされた深刻な矛盾、大きな間違いなのです。その事実に対して、世界最大の投資機関ブラックロックのラリー・フィンクCEOも、2024年書簡で「退職 (年金)危機」を大々的に警告しています。いまやこの矛盾を見極めて、最終株主/資本家の本来究極の要望を実現する企業経営が真剣に求められているのです。
にもかかわらず、現実はそうではありません。先日2025年末の引退を表明したW.バフェット氏を投資の神様と讃えながらも、大部分の機関/個人投資家は彼とは逆の投資行動、目先の企業業績の浮沈に日々敏感に対応する盛んな取引を繰り返しています。株式市場もそのプロデューサー、証券業界、も金融経済を構成する重要な存在です。彼らにとって、投資家全員がW. バフェット氏のような長期投資家となってしまっては、商売あがったり、産業自体が成り立ちませんから、そのビジネス行動は尊重されるべきでしょう。
しかしながら、一方で、企業経営者までが、自社の持続可能性を犠牲にする必要はまったくありません。なぜか?
(1)まずそもそも、最終、最大の資本家の期待に応えることができていないことで、実質的には空言でしかない株主第一主義。この名目のもとでの短期業績の最大化は、実は、短期投資リターンと手数料の最大化を追求する、機関投資家の事情・都合によるものでしかないという事実です。これに企業経営者が加担しなければならない理由は見当たりません。(注)
注:しいていえば米国企業社会では、企業経営者が投資家集団の最重要都合に従うように、過去半世紀以上にわたり株価連動報酬制度が導入されています。しかしすこし冷静に考えればこれほど企業経営者の社会リーダーとしての自立尊厳を否定する制度もないでしょう。こう申し上げると、日本社会でも20世紀末の外資導入自由化に端を発する株主第一主義ブームで同制度を導入してしまった企業経営者の方々は不愉快な思いをされるかもしれません。しかし短期業績追求が一般機関投資家の都合でしかないという事実は、社会的にはすでに自明になりつつあります。失敗も進化の重要な糧です。誤りは気づいた時点で速やかに是正することで新たな進化の道が開けます。今でしょう!
(2)したがって、二つ目のそもそもは、短期業績最大化という企業の持続可能性を最も損なう経営方針は、最終的な資本家、年金生活者、の最重要な期待に反しているのですから、むしろ最終資本家に対する企業経営者としてのコンプライアンス違反、あるいは本来ミッションの放棄、ともいえます。企業経営者が短期業績最大化志向を捨て去るべきことは、いわずもがなです。短期業績経営の対極である持続進化経営に専念、専心することこそが現代企業経営者の必須命題なのです。
(3)さらに三つ目のそもそもの理由があります。投資家と企業のパワーバランス逆転。海に沈んだ塩臼の昔話のように大量に産出され続けられる米ドル。さらに最近はこれに仮想通貨までが加わり、投資資金の方は過剰に増殖しつつあります。しかしその反面、短期業績最大化ブームで先細りし続ける企業社会、投資対象、は減少し続けています。
この需給関係の一方的な相反の現実を直視すれば企業経営者が短期業績追求という機関投資家の都合に合わせる必要がなくなりつつあることは、自明の上に自明です。この現代社会の投資需給パワーバランスの逆転は、むしろ企業経営者が投資家を選べる時代が始まっていることも示しているからです。いまや企業経営者の重要な役割責任は、いかに多くの投資家の評価を高めるかではなく、自社の持続可能性を支援する投資家を正確に選別すること。そのように断言できる時代が始まっているのです。
2.経済的な第二の理由:企業社会は最重要な経済基盤
この二つ目の理由の深刻さを、最近のトランプ米国大統領の一連の行動がものがたっています。
2019年にJ.ダイモン米国ビジネスラウンドテーブル議長が、『脱』株主第一主義経営(‘Scrapping Stockholder Primacy’)を宣言しています。またダボス会議の別名で知られている世界経済フォーラム(World Economic Forum)もその翌年2020年に、株主や資本家(Stockholder) のみに偏重した経営から、会社の利害関係者全員(Stakeholder)に貢献する経営への転換を促す「ステークホルダー資本主義」を提起しています。
これらの世界的に認知された経営トップリーダー集団が、米国では少なくとも半世紀以上、日本では20年以上、企業経営の分野で支配的であった、株主第一主義に警鐘を鳴らしているのです。これらの事実も、株主第一主義経営による米国経済、ひいては、世界経済に対する弊害が見過ごせない深刻レベルになっていることを示しています。
その深刻な弊害とは何か?トランプ氏も公言するに至った米国製造業のもはや到底見過ごせないレベルの衰退の現実です。そして、それは決して製造業界だけの話にとどまりません。表舞台では華々しく輝いている金融経済ですが、そのよって立つ基盤は製造業を中核とする実体経済です。その実体経済が、一般には気づかれないままに深刻な空洞化と一方的な衰退を続けているのです。企業社会は自らが国家経済の基盤である事実を直視する必要があります。ものつくり産業が実体経済の中核であるのみならず、それを基盤とする金融経済の命運をも握っているからです。
3.社会的な第三の理由:経済は平和共存の基盤
1972年の日中国交正常化交渉開始と78年の日中友好条約調印。これらは田中角栄首相の決断と福田赳夫首相の交渉力の賜物ですが、それがこの間6年間にもおよぶ両国政治事情の紆余曲折にもかかわらず調印実現に至った切り札は、1977年から開始された日本製鐵による宝山製鉄所に対する大々的な育成支援投資でした。
2025年現在、日本製鐵のUSS 支援、トヨタ自動車の米国投資強化表明、ソフトバンクの米国AI産業投資、などが提起されています。これらが今後の日米関係の進化をもたらす起点となるでしょう。一般に、政治、経済と並列表現されていますが、21世紀現在では、経済が国際政治外交関係の必須の成否基盤となっているのです。
そしてそのことはすでに70年以上前に池田勇人首相によって提起されています。
一、日本経済運営の目標
われわれは、心から世界平和の維持を念願する。だから、日本経済の運営にあたってもまた、この念願を実現するために、必要な経済条件を造り出すことが根本の目標とならなければならない。では、どういう経済条件が世界平和の維持のために必要だろうか。
第一には、国民の生活水準の向上をはかること。第二には、失業者を減らして完全雇用を維持すること。第三には社会福祉の増進をはかること。第四には、これらのことを、わが国だけで実現するのではなく、他国と互いに協力しつつ実現して、世界人類全体の安定と福祉を増進してゆくこと。大体この四つである。
これらは、いずれも互いに関連し合っているものであるが、せんじつめれば、それは日本経済の発展というか、高度化というか、そういう姿において、実現されるものであるといえよう。その裏付けとなるものは、結局、経済基盤の充実、強化ということでなければならない。
「均衡財政」池田勇人 1952 実業之日本社刊
ロシアによるウクライナ侵攻に端を発して、ガザ地区からのイスラエル襲撃とイスラエルによる徹底弾圧抗戦、イラン・イスラエル対立、ペルシャ湾航行船舶襲撃、東・南シナ海領土紛争、インド・パキスタン紛争、と21世紀の現代でもいまだに、他国侵攻により国民の不満を他方向に逸らせる、あるいは解消する手段として軍事侵攻が繰り返されています。
人間が働く意思を有しながら、働くべき職がないということは、誠に耐え難いことであり、不幸なことである。失業が社会的な疾病ともいうべき慢性的な状態になると、偏った思想が生まれ、戦争が誘発される。第二次世界大戦が、遠く一九三○年前後の世界的不況に起因するという見方は、決して間違っていない。(「均衡財政」完全雇用の実現 池田勇人1952)
現在でも依然として繰り返されているこのような国家紛争の原因は何か?それは結局、国民の自国経済に対する不満の鬱積であり、それを発散して現行政治体制を防御しようとする政府の意図に他なりません。そして、さらにそれらを突き詰めれば、結局、人類社会一般の「経済進化手法に対する無知」に起因しているといって過言ではありません。
自国経済と国民が十分とはいえなくても何とか満足できる状態であれば、あるいは少なくとも、政府や社会に経済成長を実現する確信があれば、自ら現状を破壊・放棄する対外侵略や紛争などは当然避けるからです。経済学的な多種多様な議論は溢れかえっても、肝心の国家経済そのものをどうすれば成長させられるかについては、ほとんどの社会に確信できる実行策が確立できていないのです。それはなぜか?どうすればよいのか?
これについても、池田勇人首相からの伝言があります。
最後に日本経済はどうなるかについてのべよう。もちろん、私はここで日本経済の運命について予言をしようとしているのではない。日本経済は、われわれ自身の願いと努力との結晶に外ならない。
私が論じようとする日本経済の進路も、このような意味における進路である。それは、単に運命によって外から日本経済にあたえられるものではなくて、われわれ自身によって切り開かるべき進路である。
「均衡財政」日本経済はどうなるか 池田勇人 1952
日本株式会社 新生記 第1巻
まえがきと目次 紹介
まえがき
本書は上場日本企業2639社の2014-23年の進化成長のデータブックです。単年度の企業業績や株価変動といったいわば表面的な情報からは判定できない日本株式会社の持続進化経営力という「底力(そこじから)」の数値計測結果です。これらのデータは、この日本企業群の経営力が、過去半世紀以上にわたる株主第一主義経営により未来を犠牲にした短期業績最大化経営に疲労困憊した欧米企業には存在しない、現代先進社会唯一の存在でもあることも示しています。
ではどのようにしてその日本企業の持続進化経営力を計測したか?それは企業経営評価の基本常識に立ち戻った計測指標によるものです。会計学で一般に「付加価値」と呼称されている企業の創出した正味の経済価値合計。本書ではこの計測指標を「企業総生産(Gross Corporate Product)」と名称し、このGCPの10年間の推移を計測しています。
このGCP(企業総生産)は、当期純利益のみではなく、これにさらに総人件費と法人税を加えた合計値です。これは企業が外部から購入した全ての価値コストを売上高から差し引いた、その企業自身による正味の創出価値です。利益という投資家に対する価値以外に、社員と社会に対する価値を合計した、社会的存在としての企業の正味創出価値の総合計です。そしてこれは有価証券報告書情報から計測できます。
このGCP(企業総生産)で上場2639社を計測すると、実にほぼ8割の2038社が2014-23の直近10年間にその数値を伸長している事実が浮かび上がります。これが現代日本企業の持続進化経営力を示す最も顕著な情報の一つです。日本株式会社は、持続的な進化成長を実現しているのです。本書ではさらにこのGCPに関連する9項目を含めた全10項目で日本企業の純然たる持続進化経営力を証明しています。
ではなぜ日本株式会社に持続的な進化成長が実現しているのか?この原因についても、第9章で過去半世紀の歴史的事実に基づいて多面的に推定しています。そしてこの事実分析に基づいて、第10章では日本企業社会の未来進路についても提言しています。
令和7年5月6日
大中忠夫
目次
第1部 持続進化経営 基盤力測定
序 章 いま持続進化経営力が必要な三つの理由
企業社会は人間社会経済の持続進化の基盤
第1章 企業総生産 (GCP)
1868社(71%)が持続的に増大
第2章 企業総投資 (GCI)
1919社(73%)が持続的に増大
第3章 持続進化経営・基盤力-GCP/GCI・4領域分類
1645社(62%)が持続進化経営・基盤力を実現
第4章 持続進化指数(CSI)
1390社(53%)がプラス成長
第5章 純資産
1960年から2023年で150倍超に成長
第2部 持続進化経営 総合力測定
第6章 持続進化経営・総合力
2038社(77%) が持続進化経営・総合力を実践
第7章 雇用重視経営
1960-2023で社員数3.3倍、企業数6倍成長
第8章 脱株主第一主義経営
株主資本利益率(ROE)を一定維持し純資産を最大化
第3部 日本株式会社 新生記
第9章 日本企業社会の持続進化力5つの源泉
世界平和に貢献する経済成長の基本方針
序 日本経済4段階成長の系譜:1960-現代
1.高度経済成長政策―なぜ経済政策が社会を動かせたのか?
2.柔軟・健全な対外協調―日米経済金融均衡40年史
3.ゼロ金利政策―インフレ期待の徹底的な抑制・排除
4.軍事力・軍需による経済政策の放棄・禁止
5.ものつくり社会文化と資本蓄積の奨励
第10章 日本経済の未来進路
池田勇人首相からの未来社会への伝言
基本方針:世界の平和・協調のための経済成長
行動提案1.現状認識:日本株式会社サステナビリティ強靱性検証
行動提案2.挑戦行動:実質GDP大国としての日本の素顔と挑戦課題
行動提案3.防御行動:「同意なき買収」に対する三段階防波堤構築
行動提案4.貢献行動:米国経済再生のもう一つの進路について
行動提案5.創造行動:なぜ創造力を活かさないのか?
大中忠夫
株式会社グローバル・マネジメント・ネットワークス代表取締役 (2004~) CoachSource LLP Executive Coach (2004~)三菱商事株式会社 (1975-91)、GE メディカルシステムズ (1991-94)、プライスウォーターハウスクーパースコンサルタントLLPディレクター (1994-2001)、ヒューイットアソシエイツLLP日本法人代表取締役 (2001-03)、名古屋商科大学大学院教授 (2009-21) 最新著書:「日本株式会社 新生記」全13巻