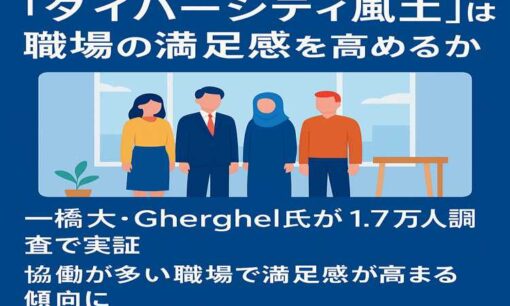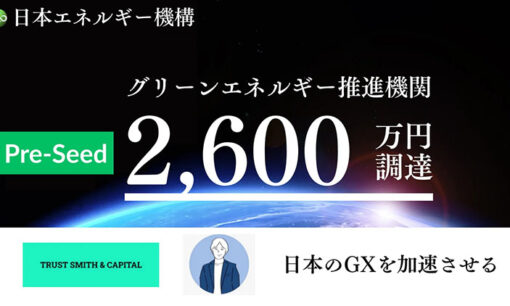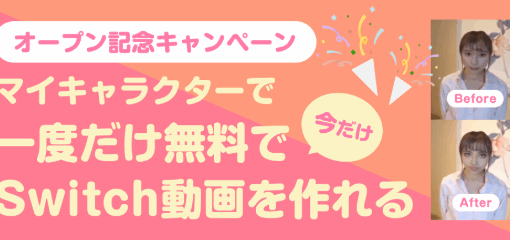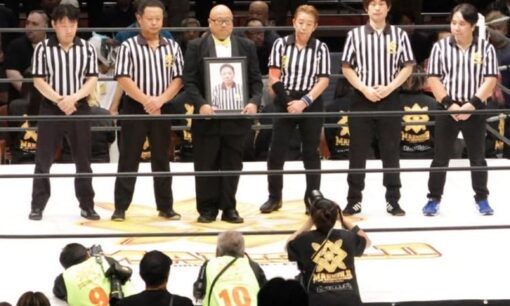岡山の山間に潜んでいた、30年企業の“綻び”

岡山県加賀郡吉備中央町――静かな工業団地に佇む塗料メーカー「岡山化工株式会社」は、大日本塗料株式会社(以下、DNT)の連結子会社として知られてきた。JIS(日本産業規格)に基づく塗料を製造し、多数の国内外メーカーに供給していたこの企業で、長年にわたる不適切行為が発覚した。
きっかけは2022年の社内コンプライアンスアンケートだった。匿名で寄せられた回答が、JIS規格を逸脱する製品出荷の疑いを指摘していた。DNTは事態を重く見て、2023年10月に外部弁護士らで構成する特別調査委員会を設置。委員会は88人へのヒアリングと約380万件におよぶファイルのフォレンジック分析を経て、2025年4月まで40回の会合を重ねた末、報告書をまとめた。
JIS規格「適用外」のトリック
調査で明らかになったのは、社内検査で基準を外れた結果を「規格内」に改ざんして出荷する行為だった。検査データの数値を手作業で“修正”し、書類上は問題ない製品としてJISマークを付けていた。検査項目のうち「加熱残分(NV)」を「優先」とする運用が悪用され、他の項目(粘度や比重)の不適合を覆い隠していた。
岡山化工の検査体制も甘かった。工程検査を行う作業者が製造工程の一部を兼任しており、チェック体制は機能していなかった。報告書では「牽制機能の欠如」「業務のたこつぼ化」「相談しにくい職場風土」が背景にあったと指摘している。
DNT本体の関与と経営陣の責任
報告書はDNT本体の管理不備にも踏み込んでいる。工程検査規格と日塗検への申請内容に齟齬があったほか、経営層による現場の実態把握も不十分だった。社長以下6名の役員に対し、自主的な報酬返納処分が発表されたが、これを「責任の明確化」として受け止めるには世論の視線は厳しい。
「不正の文化」はなぜ止まらなかったのか
調査の中で語られたのは、業績優先の空気と「納期至上主義」の現場事情だった。上司からの黙認、過去の前例踏襲、改善を拒む“近道行動”――これらが重なり、岡山化工は静かにJIS基準を裏切り続けた。
報告書では「企業風土の改革」「品質保証部門の強化」「現場との対話再構築」など15項目におよぶ再発防止策が提示された。LIMS(品質管理システム)の導入や工程検査の自動化も進められているというが、肝心なのは“風化させない”意識だ。
信頼回復に必要なもの
岡山化工の社長は「グループ一丸で再発防止に努める」と述べたが、関係者の間では「なぜもっと早く手を打てなかったのか」という声も根強い。とりわけJISマークの信頼に関わる問題は、業界全体に波紋を広げている。
本件に関しDNTは専用窓口を設置し、取引先や消費者への説明に追われている。事態をどこまで深刻に受け止め、文化をどう変えていくのか。その答えが企業の真価を問われる時代となった。
岡山化工での長年にわたる不適切行為は、企業としての透明性と説明責任の重要性を改めて浮き彫りにした。JIS認証という社会的インフラの信頼を損なう行為に対し、大日本塗料は真摯に向き合い、40回以上にわたる外部調査を経て、詳細な再発防止策をまとめた。
報告書には、品質管理部門の生産部門からの分離、LIMS導入による検査の自動化、経営層と現場の対話強化など、構造的な改善に向けた多くの改革案が記されている。こうした施策を形骸化させず、実効性あるガバナンスへと転換できるかどうかが、今後の企業価値を左右する。
本件を単なる「不祥事」で終わらせるのではなく、組織文化と風土を根本から見直す契機とし、透明で誠実な企業運営を目指す。その姿勢を継続的に示すことこそが、失われた信頼を取り戻す唯一の道だ。


新聞社・雑誌の記者および編集者を経て現在は現在はフリーライターとして、多方面で活動を展開。 新聞社で培った経験をもとに、時事的な記事執筆を得意とし、多様なテーマを深く掘り下げることを得意とする。