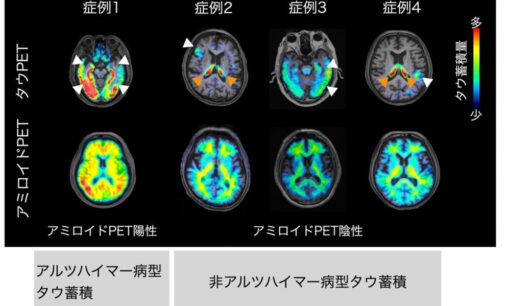ブームでも生産が減っている日本酒

酒は人類の友、という格言?がありますが、今日本酒がブームになっています。
日本酒の銘柄を豊富に備えた飲食店がメディアでピックアップされ、若い世代にも人気を集めています。また海外でも日本食ブームと相まって注目され、輸出量は年々増加、令和4(2022)年には過去最高の475億円の輸出金額になっています(農林水産省調べ)。
しかしこの日本酒ブームについて、実際に日本酒を製造している酒蔵側の視点からみてみるとどうなのでしょうか?
日本酒生産量のデータをみると、酒蔵側はこのブームに呼応できていないことが分かります。
平成10(1998)年には113万キロリットルほどだった日本酒の出荷量は令和元(2019)年には46万7千キロリットルにまで減少し、令和5(2023)年にはついに40万を割り39万キロリットルとなっています(同調べ)。
僅か25年で生産数が3分の1ほどになったこの急激な減少の原因は、以前は生産量の8割を占めていた一般酒の大幅な生産減があります。一般酒とは、いわゆる町中の酒店で手に入り、自宅で呑まれることが主の酒です。イメージ的には『ちびまる子ちゃん』で父ひろしが晩酌で呑んでいるモノを想像すると分かりやすいでしょう。安価で日常的に消費されていたこの一般酒の出荷量が、平成10年の84万キロリットルから、令和5年には24万5千キロリットルにまで落ちた。家庭でお父さんが日本酒を呑まなくなったのです。
一般酒に対して、特定名称酒と呼ばれる飲食店で供される酒に関しても同じく平成10年に比べて生産量は半減しています。ブームと呼ばれ需要が高まっている世相に対し、生産量でみると日本酒業界は右肩下がりが続いているのです。
なぜ日本酒を増産しないのか
ではなぜ需要にこたえて日本酒を増産しないのでしょうか?
第一に現在は酒類製造免許(酒造免許)の取得が極めて困難なことがあります。ブームに着目した事業者が、これから日本酒の生産に新規参入しようとしても、既存酒蔵の保護という観点から酒造免許が新規発行されることがほぼなく、非常に閉鎖的です。既存の酒蔵は明治時代から昭和初期にこの免許を取得しているところがほとんどで、その数は約2300ほどあります(国税庁HPより)。
ですがこの中で実際に酒を製造している酒蔵は半数以下と考えられています。ほとんどの酒蔵が免許は持っているものの、先に述べた一般酒消費の減少にともない製造を止めているのです。
例を挙げると竹下登元首相の実家として有名な島根県の酒蔵竹下本店は、慶応2(1866)年創業の老舗ですが、平成15(2003)年に一度、製造を止めていました。その後島根県を中心に事業展開を行う田部グループに事業承継され、田部竹下酒造として再スタート、再び製造を始めています。
この酒造免許を持っていながら生産を止めている酒蔵を事業承継し、新たに製造を始めることは現在のトレンドになっています。特に日本酒人気の高い中国資本が参入してきており、蔵を丸抱えして製造した日本酒をそのまま中国へ輸出しているところもあるのです。
第二の理由が酒蔵の閉鎖性です。酒蔵のほとんどが社員数10人以下の零細企業です。これらの零細酒蔵では大都市の飲食店に卸されるような人気銘柄を持っていないことも多く、製品はほぼ地元だけで消費されています。彼らは作った分が売れて、従業員が食べていけるだけの利益が得られればそれで充分と思っている。事業を拡大して売上を伸ばそうとする成長志向があまりないのです。
また酒蔵業界には焼酎ブームとその終焉に対する恐怖があります。2000年代に芋焼酎のブームが巻き起こり、平成15(2003)年には焼酎の出荷量が53年ぶりに日本酒を上回ったことがありました。この時九州の焼酎メーカーは工場を増設、拡大生産に躍起になったのですが、その後ブームは収束。
出荷量の前年割れが続き、多くのメーカーはその設備投資分の回収ができずに廃業、もしくは今も苦しんでいます。この焼酎メーカーの状況をみているので、日本酒の酒蔵は生産量を増やすことに二の足を踏んでいるのです。
第三の理由が日本酒のデリケートさです。日本酒はその生産方法から「醸造酒」に分類されますが、日本酒やワインなどの醸造酒はウィスキーや焼酎などの「蒸留酒」と比べて温度変化に非常に敏感です。
日光に僅かに当たるだけでも味が変わってしまうほどです。低温暗所で貯蔵するワインの保存方法を想像していただけると分かりやすいと思いますが、日本酒がワインと大きく異なるのは、ワインと比べて長期保存ができないことです。ワインは時間をおいて熟成させて味わいを深くする楽しみがありますが、日本酒、特に生酒は製造後できるだけ短期間で消費しないと味が落ちてしまいます(熟成させたほうが美味しくなるタイプの日本酒も存在します)。
また製造方法もデリケートです。人気の高い特定名称酒の中でも「純米酒」や「吟醸酒」は米と水、そして麹の三つの原材料のみを使用して作られます(それ以外に醸造アルコールを添加しているものは「本醸造」として区別されます)。
この三つがいくつかの過程を経ていくことで日本酒になるのですが、その過程の手順や時間、気温、菌の繁殖状態など様々な要素が複雑に絡まって味を形成しています。そのデリケートさは、例えば容器から移し替える時間が数秒変わっても味に影響してしまうほどなのです。ですから酒蔵の従業員は機材の配置変更すら嫌います。それが生産拡大のための増設に否定的なことにも繋がっているのです。
「獺祭」が起こした革新
これらのことから、日本酒はブームといえどすぐには増産できないことがお分かりいただけたと思います。
しかしこの閉鎖的で変化を嫌う酒蔵業界に新風を巻き起こした酒蔵があります。ご存じ人気銘柄「獺祭」を製造する旭酒造株式会社(山口県岩国市)です。旭酒造は長く「旭富士」という一般酒を製造していました。現在の社長桜井博志氏が父の後を継いで社長に就任した昭和59(1984)年には、その年間生産量は僅か126キロリットル、売上高9700万円と、これまで述べてきた典型的な地元消費型の零細酒蔵だったのです。
それを桜井氏が変え、日本のみならず世界中で注目される「獺祭」を生み出し、大躍進を遂げたことは広く知られるところですが、酒蔵という変化を嫌う業態でなぜこれだけの改革ができたのでしょうか。
その理由の一つは杜氏に恃んだ生産を止めたことです。酒作りの総指揮者である杜氏は、その味を決める重要な役割です。杜氏が変わると酒の味は変わりますし、杜氏が同じだと別の蔵でも味が似てきたりします。
この杜氏を旭酒造では入れず、データと社員たちによる集団管理によって製造しています。それによって常に安定した品質での商品製造が可能になり、生産拡大へと繋げることができたのです。実際、旭酒造の現在の生産量は5400キロリットル(2022年)と、桜井氏の社長就任から約40年間で40倍以上に拡大しています。
しかしこの方法に関しては批判の声もあります。安定品質で大量生産となると酒の「年ごとの味わいの変化を楽しむこと」や「趣」が損なわれる、といった意見もあり、アンチ獺祭の日本酒好きも多数いるのです。
しかし増産によるメリットも多くあります。売上増もさることながら、原材料である酒米の生産農家への利益波及です。これまで酒米の生産農家は卸す酒蔵の生産量が減少すれば、それに従って米の生産量も減少させざるを得ない状況でした。「今年はこれだけしか作らないので米はこの量しかいりません」と酒蔵から言われてしまうと、農家はそれだけ利益が減っていたのです。しかし旭酒造が常に一定して購入してくれることで農家の利益も安定する。ステークホルダーに対しても好循環が生み出されているのです。
おわりに
今回は日本酒を取り巻く状況を、酒蔵側からの視点で考えてみました。
日本酒はそのデリケートさから簡単に増産ができないものですが、その結果人気銘柄はその希少性も相まって価格が高騰、高額のプレミア価格で取引されることもあり、その様相は今後も続いていくと考えられます。(※)
またそういった人気銘柄があることに対して、ひっそりと生産を終了している酒蔵も多数あります。地方自治体ではこれを憂慮していて、酒蔵を事業承継してくれる企業を募集していたり支援金を出すという施策をとっているところもあります。
日本には1万を超える銘柄の日本酒があるといわれます。まだ見ぬ美味しいお酒との出会いに思いを馳せるのも酒好きの愉しみですが、この業界の状況に目を向け、日本酒の行く末を考えながら呑むのも一興ではないでしょうか。
※ こういった高値の銘柄からの販売利益は酒蔵には入っていません。酒類は製造者と販売者が明確に区別されており、酒蔵は販売業者に卸値で受け渡しているのですが、一部販売業者が消費者に販売する際に価格を上げている現状があり、これも問題になっています。