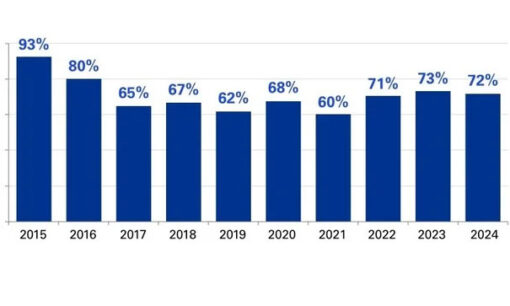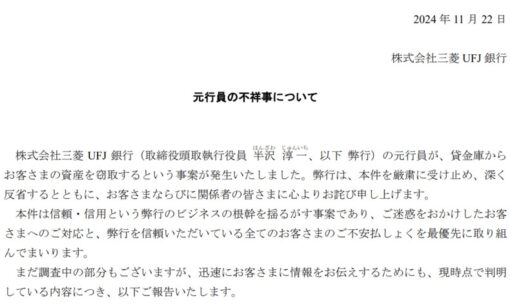大中忠夫(おおなか・ただお)
株式会社グローバル・マネジメント・ネットワークス代表取締役 (2004~)
CoachSource LLP Executive Coach (2004~)
三菱商事株式会社 (1975-91)、GE メディカルシステムズ (1991-94)、プライスウォーターハウスクーパースコンサルタントLLPディレクター (1994-2001)、ヒューイットアソシエイツLLP日本法人代表取締役 (2001-03)、名古屋商科大学大学院教授 (2009-21)
最新著書:『創造力プログラミング』2022改訂版
日本を「日本株式会社」という一つの会社に見立てて再興の鍵を探す、大中忠夫さんによるコラム。改革の成否を決定づける「創造力」とは何か?
なぜ創造力の必要性を認めないのか? -その1.創造力は特殊能力との思い込み
日本株式会社の20年以上の停滞とそれがもたらした日本経済の衰退を立て直す社会的潮流が、岸田政権の「新しい資本主義」や産官学賢人会議主導の「人的資本経営」を始動させています。しかし、この改革の成否を決定する基盤条件については未だ何も提起されていません。
その基盤条件とは、日本株式会社の創造力復興です。これについては、何ら具体的な施策も工程表も示されていません。それどころか、創造力の復興が経済再生の大前提となる事実すらも提起されていません。
原因は三つ考えられます。
1)創造力という社会的人間性に基づく能力の地位が、20世紀の科学的合理性追求型社会によって、その価値が社会全体で大きく衰退したことです。
2)その結果、現代社会では創造力は特殊な先天能力であるとの思い込みが当たり前になってしまったことです。
3)どのようなイノベーションの提起も特殊先天能力を必要とするものと片づけられるようになり、実現性を疑われてしまうことへの懸念、配慮です。
しかしながら、創造力を、日本社会全体に復興させることなしには、日本経済の新たな進化成長をめざすどのような改革もいずれ掛け声で終わってしまいます。創造力という実効力をともなわないからです。この因果関係の事実については、日本社会は既に十分に体験しているはずです。
政府からの繰り返しの要請にもかかわらず、過去20年以上にもわたり実質賃金がまったく上昇しなかった事実が因果関係を証明しています。
ここにきて、少なくない方が創造力を根本的に復興しない限り、いかなる経済成長も実現することはないことに感じはじめているのではないでしょうか。
では、なぜ創造力の復興に向けての一歩を踏み出せないのか?
原因の一つが、現代社会の金融政策に関する「幻想」です。この幻想が、何か特殊能力にも思える創造力に依存しなくても何とかなるのではないか?という思いを日本社会全般に抱かせています。
なぜ創造力の必要性を認めないのか?―その2.金融政策で経済成長を実現する幻想
いまの社会を覆っているのは金融政策で経済成長や景気上昇が実現できるという思い込み、幻想です。確かに、金融緩和は、個や集団・社会全体の思考をリラックスさせる効果をもたらすかもしれません。社会的な緊張や切迫感・不安感を解いてくれます。
しかし、それだけで経済成長の基盤である個と組織の創造力が高まることはありません。金融政策で経済成長が実現できるというのは幻想にすぎません。
もし金融緩和で個人的、社会的な創造力が高まるのであれば、主要な基軸通貨量が指数関数的に増大し過剰に充満している現代グローバル社会では、逆の相関として創造力も同様に社会に溢れ返っているはずです。しかし、そのような現象は出現していません。金融政策が経済成長を実現することはないのです。
これを証明している事象もあります。20世紀後半以来グローバル社会に何度も出現しているバブルの出現と破裂です。バブル破裂とは金融量増加に実質経済成長が追いつけない、あるいは前者が増加しても後者は成長しない、現象です。この20世紀後半からのバブル破裂の繰り返し(注1)が、金融政策では実質的な経済成長は実現できないこと、を証明しています。
注1:80年代末の中南米、90年代の日本、韓国などでのバブル破裂、21世紀初頭では金融経済の源泉である米国でのITバブル破裂、2008年のリーマンショック、そして2022年7月には再び米国社会で、リーマン規模あるいはそれを超えるバブル破裂のリスクが警告されています。
なぜ金融政策では経済成長が実現できないのか?-現代経済の二階層構造
では、なぜ金融政策で経済成長は実現できないのでしょうか。この原因は、金融経済と実体経済を独立した二階層で構成されているものだと捉えることでよくわかります。
実体経済とは社会全体での衣食住などの価値の産出と交換により利潤を産み出す経済を指します。
金融経済は実体経済の運営に必要な通貨資本を供給することにより利潤を生み出す経済を指します。
したがって、通貨流通そのものが利潤を生み出す金融経済は、政府と中央銀行の通貨供給増によって直接的に成長します。さらに、70年代中盤からの金融証券取引の出現により、金融経済内部のみでの取引利潤実現も可能となり、通貨供給量増大に対する金融経済の成長弾力性もさらに高まりました。
しかし、この金融経済とは投融資関係で連結されているものの、それ以外は独立運営されている実体経済の方はそうはいきません。実体経済は、流通価値を開発・製造・販売することで初めて成長するからです。
したがって、金融政策が実体経済の成長に、即効的にはもちろんのこと直接的にも、影響力をもつことはありません。この事実は、米国社会でも既に半世紀以上前からJ.K.ガルブレイスなどの経済学者に指摘されています。ただ、少数意見に留まっています。米国社会でも日本社会でも、政府と中央銀行の金融政策が実体経済を直接成長させることはできないという事実が、見逃され続けています。
なぜ金融政策による経済成長の幻想が存在し続けているか?― 金融経済成長と経済成長の社会的混同
この現実がなぜ見逃されているのか?その原因を一言でいえば、金融経済の成長と経済成長の混同です。
それは金融経済の成長、すなわち株価の上昇、があたかも景気の上昇、経済の成長であるとする混同です。経済を構成している二層の一つでしかない金融経済の膨張をあたかも経済全体の成長と混同しているのです。
その結果、金融経済バブル破裂の繰り返しも何か必要悪、あるいは経済成長の過程で辿る当然の帰結と思われてしまっている節さえあります。「これからもバブル破裂は繰り返される!」と、まるで学術的法則を発見したかのごとく自慢げに口にする経済学者も少なくありません。
研究者のみではありません。現代社会も、台風か何かのように、バブルの繰り返し破裂に慣れてしまっているのではないでしょうか。しかし、その慣れが、金融政策がいつかは経済成長を実現するのではないかという幻想を存続させ続けています。
金融政策への幻想期待が現代社会に何をもたらしているか?―バブル破裂のもう一つの形、繰り返され続ける戦争と紛争
しかしバブル破裂は人間社会に深刻な不幸をもたらし続けています。金融政策に起因する経済破綻、金融通貨量と実質経済力との過剰乖離は穏健な表現ではバブル破裂と呼ばれています。しかし、現代史には凄惨な経済破綻、あるいはバブル破裂も複数出現しています。紛争と戦争です。
バブル破裂を、金融経済の過剰膨張に実体経済が追いつかない社会的破綻と広く定義すれば、それは現代経済学が指摘する穏健な経済破綻のみにとどまりません。1929年の米国発の世界恐慌とそれに続く第二次世界大戦、それに続く、朝鮮、ベトナム、イスラエル-エジプト、アフガニスタン、イラク、イラン、そしてウクライナまでの地域での紛争と戦争も、凄惨なバブル破裂、あるいはその結果と言えます。
現代社会は、平和裏なバブル破裂以外に、20世紀初頭から現在まで大規模なものだけでも10件以上の、それぞれの継続期間を考えれば、ほぼ連続的に、この悲惨なバブル破裂を繰り返しているのです。
なぜ戦争と紛争がバブル破綻のもう一つの形なのか?-高度経済成長社会は自ら戦争や紛争を起こす必要がない
因みに、どのような戦争や紛争にも必ず何らかの政治的な大義が掲げられています(大義が明確でない、あるいは虚偽であったものもあったようですが)。しかし、本質的な原因はいずれも国内経済の何らかの行き詰まりにあります。
なぜそう言えるか?簡単なことです。自国経済が全面的に健全に、特定の軍需産業などに依存することなく、発展し続けている政府や国家は自らその状況を破壊する戦争や紛争を起こす必要はないからです。
さらに、戦争や紛争は、その終結後も、勝者にも敗者にも長期間の社会的・経済的な後遺症を産み出します。第二次世界大戦後の日本社会経済復興を首相として牽引した池田勇人は、著書『均衡財政』で第二次大戦の反省に基づいて、「経済成長の最終目標は世界平和である」と宣言しています。これは、経済閉塞や破綻が戦争をもたらす因果関係を直接示唆しています。
さらに2022年現在のウクライナ紛争は、核の時代の紛争が人間社会全体の消滅リスクすら高めている事実を広く世界に公開しています。人間社会が100年以上もの間抱き続けていた金融経済による経済成長の幻想が経済閉塞や破綻をもたらすことで、21世紀には単なる幻想に留まらず大規模な戦争を起こす温床ともなっているのです。この事実を直視すればこの幻想に期待し続ける理由はもはやないでしょう。
となれば、あとは経済成長には創造力が必要だという現実に向き合うだけでしょう。しかし、そのことを納得して一歩踏み出すためには、最後にもう一つの解消すべき壁があります。
それは、特に日本社会で、個や集団、社会の創造力が経済成長を実現した事例がないという思い込みです。
なぜ創造力の必要性を認めないのか?―その3.創造力が経済成長を実現した経験がないという思い込み
社会心理学の学問的厳密さ、あるいは森を見ずに木のみを眺め続けたことの最大の過ちが、1960-70年代の日本の高度経済成長社会は、日本社会全体が実現した紛れもない創造物であることを見逃していることでしょう。原因には、創造力を特殊能力と思い込んでいる社会認識以外に、この高度経済成長を嫉妬、揶揄あるいは過小評価する、日本社会内外のさまざまな思惑や意見があったと思われます。
例えば、60-70年代には、日本人に対する「エコノミック・アニマル」という呼称がありました。この呼称は創造力をアニマル・スピリットと表現したケインズ経済学の専門家であれば最高の尊称と受け取るかもしれませんが、一般には人間差別の別称のように受け止められました。
多くの日本人もそのように呼ばれることを必ずしもよしとはしませんでした。そのような国際社会からの認識を感じる時代には、自ら実現した高度経済成長の社会基盤に日本的な創造力が存在したという事実に思い至ることもありませんでした。
さらには、エコノミック・アニマルの延長で「日本人は模倣がうまい(だけだ)」というプロファイリングも日本社会内外に喧伝されました。確かに、高度経済成長の原動力であった製造産業の最重要原料、トランジスタ、は日本国内で研究開発されたものではありませんでした。
因みに、池田勇人首相を「トランジスタラジオの商人」と小馬鹿にした大統領もいました。また、テレビ、洗濯機、冷蔵庫などの電化製品も日本発の発明ではありませんでした。
しかし、その原材料や製品を活用して第二次大戦廃墟に出現した高度経済成長社会は、日本社会史上の偉大な創造物に他なりません。そして、この歴史的な創造物を実現したのは、当時の日本社会に存在した創造力に他なりません。現代日本社会はこの事実を自然体で認めるべきでしょう。
なぜ創造力の必要性を認めないのか?―その4.高度経済成長社会喪失のトラウマ
しかし、もう一つ、その事実を受け容れることを難しくしている事実があります。それが、高度経済成長社会の衰退と喪失です。そして、それによるトラウマ(心理後遺症)です。さらに、現代社会の40歳未満世代は、そのような高度経済成長の経験すらありません。ものごころついたときから日本社会経済は低迷し下り坂であったのですから。
とはいえ、なぜ高度経済成長社会が衰退消滅したかを徹底的に検証すれば、そこには創造力を喪失する重要な原因が見えてきます。そしてそれらの原因が同時に、創造力を醸成、進化させる条件でもあります。
高度成長経済衰退の原因として先ず一般的に指摘されるのは、日本社会の自国経済力に対する過剰な自信や熱狂です。これらがさらに何らかの価値を獲得して豊かになることに専念する意識過剰な社会文化を生み出しました。それがさらに日本社会の強みでもあった個々人の社会貢献意識、社会に役立つ自己の存在認識を衰退させました。
これが、まさに創造力の必須基盤条件でした。すなわち、貢献意欲と自立意識(他者に役立つ自己実現意識)あるいは、簡易な表現では、人間相互の思いやり、が創造力を醸成する切り札であったのです。
なぜ創造力の必要性を認めないのか?―その5.外部金融経済による実体経済への圧力と操作
高度経済成長喪失のトラウマを解消するためには、内的原因のみならず、もう一つ外的原因も直視する必要があります。その外的原因は3段階で日本社会に飛来しました。
第一弾は、日本社会外部からの政治的圧力です。70年代初頭には米国政府から当時の日本の最大輸出品であった繊維製品の輸出が規制されました。そして80年代にはほぼ10年間にわたり、同じく最大輸出品であった自動車の自主的な米国向け輸出規制を実施させられました。
第二弾は、1985年のプラザ合意でした。為替円レートの突然の大幅引き上げです。因みに、当時の米国自動車業界の経営者の一部からは、日本製自動車の驚異的な米国内販売増は日本円の不公平に低い為替レートによるものであり、米国自動車会社の経営力が問題なのではない!といった証言が米国議会に提出されていました。
しかし、これらの二つの着弾は、誰もが認識できる顕在的な圧力であったために、日本の産業界は少なからぬ痛手を被りながらも、これらをさらなる進化の糧としました。これも当時の日本社会の創造力によるものです。
そして第三弾は、政治的な圧力の形を取らない、金融経済による実体経済の抑制操作でした。最初に、日本経済高度成長の基盤であった金融業界が緊縮させられました。いわば、馬を射止められたのです。1988年の国際決済銀行による銀行融資規制、BIS規制(注2)です。
株主第一主義の流入と浸透
その結果何が起こったかは現代からは明らかです。金融業界の緊縮によって、政府・中央銀行―金融機関―実体経済の資金流が突然絞られたために、新たにより大きな資金・資本の流れが必要になりました。
その結果1990年代を通じて、外資導入自由化が本格化しました。それは、当時の日本企業の過信や閉鎖性を打破し、さらに膨大な資本・資金を海外からも取得できる大きな機会をもたらしました。しかし同時に、株主第一主義経営、会社は株主すなわち金融経済の財産であるとする企業定義と経営標準、ももたらしました。
株主財産を最大化する短期業績経営による実体経済の経年疲弊
株主第一主義経営の短期業績最大化の追求が、会社とその集合体である実体経済の持続的な進化成長力を徹底的に衰退させました。経済の第一層である金融経済が、その基盤となっている第二層の実体経済を構成する会社群に、株主のための短期業績を最大化する経営を要求することで、実体経済を疲弊、衰退させ続けたのです。
なお、この因果関係の事実は、株主第一主義の本家である米国ビジネス社会を牽引する米国ビジネスラウンドテーブルの議長、JPモルガンチェース銀行CEOですら、2019年に株主第一主義の撤廃(Scrapping Shareholder Primacy)を公然と提起したことでも明らかです。
基盤となる実体経済を構成する会社群が衰退し続けるままでは、いずれその上層の金融経済も立ちゆかなくなるとの認識が米国社会でも高まり始めたということでしょう。
「外圧」とは認識できなかった株主第一主義要求
しかし、残念なことに、この株主第一主義経営が日本社会にとっての「外部圧力」であることは、少なくとも最近に至るまでの20年間には認識されることはありませんでした。日本社会が歴史的にその進化の糧としてきた「外圧」とは認識できなかったのです。その結果、最終的には、その株式第一主義経営が「日本経済の基盤である会社の基盤である社員の基盤である創造力」を衰退させてしまった事実も、あるいはその創造力を復興させる必要性も見逃すことになりました。
注2:どのようにして日本経済の「馬」が射止められたのか?BIS規制とは、金融機関が国際ビジネスに従事する条件として、各行の金融リスク総額に対する自己資本比率を8%以上とすることを求めたルールでした。これがなぜ馬を射止めることになったのか? 20世紀の日本の高度経済成長の本質は実体経済の成長でした。その成長を政府・中央銀行から銀行業界を経由した金融力が支援していました。創造力を備えた会社と社会に対する金融供給は、その創造力を損なわない限り、強力な経済成長原動力となっていたのです。
因みに1989年の世界の時価総額トップ10社には日本の大手金融機関が5行入っています。それは日本の大手都市銀行によるほぼ制限のない実体経済企業への資金・資本の注入の見返りでもあり証明でもありました。この資金・資本の奔流が、BIS規制というバルブで急遽絞り込まれました。BIS規制は88年に合意され日本社会にも93年から適用開始されました。この期間に、日本経済のバブルが破裂しました。
創造力の社会的復興の第一歩をどう踏み出すか?―日本経済の過去半世紀の栄枯盛衰を直視する60-80年代の高度経済成長の事実が創造力の存在証明
まずは20世紀中盤の日本の高度経済成長が紛れもなく当時の日本社会の「創造物」であった事実を再確認することです。そうすれば、その経済の成長の基盤である会社の成長の基盤は「社員」であったことを再認識できるでしょう。
会社そしてその集合体である経済の高度成長基盤が、ロボットや機械ではなく、社員であったのです。このことが、経済-会社-社員の成長連鎖の基盤には、人間のみが保有する創造力が存在していたことを教えてくれます。
90年代以後の長期経済低迷時代から学ぶ創造力の基盤条件
第二次大戦敗戦の廃墟から奇跡とも呼ばれた高度経済成長社会を復興したものは何であったか?そしてその成功の熱狂と過信の中で何を失ったのか?
それは、廃墟の中で日本社会の一人一人が自らの力で自身と家族の生活を立て直し、そしてそれぞれの立場で会社、地域、そして日本社会全体、の復興に尽くした。この意識と行動であったでしょう。
自立意識と貢献欲求、一言でいえば「思いやり」による自己実現、これが高度経済成長社会を実現した創造力の基盤要件であったといえるでしょう。
自己の創造力を認知して実践する
以上の、「なぜ創造力の必要性を認めないのか?」の5つの原因を解消できれば、あとはご自身の創造力を認知して実践するのみです。これらの思考手順については「創造力プログラミング」第1章 創造力を認識する、第2章 創造力を実践する に詳細説明しています。
なお、同書では、上記2章につづいて、第3章 創造力を点検する、第4章 創造力を鍛錬する、第5章 創造力を増強する、第6章 創造力を進化させる を提案しています。
創造力は誰にも与えられており、そして他のすべての能力と同様に、意図すればさらに進化させることができます。同書が創造力を認知して実践、強化する案内書となれば幸甚です。
『創造力プログラミング』2022改訂新版 大中忠夫・日下幸徳 共著