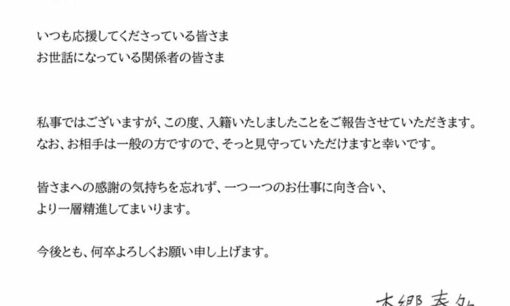老後をどこで迎えるかという個人の選択が、ここまで激しい怒りを呼ぶ社会になってしまったのか。
1月29日に日本経済新聞が配信した「人生の最後は日本で 米国から永久帰国 当事者の決断」という1本の記事が波紋を広げている。記事によると、東京出身の78歳男性は18歳で渡米し、約60年間を米国で過ごした。妻とともに現地で生活基盤を築き、「素晴らしい人生を送った」とされるが、円安を機に日本でマンションを購入し、老後は日本で暮らすことを決断したという。
いわゆる「永久帰国」だ。日本に戻った男性は在留資格を得て滞在し、国民健康保険にも加入可能な立場にある。制度上、違法性はない。
だが、この記事が公開されるや、X上では一気に空気が変わった。
「帰国税1億円払え」怒りが爆発したXの反応
「社会保障のタダ乗りだ」「50年以上、日本で保険料を払っていないのに、同じ医療を受けるのはおかしい」
中でも、「こういう社会保障タダ乗り爺婆は、帰国税として1億円くらい請求してほしい」とする投稿は、3万6千件を超える「いいね」を集め、炎上の象徴となった。
特徴的なのは、その怒りの向きだ。「これ、今問題視されている移民の医療福祉タダ乗りと何が違うんだ」「外国人ならまだしも、日本人だから余計に腹が立つ」
同じ国籍を持つ“同胞”であるがゆえに、感情が先鋭化している側面がある。
「挑戦した人生だろう」擁護の声も確かにある
一方で、記事のコメント欄やSNSには、冷静な擁護の声もある。
「若い頃に憧れのアメリカへ渡り、何十年も暮らしたのは挑戦そのものだ」「向こうで散々、税金も保険料も払ってきたはずだ。最後くらい日本でいいのではないか」
実際、米国で長年働いた場合、年金にあたるソーシャルセキュリティだけでも、年間400万〜500万円規模になることが珍しくない。これらの年金や401k、家賃収入、利子収入は、日本に帰国すれば日本で課税対象となる。
つまり、「日本の社会保障だけを使いに戻ってきた高齢者」と単純化できる話ではないケースも多い。
帰国者を叩いても、制度の限界は消えない
それでも、怒りが収まらない背景には、より深刻な問題がある。現役世代が背負う社会保険料は年々重くなり、「このままでは将来がない」と感じる若者も少なくない。日本の社会保障制度は、すでに限界に近づいているという実感が広く共有されている。
だからこそ、海外からの帰国者が“象徴”として叩かれる。
「70歳までに本来払う分を一括で払わせたら、受給できるようにすればいい」「一定期間以上、保険料を納めた人だけが最低保障を受けられる制度にすべきだ」
こうした声は、感情論の裏にある制度不信を物語っている。
本質は「自己負担1割」と「過剰医療」ではないか
議論の中で、より本質的な指摘も出ている。
「いろいろな批判を受けて思ったけど、問題の核心は自己負担1割と過剰医療だと思う」
「社会保障に対する苛立ちが、海外勢にも飛び火しているだけではないか」
高齢者医療の自己負担1割制度は、現役世代との不公平感を生みやすい構造を抱える。加えて、過剰な検査や投薬が医療費を押し上げているという指摘も根強い。
「海外からでも保険料を払える制度があるなら、しっかり払う」
「その代わり、自己負担3割への見直しや、過剰医療の抑制を本気でやってほしい」
これは、帰国者を擁護する側から出た声でもある。
「貧すれば鈍る」日本社会の現在地
老後をどこで迎えるかは、本来、個人の自由である。年金、税、社会保険といった義務を果たしていれば、恥じる理由はないはずだ。
それでもなお、同胞に対してすら「汚い」「許せない」という言葉が投げつけられる。その背景にあるのは、日本社会の余裕のなさだ。
「貧すれば鈍る」。制度の持続可能性に対する不安が、人々から寛容さを奪っている。
問われているのは、78歳男性の人生選択ではない。制度疲労を起こした社会保障を、どう立て直すのか。
その議論を先送りにする限り、次の炎上は、また別の誰かに向かうだけだ。