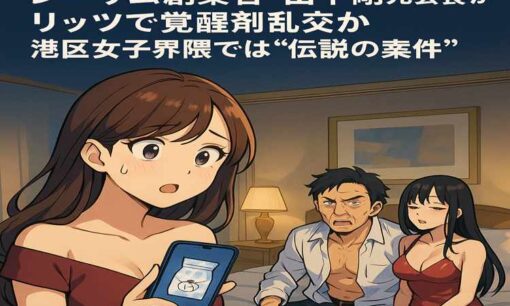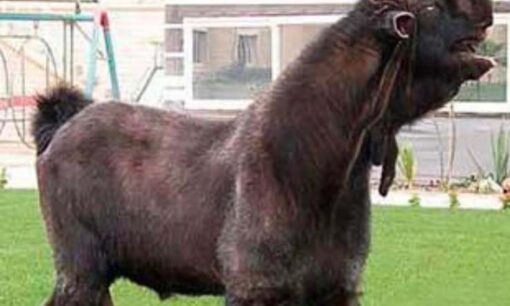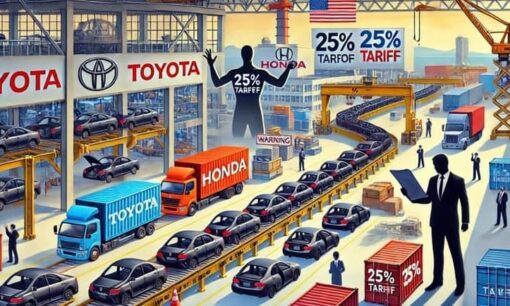インスタやXで鮨や海外旅行の写真を投稿し、まるで「親が太い」「彼氏が富豪」と言いたげに振る舞う若い女性たち。だが、実際にはその多くが交際クラブに登録し、資金源を得ていると指摘する声がある。滝沢ガレソ氏がリポストし話題になったインフルエンサーのomochi氏の9月13日の交際クラブの解説投稿は、そうした“魔境”の実態を生々しく伝えている。そこに広がっているのは、金銭感覚が完全にバグった世界だ。
「お金が尽きたらすぐ海外に飛び、豪華な暮らしをSNSにあげる。でも実際は交際クラブでの収入が日常化している。しかも薬物や海外案件まで組み込まれている」。omochi氏はそう警告する。
「交際タイプ」と建前と現実
交際クラブの登録では「A=食事のみ」「B=ゆっくり」といった建前がある。だが、現実には「C=2回目から」「D=フィーリング次第」「E=積極的」のゾーンでの活動が主流で、AやBで稼げるのは芸能人級の容姿を持つごく一部に限られる。
クラブ自体は東京都のデートクラブ条例に基づき届け出られ、男女ともに面接が必須とされる。しかし、公式サイトが語る「安心・健全な大人の出会い」と、実際に交わされるやりとりの乖離はあまりに大きい。
魔境をのぞく体験ルポ
「初めて会ったのは丸の内の高級鮨店。顔合わせだけで交通費として1万円を受け取り、次は銀座のバーへ。その後はホテル直行で1時間10万円。『これで今日は終わりね』と笑顔で現金を差し出され、正直、頭が真っ白になった」。
こう語るのは20代半ばの元大学生。交際クラブの紹介で訪日韓国人の客と会い、以降、定期的に呼ばれるようになったという。
「最初は怖さもあったけれど、周囲の女友達も皆やっていた。普通のバイト代では到底追いつかない金額が、一晩で入ってくる。感覚が壊れていった」。
この証言は、omochi氏が言う「金銭感覚のバグ」の象徴だろう。SNS上で着飾った写真を投稿しながら、裏では国籍を問わぬ顧客と交渉を繰り返す。やがて「高いバッグや整形にいくら使ったか」で女性同士のマウント合戦が起き、生活がさらに加速していく。
実際に存在するクラブの顔ぶれ
現在、日本には数十を超える交際クラブが存在する。業界最大手とされるユニバース倶楽部は全国に拠点を展開し、同系列のPATOLO(アプリ型)や、対面型のユニバースラウンジ、超富裕層限定のザ・サロンまで階層を広げている。また、可愛い女の子が多いマッチングアプリとして人気のあるペーターズが提供するペーターズクラブなども人気のようだ。
老舗では青山プラチナ倶楽部、白金アクアマリン、RN246などが高額会費と厳しい審査を掲げる。ヴェルサイユや銀座クリスタルは芸能関係や地方都市にもネットワークを持ち、会員の属性を分けている。
料金は男性の入会金・年会費・紹介料を合算して最低でも5万円台から、上位会員なら数十万〜100万円超。こうした「高額を平然と払える太パパ」だけが参加できる構造となっている。
華やかさと裏腹のリスク
一見すると高収入の富裕層と若い女性の効率的なマッチングだが、その裏には恒常的な売春や薬物、海外案件などのリスクが潜む。SNSで“キラキラ女子”を演じる彼女たちは、実際には「交際クラブの魔境」で命を削るように日々を過ごしているのだ。
魔境に取り込まれた日常
「今日は鮨で、そのあとホテルで1時間。手渡しで10万円。これが普通になってしまった」
ある女性はそう淡々と語った。かつては大学のカフェでバイトをしていたが、今は銀座の交際クラブからの紹介が生活の基盤だという。
SNSには「#海外旅行」「#ご褒美ディナー」といった写真が並ぶ。だが、裏側は違う。周囲に「親が太い」と笑ってごまかしながら、実際は週3のデートで得た現金で生活を組み立てている。バリ島から連投される写真の裏で、金銭感覚は崩壊し、友人との会話は「どのブランドのバッグを次に買うか」「整形にいくらかけるか」ばかりになった。
比較すれば狂気は一層浮かび上がる。普通の20代OLが1か月かけて稼ぐ23万円前後の給与と、交際クラブ女子が“一晩”で手にする10万円超が、同じ財布の中で並ぶのだ。数字が現実感を失わせ、やがて「もっと稼げるはずだ」という幻想が麻薬のように日常を支配する。
SNSでは「彼女はただの港区女子」「実家が太いんじゃない」と冷笑が飛ぶ。匿名の揶揄は鋭く、「インスタで煌びやかに笑っていても、実際は銀座でパパ活漬け」と囁かれる。虚像と現実の乖離は、時に本人自身さえも飲み込んでいく。
一方で、男性側は「経営者として効率がいい」「素人感が大事」と口にする。自分の欲望を正当化する言葉に隠れながら、彼らもまたこの魔境の構造を支えている。華やかに見える取引の背後にあるのは、双方が「割り切った関係」という言葉で覆い隠した欲望の市場だ。
こうして交際クラブは、煌びやかなSNSの虚像を下支えする“魔境”として、今日も誰かの人生をのみ込んでいる。そこに足を踏み入れるかどうか――最後に問われるのは、当事者が現実を直視できるかどうかである。