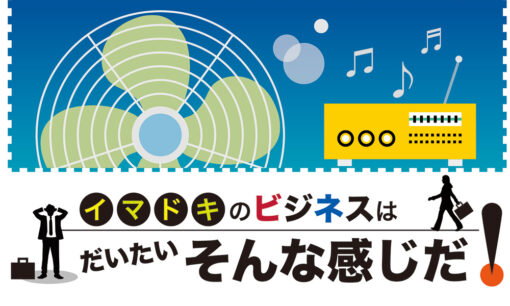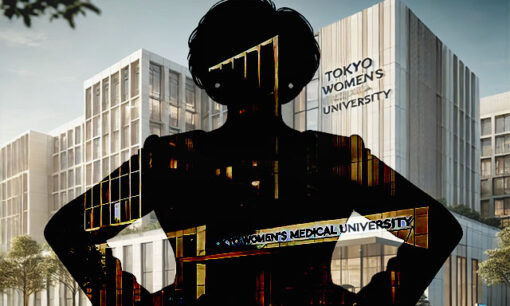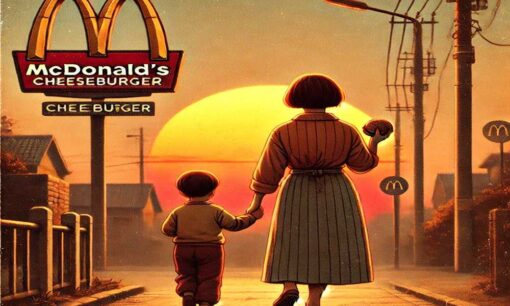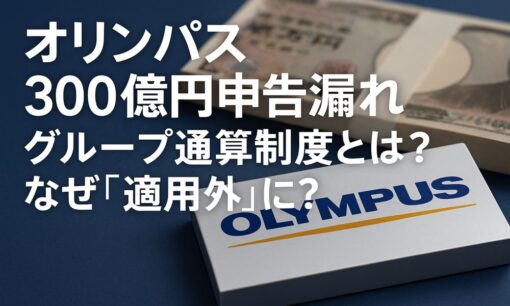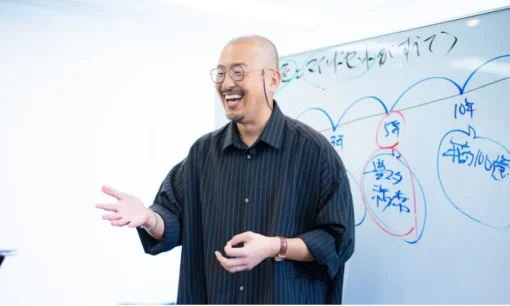お笑い芸人のTKO木下(53)がタイ移住直後に寺院前で袈裟姿の動画を投稿し、SNSや現地から反発を受けている。X上では「TPOはダメで草」と揶揄する声がある一方、「少しも調べないバカはいやねえ」「宗教観が違う。真夜中に玄関を叩かれてヒット(拘束)される国でもある」といった在タイ邦人・タイ人からの指摘が相次いだ。
日本では“せんと君ノリ”の軽い演出が通用する場面があるが、仏教国タイでは僧衣は信仰共同体の象徴であり、冗談が冗談で済まない。
僧衣は「衣装」ではない タイ刑法208条の重み
タイでは僧侶の地位は極めて高い。刑法208条は「僧侶や聖職者を誤信させる目的でその表象を不当に使用した者」に1年以下の禁錮または罰金を科すと定める。観光客のコスプレ感覚は、現地法では通じない。
パタヤでも炎上、バイクに乗った僧侶と観光客
似たような騒動は過去にもあった。パタヤでは観光客と僧侶がバイクに二人乗りする動画が拡散され、「仏教を軽視している」と住民から批判が殺到した。宗教的象徴を“演出”に使えば、すぐさま世論の逆鱗に触れる。それが仏教国タイの日常なのだ。
さらに、偽物の僧侶や寄付金詐欺の摘発は定期的に報じられてもいる。たとえばタイ国内でカンボジア人の偽僧侶が寄付集めで摘発された事案や、僧籍者を含む偽の托鉢行脚による詐欺事件などは度々報道されているようだ。
贅沢をした僧侶の摘発史から見る世論の厳しさ
僧侶のモラル逸脱には世論が不寛容。私的ジェット機映像で悪名を轟かせた元高僧・ウィラポン(通称“ジェットセット僧”)は、詐欺・資金洗浄などで禁錮114年の判決に至ったという驚愕の事実も。
僧侶は尊敬される存在なだけに、清貧であることも問われるというガチ宗教っぷり。キャバクラなどに繰り出せば、下品そのものな禿げ坊主たちが馬鹿騒ぎしている日本の生臭坊主たちにも爪の垢を煎じて飲ませたいような仏教の環境なのだ。
直近でも、寄付金の不正疑惑をめぐり著名僧が逮捕・還俗に至ったケースが続く。7月には僧侶への色仕掛けと恐喝で巨額を得たとされる女の逮捕と複数高位僧の還俗が国際報道され、当局は寺院資金の監督強化と法令見直しに言及までしている。
8月下旬にはエイズ療養施設に関わる横領容疑で著名僧が逮捕され、手続上僧衣を脱いだうえで訴追に臨んだと報じられた。制度と運用の両面で、宗教の廉潔性を守る圧力は強い。
Xににじむ“現地の肌感”
今回の木下動画に対して、Xでは「TPOをわきまえろ」という短い嘲笑から、「タイは宗教法制が厳格。僧衣はコント小道具ではない」「寺前での演出は“神聖の侵食”に映る」といった批判まで幅広い反応が見られた。
Xには在タイ邦人の声も目立った。「日本のせんと君ノリはここでは通じない」「敬意を欠けば、夜中に戸を叩かれるのもあり得る」。タイでは宗教と日常が密接に絡み合っており、僧衣は単なるコスチュームではなく共同体の清廉の象徴だ。木下の軽いノリは、まさに“聖と俗の境界”を無自覚に踏み越えた行為だった。
文化の境界線を越える前に
タイで暮らし、発信する者に求められるのは、相手国の文化や宗教への敬意であることは言うまでもない。軽いノリの延長で寺院や僧衣を舞台装置にしてしまえば、現地社会からは不敬と映り、笑いどころか反発を招くのは必然だ。
不運続きのTKO木下が、この先どんな新しいステージを見せるのかは未知数だ。しかし、まずはタイ社会に受け入れられる存在になることが先決であり、その第一歩は「現地へのリスペクト」から始まるだろう。
そうでなければ、次は本当にタイ人からペットボトルを投げつけられる日が来るかもしれない。もっともタイは“レディボーイ”文化が根づく国でもある。かつて日本でそっち系の美人タレントとの浮名も流れた木下にとって、その手の世界は決して遠い話ではない。ならばまずは、彼女たち——あるいは彼——から、タイという国の奥行きをじっくり学ぶことが、炎上芸人としてではなく“移住者”としての再出発につながるのではないか。