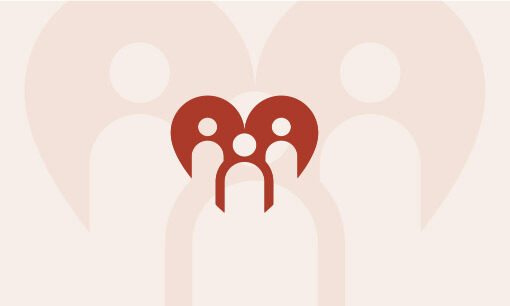全国で郵便物の不配が少なくとも約4000通にのぼり、日本郵便が公表していなかった事実が明らかになった。職員のロッカーや自宅、休憩室などから発見されたり、シュレッダーで細断されて廃棄されていた例もある。差出人が気づけない可能性があり、郵便制度の信頼を根底から揺るがす深刻な問題だ。民営化から20年近くが経過しても不祥事が繰り返される背景には、経営の透明性不足と現場の過酷な労働環境があると指摘されている。
非公表の不配、4000通超
日本郵便は2021〜24年にかけ、郵便局員による郵便物の放棄や隠匿を巡り23件を公表した。対象となったのは約2万5000通に及ぶ郵便物で、一部は警察に立件されるなど「犯罪」として認定されたものだ。
しかし関係者によると、同じ時期にこれとは別に、非公表のままとされた事案が少なくとも約30件、計4000通以上存在していた。郵便物は局員のロッカーや休憩室、自宅の押し入れや宅配ボックスから発見された。中にはシュレッダーで細断され、ごみとして廃棄されていた郵便物もあったという。
「犯罪」のみを公表という基準
日本郵便は原則として「犯罪と認定した事案のみ」を公表してきた。非公表事案についても「確認できる限り差出人に謝罪や経緯説明を行っている」と説明するが、差出人が特定できず、謝罪や説明が不可能なケースもあるという。
もし郵便局名や発生時期といった概要が公表されれば、差出人は自らの郵便物について問い合わせることが可能だ。しかし事案そのものが非公表であれば、差出人は「出した郵便物が届かなかった」という事実を知る術すらない。利用者保護の観点からも、公表基準のあり方が問われている。
利用者の不安とコメントの声
今回の不配問題を巡って、インターネット上では批判が相次いでいる。
ある利用者は「民営化しても体質は変わらない。まず意識改革が必要なのは現場ではなく経営幹部だ」と指摘する。国が民営化によって事業から手を引きつつも、依然として所有権を持つ“歪な構造”が改革を阻んでいるとの見方だ。
また「郵便物は人の人生を左右するもの。特別な権限を与えられている自覚を持って仕事をしてほしい」との声も多い。給料や労働条件の厳しさを理由に、客の信頼を裏切る行為は許されないとする意見だ。
一方で、現場の厳しい実態を訴える声もある。大手宅配業者で業務委託を受けている男性は「日本郵便の配達員は、一カ所にバイクを停めて複数軒をダッシュで回っている。そこまでしないと配りきれない荷物量なのだろう」と語る。自身は雨の日に封書を袋に入れる余裕があるが、郵便局員には過酷なノルマが課され、ブラックな契約条件が背景にあると指摘する。
元配達員が語る「誇り」と「失望」
40年前に郵便配達員として勤務した経験を持つ男性は「当時は全逓が強く、局内の組織も厳格だった。配達を完遂することが当たり前で、不配や隠匿など考えられなかった」と振り返る。年末繁忙期には高校生アルバイトを雇い、郵便物を捨てたりしないよう細心の注意を払ったという。
「百歩譲って台風や地震などの自然災害で配達できないのなら分かる。しかし任務を放棄した上で隠蔽するとは終わっている。私も遅延はあっても、郵便物を捨てたり隠したりは絶対しなかった」と憤る。
枚方市で逮捕事例も
9月には大阪府枚方市の枚方北郵便局に勤務する21歳の配達員が、郵便物4通を配達せず勝手に開封したとして郵便法違反容疑で逮捕された。局内の抜き打ち検査で、本人のロッカーから開封済みの郵便物が見つかり、事件が発覚した。
警察によると、容疑者は事実を認めており、他にも未配達被害が確認されている。同局の配達エリアでは複数の郵便物が届かない被害が報告されており、余罪があるとみて警察が調べを進めている。
こうした刑事事件化する事例が出ていること自体、制度の信頼性を大きく損なうものだ。
信頼回復への課題
郵便法は、日本国内で手紙やはがきといった郵便物を扱えるのは日本郵便だけと定めている。つまり、利用者にとって郵便事業は唯一無二の存在であり、代替手段は限られている。だからこそ、一度信頼を損なえば、その影響は計り知れない。
利用者の立場からすれば、最も求められるのは透明性だ。非公表とされた事案の存在は、差出人の権利を著しく侵害し、結果として「郵便が届くかどうか分からない」という不安を広げてしまう。
再発防止には、まず幹部層の意識改革が欠かせないとされる。現場の労働環境改善とともに、経営層が透明性を優先し、利用者に対する説明責任を果たすことが急務である。
揺らぐ信頼、求められる改革の道筋
郵便物不配4000通の非公表問題は、単なる一企業の不祥事にとどまらない。郵便事業の独占を担う日本郵便にとって、利用者の信頼は事業の根幹だ。民営化から年月を経ても改善されない体質は、制度そのものへの疑念を招きかねない。
「確実に届く」という当たり前の約束を守るために、同社は透明性と説明責任を徹底し、現場と経営が一体となった改革を進めなければならない。信頼回復への道は険しいが、それを成し遂げられなければ、日本の郵便制度そのものが揺らぐことになるだろう。