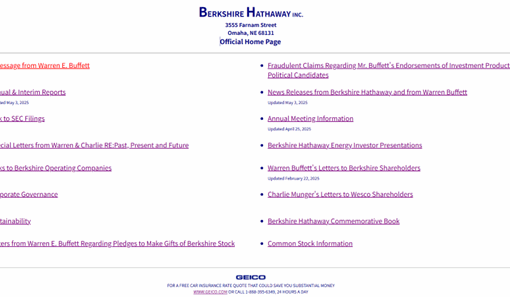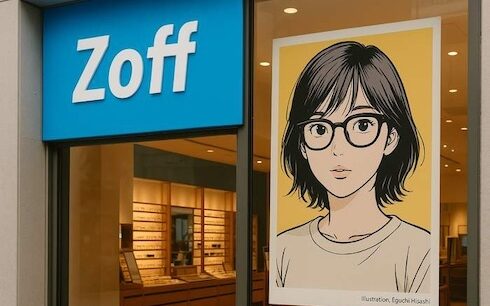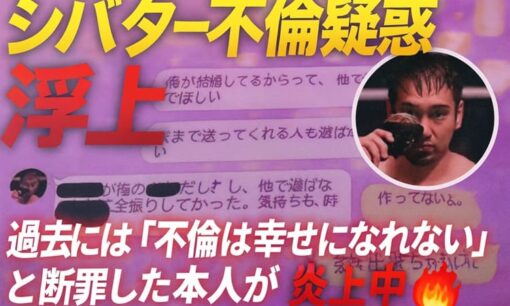企業が社員の奨学金返済を肩代わりする「代理返還」制度の導入が広がっている。2021年度に制度が本格化して以降、導入企業は約1.4倍に増加。人材確保や若手社員の定着策として注目される一方、制度の背景には教育費負担の大きさや奨学金制度の課題も横たわっている。
導入企業、8カ月で約1.4倍に
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)によると、奨学金の「代理返還」制度を導入している企業数は、2024年10月時点で2,587社だったが、2025年6月には3,721社に達し、わずか8カ月で約1.4倍に増加した。
制度は、企業が社員本人に代わってJASSOへ奨学金を返還する仕組みで、2021年度から本格的に運用が開始された。企業が直接JASSOに支払うことで、確実な返還が可能となり、税制上の優遇も受けられる。
企業の人材確保戦略の一環として、特に慢性的な人手不足が続く業界や地方の中小企業での導入が進んでいる。
負担の大きい奨学金返済が背景に
JASSOの調査によれば、4年制大学に通う昼間部の学生のうち、およそ55%が奨学金を利用しており、平均借入額は約310〜313万円。返済は就職後に始まり、月額1万5000円〜2万円を15年近くかけて返すケースが一般的だ。
このような返済負担は、若手社員の生活設計に影響を及ぼすとの指摘がある。代理返還制度は、こうした状況を踏まえ、企業が福利厚生の一環として導入する動きにつながっている。
人材確保と定着への効果も
企業にとっては、代理返還制度を活用することで新卒採用時の訴求力が高まるとされている。また、返還支援を受ける社員の離職率が比較的低い傾向にあるという企業もあり、定着促進の手段としても注目される。
制度の利用者が給与としてその額を受け取るわけではないため、所得税や社会保険料の対象とはならず、企業側も損金として処理できる点が利点とされている。
自治体の支援制度も拡大中
企業による支援に加えて、地方自治体による奨学金返還支援制度も拡大している。JASSOや複数の報道によれば、全国47都道府県と816の市区町村が何らかの形で制度を整備しており、Uターン・Iターン人材の定着促進や特定業種(介護・看護・保育など)の確保を目的とした支援が行われている。
地方の中小企業と連携し、地域ぐるみで若者の就職を後押しするケースも見られる。
給付型奨学金は限定的、情報提供に課題も
JASSOの統計によれば、大学生における給付型奨学金の利用割合は約23%であり、残る77%は貸与型(返済義務あり)となっている。現状では、奨学金=「借金」としての性格が強い。
一部の企業や団体では、学業成績や家庭状況にかかわらず、意欲を基準とする独自の支援制度を導入している例もあるが、情報が分散していることから、必要な学生に届きにくいという課題が指摘されている。
教育費と奨学金制度をめぐる社会的議論
代理返還制度の広がりは、企業や自治体による若者支援策として注目を集めている。一方で、進学にかかる費用の大きさが学生本人や家庭にとって大きな負担となっている現状も浮き彫りになっている。
経済的理由から進学をあきらめたり、進路選択を制限したりする例も報告されており、教育費の負担は、将来の選択肢やキャリア形成にも影響を及ぼしているとされる。
代理返還制度の拡大とともに、公的な教育支援のあり方や、奨学金制度の構造そのものを見直す議論が求められている。