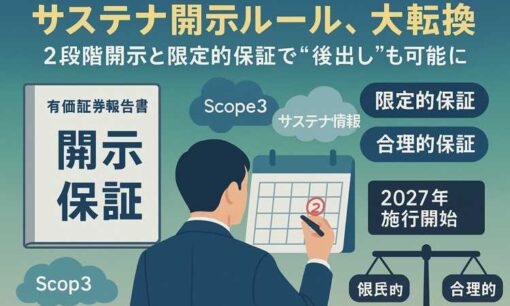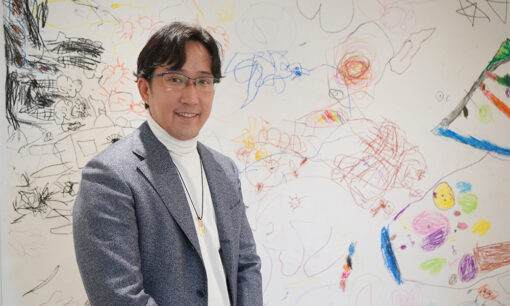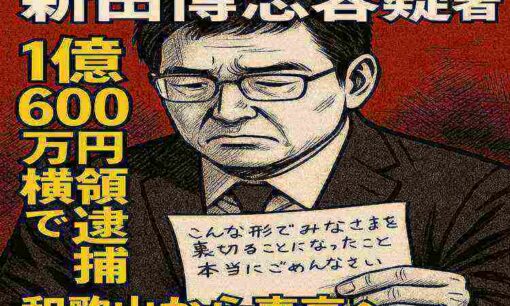金融庁が、上場企業に対して有価証券報告書(有報)への新たな記載義務を導入する方針を固めたことが、7月12日までに明らかになった。今後、企業は毎事業年度ごとに、従業員の給与の増減率を記載し、その方針や人材戦略とともに開示することが求められる見通しだ。
物価高が続くなか、投資家にとって企業の賃上げ水準や賞与の動向は、業績や経営姿勢を評価するうえでの重要な判断材料になりつつある。金融庁は、そうした市場ニーズに対応するとともに、企業に人的資本への投資姿勢を明示させることで、持続的な成長の後押しを狙う。
2026年にも新様式適用 内閣府令の改正へ
今回の措置は、有価証券報告書の様式を定める内閣府令の改正によって実現される予定で、金融庁は今後、有識者会議やパブリックコメントを通じて幅広い意見を募る。早ければ2026年6月、有報を提出する2025年3月期決算の企業から新たな記載が義務化される可能性がある。
今回の制度改正が実現すれば、日本企業の「賃上げ実態」と「人材戦略」が投資家により明瞭に開示される初の制度化となる。
既存の人材情報開示との接続も
現在、有報では従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与に加え、男女の賃金格差、育児休業取得率、管理職における女性比率などが記載されている。今回の改正では、これらの情報に加えて「給与水準の変化」や「その決定方針」についても説明が求められることになる。
また、企業が人材獲得や維持に向けてどのような戦略を講じているか、持続的成長に向けた人材投資の位置づけも開示内容に含まれる。企業の賃金施策が従来以上に経営戦略の一部として問われる時代が到来しつつある。
平均値では見えない「格差」の実態
一方で、平均年収や賃上げ率だけでは、企業内の実態を正確に捉えきれないという懸念もある。たとえば一部の高給幹部や技術職が全体の平均値を押し上げているケースでは、実際の多数派である一般職の昇給幅が小さい可能性もある。
米国などではすでに「給与の中央値」や「CEO報酬との格差倍率(pay ratio)」の開示が義務化されており、開示指標が格差の透明化に寄与している。日本でも賃上げの「質」に注目が集まる中で、今後はこうした実質的な格差把握のための指標導入が議論される可能性がある。
企業・スタートアップの声は割れる
今回の改正に対し、企業現場の反応はさまざまだ。都内のITスタートアップ人事責任者は「人的資本開示が採用ブランディングの一環になるのは歓迎」と前向きに評価する。一方で、別の上場企業のIR担当者は「人材戦略を言語化して開示できる余裕がない企業も多い。大企業基準が中小にも波及すると負担が重い」と語る。
賃上げ率の記載が義務化されることで、見栄えを良くするために変動給や一時金に依存するケースも考えられ、制度の趣旨を損なわない運用ルールの整備も求められる。
グローバル規制の中で問われる“後れ”
人的資本の情報開示は、すでに世界的な潮流となっている。米国では2020年にSEC(証券取引委員会)が人的資本情報の開示を義務化。EUもCSRD(企業持続可能性報告指令)によって、2024年以降段階的に、詳細な人材指標の開示を義務づける方針を打ち出している。
これらと比較すると、日本の制度設計はようやく本格的な「人的資本の数値的開示」の入り口に立った段階ともいえる。金融庁としてもグローバル投資家からの信頼獲得を意識した施策とみられ、特に海外機関投資家にとっては、日本企業の人的資本マネジメントの透明性が大きな関心事項となっている。
人的資本の「質」まで問われる時代へ
単なる平均給与や賃上げ率の数字にとどまらず、その背後にある考え方や説明責任の履行が今後の企業に求められる。今回の制度改正は、開示制度を通じて企業の人材マネジメントの質そのものを問う流れの一環と位置づけられるだろう。
人的資本への適切な投資は、イノベーションや持続的成長の源泉となりうる。金融庁がこの動きを制度面から支援しようとする今回の方針は、資本市場と企業経営をつなぐ新たな試みとして注目される。