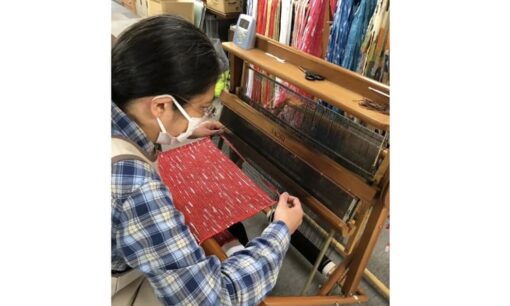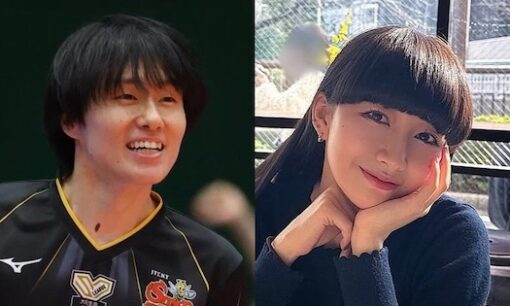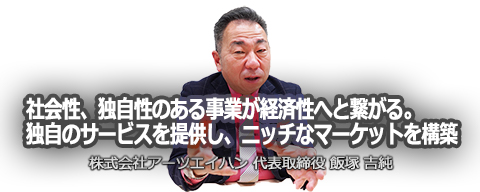書籍と雑貨を縦横無尽に陳列し、手書きPOPがユーモアを交えながら購買意欲を掻き立てる――かつて“サブカルの聖地”とまで称されたヴィレッジヴァンガードが、その象徴的な「場」を大幅に手放す。
2025年7月11日、運営元のヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、全店舗の約3割にあたる81店の閉店を発表した。2025年5月期の決算は、最終赤字42億円(前年は11億円の赤字)と2期連続の赤字。棚卸資産評価損などの特別損失が重く、もはや“ユーモア”だけでは帳尻は合わない。
カルチャーの“箱庭”がコストセンターに
ヴィレッジヴァンガードは1986年、創業者・菊地敬一氏の「自分が客だったらほしいものを置く」という思想を核に名古屋で誕生した。倉庫風の空間にビリヤード台、MGミゼット(小型車)、ジャズ、ブルース。店そのものが編集された“カルチャーの箱庭”だった。
本屋でありながら、むしろ売上の7割以上はCD・雑貨・Tシャツ・食品などの非書籍商品。「サンクチュアリ出版」「幻冬舎」「いろは出版」などマイナー系出版社の書籍が並び、商品へのPOPは時に「まずい!罰ゲーム用!」と毒づく。だが、それが心地よかった。
それがいまや、テナント店舗に同じような商品が並び、どこも「それっぽいだけ」の“ヴィレヴァン風”。本来、地域や店長によって違う“偏り”こそが魅力だったはずが、POS管理による標準化が没個性を加速させた。
「ヴィレヴァンでなくてはならない理由」が消えた時代
ネットで雑貨を買うのは簡単になった。だが、ヴィレヴァンの強みは“空気”だったはずだ。B級カルチャーとBGM、ジャンクと美学、あの棚と棚の隙間に漂う匂い。ポチるだけのECでは、それは再現できない。
それでも会社側は「オンライン強化」で黒字転換(2026年5月期に8億4700万円)を狙うという。だが、ECは“空気”を売れない。なぜ今ヴィレヴァンで買うのか?という根本の問いに答えなければ、残る店舗もいずれ「閉めるための余命」になりかねない。
ヴィレッジヴァンガードは文化のインフラだったのかもしれない
ヴィレヴァンの店舗が街から消えるとはどういうことか。それは、地域にひとつだけある“価値観の自由市場”が失われることだ。吉祥寺や下北沢の店舗で、本と雑貨の棚を“巡礼”した者たちにとって、それは青春の一部だった。
「まずい」お菓子に「まずい」と書く店。「売れない本」こそ仕入れる度胸。洒落と本気のあいだを縫い続けたヴィレヴァンの精神が、数値管理に回収されてしまうのなら、私たちはまたひとつ、面白い国のあり方を手放すのかもしれない。