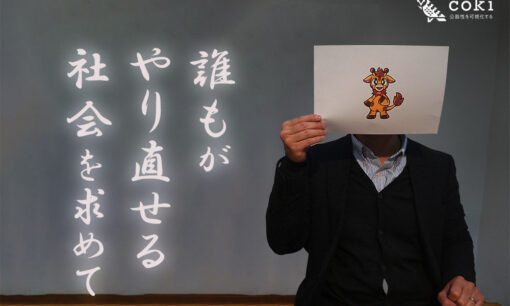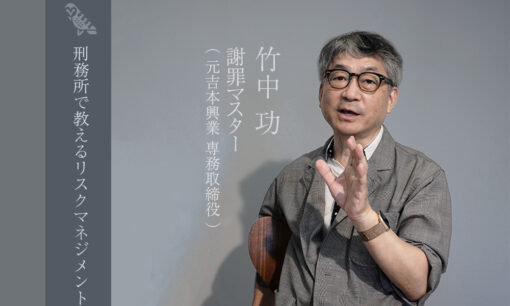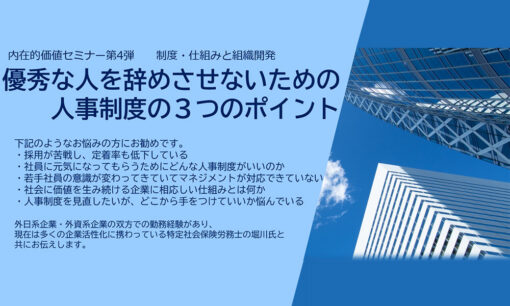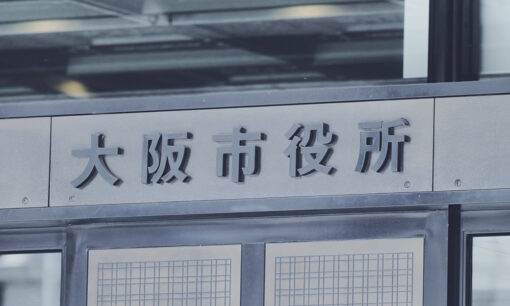一番罪を犯してはいけない人の裏切り

「歌舞伎町の裏社会と闘ってきた男が、今度はその裏社会に堕ちた」
関係者のひとりは、そう語る。
5月18日夕刻、東京・新宿区大久保の路上で、公益社団法人「日本駆け込み寺」事務局長・田中芳秀容疑者(44)が麻薬取締法違反(コカイン所持)容疑で現行犯逮捕された。さらに、同行していた20代女性も薬物使用容疑で逮捕された。彼女は「駆け込み寺」の相談者とみられ、警視庁は田中容疑者が薬物使用を勧めた可能性も視野に入れて捜査を進めている。
財布から発見された小分けの白い粉。本人は「自分で使うためだった」と容疑を認めている。支援の現場で活動してきたはずの男が、支援対象の若者と薬物を共有していた。その構図があまりに痛ましい。
女と薬物を共にした支援者の矛盾 糾弾してきたホストとどちらが害悪か
田中氏はこれまで、ホストクラブにおける「売掛被害」などに対し強い姿勢で臨んできた人物だ。一般社団法人「青少年を守る父母の連絡協議会」(青母連)の代表理事を務める玄秀盛氏の側近として、報道番組や行政の協議会に顔を出し、「ホストと匿名犯罪グループ(トクリュウ)は持ちつ持たれつの関係」「行き場のない少女たちがホスト社会で再生産されている」と実態を訴え続けてきた。
若年女性が抱える多額の借金、風俗への斡旋、そしてホスト依存という負の連鎖を「社会の病理」として訴えてきた人なのだ。
だが、そうした“正義”の言葉は、今回の事件で大きく揺らいだ。
自らが守ろうとしていたはずの相談者とともに薬物を使用していた疑い。ホストを「依存を利用し、若者を搾取する」と非難していた立場の人間が、今や同じ構造に自ら取り込まれていたのではないかという疑念が広がる。
「ホストとどちらが害悪なのか、わからなくなった」とSNSで揶揄される状況は、活動の信頼性そのものを損なう重大な裏切りである。
支援者としての信義を問う声
田中氏はこれまで、支援の現場で数多くの若者と向き合ってきた。歌舞伎町に根を張り、行政と業界の間に立って対話を試みるなど、問題解決に向けた行動を地道に積み重ねてきた存在でもある。
だが、支援活動には倫理が求められる。特に薬物や性に関わる境界線において、その線を越えることは、活動の信頼性を根底から崩す行為だ。被害者と支援者、依存と共犯。その境界が曖昧になったとき、支援という営みは成り立たない。
「誰よりも罪を犯してはならない人間が、罪を犯した」。この重さは、本人にも、団体にも、そして社会全体にも突き刺さる。
それでも、“やり直せる社会”のために
とはいえ、ここで問われるべきは、田中容疑者個人の転落だけではない。むしろ、彼が訴え続けてきた「やり直せる社会」「誰一人見捨てない支援」という理念を、どう持続させていくのかという問いだ。
社会包摂とは、すべての人に再出発の機会を保障することである。今回の事件は、その理念に対する皮肉な逆説であり、同時に再起の意義をより強く照らし出す契機でもある。
田中容疑者が犯した過ちは大きく、決して軽視すべきではない。だが同時に、彼自身がもう一度、自らがかつて立っていた場所に戻り、支援の現場に立ち直ることを願う声もある。
「薬物に染まったから終わり」ではなく、むしろ「そこから立ち上がる姿こそが、支援者としての最後の仕事」だとするならば。田中芳秀という男に、再び支援の意味を証明してもらう日が来ることを待ちたい。