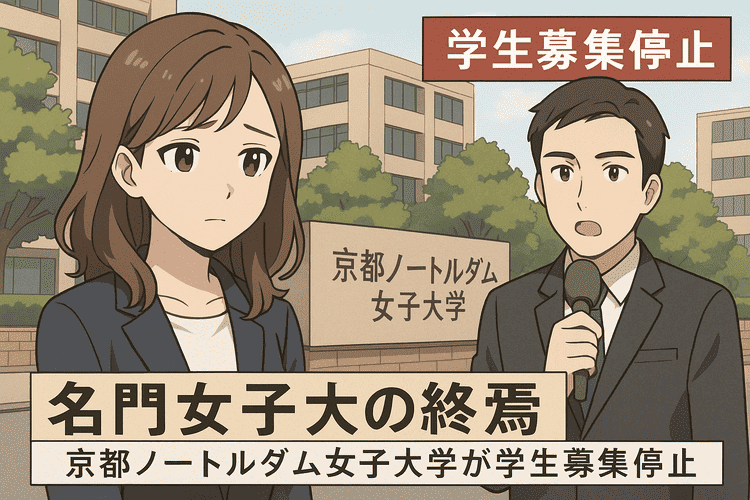
関西の名門女子大学の一角、京都ノートルダム女子大学が2026年度から学生募集を停止する。少子化と進む共学化の影響で、女子大学の存続がいま大きな岐路に立たされている。
「関西女子大御三家」に衝撃──名門大学が学生募集を停止へ
春の柔らかな陽光が差し込む京都市左京区のキャンパス。その静寂を破るように、2025年4月25日、京都ノートルダム女子大学は2026年度以降の学生募集を停止すると発表した。運営する学校法人ノートルダム女学院が同日午前に開いた記者会見で明かされた。
1961年の開学以来、英語教育や人文学を中心に据え、女子の高等教育に尽力してきた同大。京都女子大学、神戸女学院大学と並び「関西女子大御三家」の一つに数えられ、その伝統と格式は多くの卒業生にとって誇りであった。しかし、24年度の入学者数は定員330人に対し186人と、大きく下回った。かつて学生たちで賑わったキャンパスに、今は空席の教室が目立つ。この現実が、大学の未来に静かに終止符を打った。
急速な少子化と価値観の変化──女子大離れが進む背景
今回の決定の背景には、急速に進む少子化と、進学先の選択肢の多様化がある。大学側は「定員割れの常態化が経営に深刻な影響を与えた」と説明。近年では、男女共学の大学を選ぶ傾向が強まり、女子大への志願者は右肩下がりに減少している。
実際、文部科学省の調査によると、女子大学の多くがこの10年間で定員割れに苦しみ、そのうち6校が既に閉学を決定。また、他校との統合や学部再編によって形を変える女子大も後を絶たない。教育の多様性を支えてきた女子大学という存在が、いま大きく揺れている。
新学部設置でも打開できなかった構造的問題
京都ノートルダム女子大学も、近年は時代のニーズに応えようと改革を重ねてきた。2023年に「社会情報課程」(2025年より「社会情報学環」に改称)、2025年には「女子キャリアデザイン学環」を新設するなど、女子のキャリア支援や情報リテラシー育成に力を注いだ。
また、国際言語文化学部を2026年に廃止し、人文学部言語文化学科へと再編するなど、スリム化と専門性の強化を図ったが、入学者数の改善には至らなかった。学生募集停止という決断は、そうした努力の限界を示している。
ネット上でも衝撃と惜別の声──「時代の流れとはいえ寂しい」
SNSでは、「ダム女」の愛称で親しまれた同大学の突然の募集停止に、驚きと悲しみの声が相次いだ。
「学生時代を思い出す。名門が消えるのはやっぱり寂しい」「女子大の存在意義、改めて考えさせられる」──。
一方で、「女子大が時代に合わなくなったのは事実」「選択肢が多い現代では、女子だけの環境に魅力を感じない人も増えている」と冷静に受け止める声もあった。
SNS上の声は賛否が交錯しながらも、女子大学の意義とその存在価値について、多くの人々が関心を寄せていることを浮き彫りにしている。
女子大学の全国的動向と今後の展望
京都ノートルダム女子大学の学生募集停止は、全国の女子大学に共通する現象の一部だ。全国的に女子大学は、少子化とともに厳しい存続問題に直面しており、多くの学校が共学化や学部改革を進める一方で、いくつかは閉学や統合を決定している。これにより、女性教育の場としての女子大学の役割が再定義される必要がある。
東京家政大学や神戸女学院大学など、今も名門として知られる女子大学が多く存在するが、その多くが改革を迫られている。今後、女子大学が生き残るためには、性別にとらわれず、時代に即した教育改革を進めることが求められるだろう。
関西の女子大学は10年で6校減──次に閉じるのはどこか
京都ノートルダム女子大学の閉学により、関西の女子大学はこの10年で6校が姿を消すことになる。少子化による大学全体の競争激化のなかで、女子大はその存在意義を問われ続けている。
各校は生き残りをかけ、共学化や専門分野の転換を進めるが、将来像を描けない大学にとって、閉学はもはや他人事ではない。とりわけ、知名度に依存してきた中小規模の女子大は、ブランドの陳腐化が進み、競争力を失いつつある。
女子大学の未来はあるか──社会と共に再定義される高等教育
教育の多様性と選択肢を確保するうえで、女子大学は一定の役割を果たしてきた。女性が自信を持って学び、将来を描くための環境を提供してきた歴史は、消えてはならない財産である。
だが、時代は確実に変わっている。性別にとらわれず学びを選び、社会に出るという価値観が定着しつつある現代において、女子大学がその存在意義を保ち続けるためには、根本からの変革が求められている。
京都ノートルダム女子大学の決断は、その先陣とも言える。今後、他の女子大や高等教育機関がどのような舵を取るのか──その選択が、未来の教育地図を塗り替えることになるだろう。
















