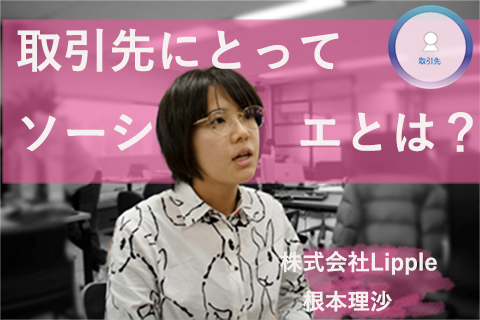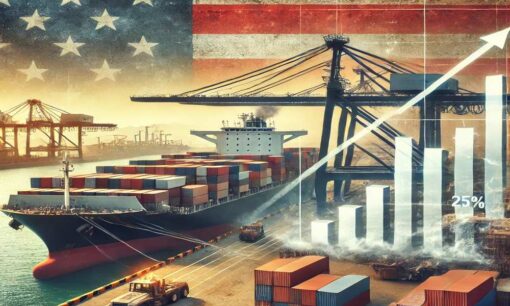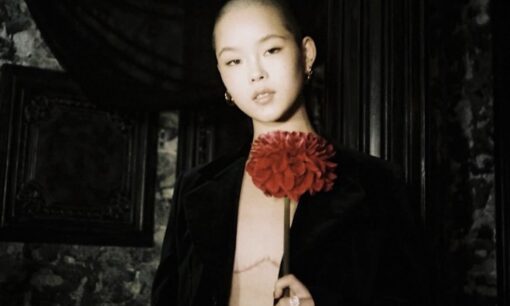精神疾患によって働くことが困難になった人が、障害年金を申請する際、「初診日」の取り扱いが受給の可否を左右する大きなポイントとなる。診断名が変化していても、制度上は同一の病気と見なされ、初診日がさかのぼることで申請が複雑化するケースも少なくない。特に精神疾患ではこの傾向が顕著であり、制度への理解不足が受給の遅れや不支給につながる恐れもある。この記事では、精神疾患による障害年金の請求方法と注意点、そして専門家に依頼する際の実務と費用について解説する。
精神疾患と障害年金――申請のハードルはどこにあるのか
障害年金は、病気やケガにより生活や就労が著しく制限される人に支給される公的年金制度である。しかし、その制度には複雑な要件や運用上の注意点が多く、とくに精神疾患を抱える人の申請には“盲点”となるポイントが潜んでいる。
就労が困難な若年層のひきこもりや精神疾患を抱える当事者の支援を行っている社会保険労務士によれば、障害年金制度の運用には制度上の理解を要する部分が多く、初動の誤りが申請の遅れや不支給につながる恐れがあるという。
初診日がカギとなる制度構造
障害年金の受給には、原則として以下の3つの要件を満たす必要がある。
- 障害の原因となる傷病の初診日が特定できること
- 初診日において一定の保険料納付要件を満たしていること
- 障害認定日において、障害の程度が法定の基準に該当していること
このうち、最も誤解が多いのが「初診日」の扱いである。制度上、初めてその病気やケガで医療機関を受診した日が「初診日」とされ、それを基準に障害認定日や申請時期が定まる。
精神疾患の場合、症状が変遷し診断名が変わることは少なくないが、たとえ名称が変わったとしても、「同一の精神疾患」と見なされれば、初診日は過去にさかのぼって確定される。
このため、初診日に受診した医療機関が現在と異なっていた場合でも、診断名が適応障害からうつ病へと移行したようなケースでは「同一疾病」として扱われる可能性が高い。その際、申請に必要な診断書をその時点で取得できないと、「障害認定日による請求」ができなくなる。
障害年金の請求には2つの方法がある
障害年金の請求方法には、以下の2つのパターンがある。
① 障害認定日による請求
初診日から1年6カ月が経過した「障害認定日」時点での状態に基づき請求する方法。
この場合、障害認定日前後3カ月以内の診断書が必要となる。受診歴がない場合はこの方法は使えない。
② 事後重症による請求
現在の障害状態をもとに請求する方法であり、診断書に記載された「現症日」以降に年金が支給される。
過去にさかのぼって受給することはできないため、申請が遅れるほど、損をする可能性がある。
精神疾患に特有の注意点――見逃されがちな“初診の証明”
制度上、請求には「受診状況等証明書(初診日の証明書)」と「診断書(現在の状態を証明するもの)」が必要となる。初診時の病院が閉院していたり、カルテが破棄されていた場合、証明が困難になる。
特に若年層では、大学時代や学生納付特例の期間に受診していたことが多く、当時の国民年金の納付状況が受給可否を左右する。たとえば、納付猶予が認められていた期間に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たしていると判断される可能性がある。
実際の事例――申請ができなかった理由とは
ある社会保険労務士の支援事例によれば、25歳の女性が大学生の頃に適応障害と診断された後、受診を中断。24歳でうつ病と診断されて再受診したが、制度上は21歳時点の初診が有効とされ、障害認定日時点の診断書が取得できなかったため、障害認定日による請求が不可能となった。最終的に「事後重症」での請求を行い、障害基礎年金2級の受給に至ったという。
障害年金の請求手順(精神疾患の場合)
| 手順 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ① | 初診日の確認 | 原則、医療機関から「受診状況等証明書」を取得 |
| ② | 保険料納付状況の確認 | 初診日の前々月までの1年に3分の2以上の納付または免除 |
| ③ | 診断書の取得 | 精神科医から「障害年金用」の書式で作成 |
| ④ | 申立書・病歴就労状況等申立書の作成 | 本人の状態を時系列で記載 |
| ⑤ | 年金事務所等への提出 | 必要書類をそろえて申請 |
| ⑥ | 結果通知・受給開始 | 審査後、受給可否の通知が届く(通常2〜3カ月) |
専門家に依頼する際のポイントと費用
障害年金の申請は、必要書類の量と制度の複雑さから、家族だけで対応するには限界があるケースも少なくない。初診日の証明が困難な場合や、複数の診断歴がある場合などは、社会保険労務士(社労士)などの専門家に早めに相談することが、結果的に受給につながりやすい。
社会保険労務士(社労士)とは
障害年金の申請代行が法的に認められている国家資格者である。書類作成や初診日の証明取得、診断書依頼書の作成、年金事務所との連絡調整など、申請実務全般を担うことができる。行政書士やファイナンシャルプランナーは、申請代行はできず、相談にとどまる。
費用の相場
| 費用項目 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 着手金 | 0円〜5万円程度 | 無料の事務所も多いが、事前調査などで必要となることもある |
| 成功報酬 | 初回年金受給額の10〜20%程度+消費税 | 原則として、受給が決定した場合のみ発生。不支給の場合は発生しない |
| 実費 | 数千円〜(診断書料・交通費等) | 医療機関への支払いは別途本人負担 |
たとえば、初回に2年分の障害基礎年金(約160万円)が一括で支給された場合、成功報酬が15%であれば24万円+消費税が報酬額となる。これ以降の年金は全額本人に支給される。
多くの社労士事務所では初回相談を無料で実施している。地方自治体や障害者支援センターなどで行われている「障害年金無料相談会」を利用するのも有効な手段である。
現場の支援者は「制度を知らないことで、本来受け取れるはずの年金を受けられない人もいる。早い段階からの情報収集と、必要に応じた専門家の関与がカギになる」と指摘している。