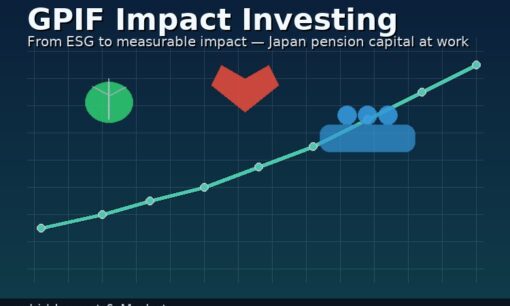2024年度、介護事業者の倒産が過去最多の179件に達し、現場の深刻な疲弊が浮き彫りとなった。特に小規模事業者が淘汰される傾向が強まり、地域の介護基盤が揺らいでいる。にもかかわらず、介護サービスへの利用者の期待はむしろ高まり続けている。介護現場が直面する構造的課題と、今後の生き残り策、そして利用者が求めるサービス像を探った。
介護倒産が過去最多 小規模事業者に集中
東京商工リサーチが2024年度に実施した調査によれば、老人福祉・介護事業の倒産件数は前年比36.6%増の179件に達し、過去最多を記録した。とくに「訪問介護」が全体の約半数(86件)を占め、「通所・短期入所」(55件)や「有料老人ホーム」(17件)も軒並み高水準で推移した。
倒産理由の大半は「売上不振」(133件)で、「既往のシワ寄せ」(15件)、「事業上の失敗」(15件)も顕著に増加している。資本金1000万円未満の零細事業者が87.7%を占め、従業員10人未満の構成も83.2%と、規模の小ささが事業継続の壁となっている実態が浮き彫りとなった。
利用者が介護サービスに求めるもの
介護サービスの利用者やその家族は、単なる“介助”を超えた安心感や信頼性を求めている。厚生労働省の調査でも、「担当職員が長く続けてくれる」「個別対応ができる」「柔軟にサービスを調整できる」といった点が重視されており、介護事業者には経営の持続性と質の両立が求められている。
介護にかかる費用と制度の仕組み
介護保険制度の下では、利用者は原則1割(一定所得以上は2〜3割)の自己負担でサービスを受けられる。しかし、施設入所や特別なサービス加算がある場合は、月額で数万円から十数万円の費用がかかることもある。世帯の収入や要介護度によって負担額は大きく変動するため、事前の制度理解と見積もりが不可欠である。
小規模介護事業者が生き残るために必要な5つの柱
介護ニーズが高まる一方で、事業者側の体力が問われている。とくに小規模事業者が持続可能な経営を行うには、次の5つの方向性に沿った具体的な対策が不可欠である。
小規模介護事業者が生き残るための5つの柱
| 対策の方向性(何をするか) | 実施の具体策(どうするか) | 目的・効果(なぜ必要か) | その他(補足・活用策など) |
|---|---|---|---|
| 経営の複線化と地域密着 | サービスの多角化 | リスク分散と収益の安定化を図る | 地域包括ケアに合致した事業展開が鍵 |
| 地域との関係深化 | 顧客との信頼関係を構築し、継続利用を促進 | 顔の見える関係がサービス評価にも直結 | |
| 財務管理と補助金最適化 | 資金繰りの見直し | 経営の安定と倒産リスクの回避 | 専門家(診断士・社労士等)の支援が有効 |
| 補助金・加算の活用 | 財政基盤の強化と制度の最大活用 | 介護報酬加算、ICT補助金の積極活用を | |
| 人材確保と定着 | 柔軟な雇用制度 | 働きやすい環境で人材流出を防ぐ | 若年層や家庭持ち人材の採用にも効果的 |
| 教育・育成体制 | 技術の均質化と職員の定着促進 | 資格支援や外部研修で専門性を強化 | |
| デジタル化と効率化 | ICTの導入 | 業務の省力化とミス削減で生産性向上 | ICT導入補助制度の活用が鍵 |
| 情報共有の強化 | 業務の見える化とチーム連携の強化 | クラウド化で連絡・記録・管理を一元化 | |
| 保険外サービスと共助展開 | 自費サービスの開拓 | 新たな収益源の確保と差別化 | 家事代行や見守りサービスの提供が有効 |
| 地域連携と共助 | 地域資源を活かし人材不足を補完 | ボランティア・学生・シルバー人材との協働 |
今後の展望 介護は「社会の責任」として問われる
介護事業の持続は、もはや一事業者の努力だけで賄えるものではない。処遇改善やICT補助といった国の支援の充実は不可欠であり、加えて自治体や地域全体が一体となって介護を支える体制づくりが求められる。
事業者の経営努力と制度の後押し、そして地域住民との共助の融合がなければ、「介護難民」が生まれる危険性は高まる。介護は一人ひとりの人生に直結する問題であり、社会全体が「支える介護」に責任を持たなければならない。