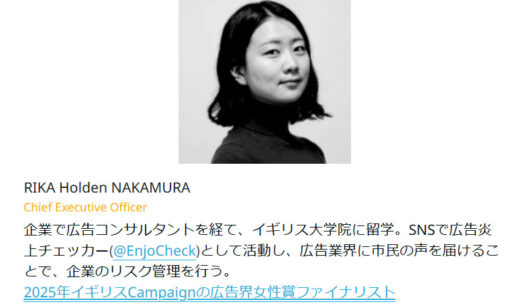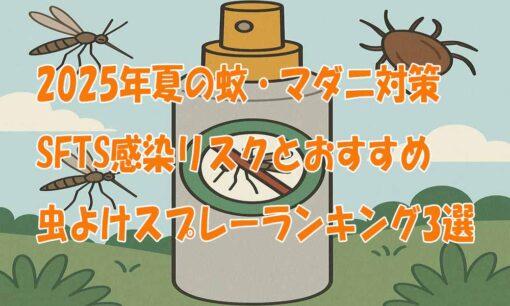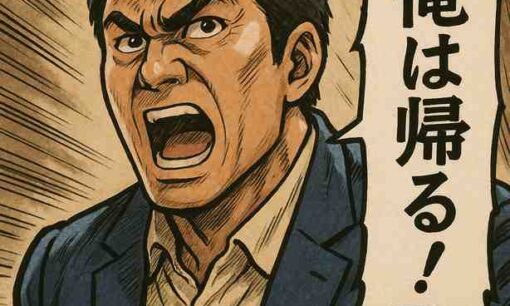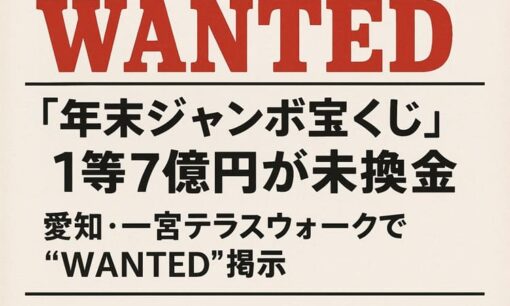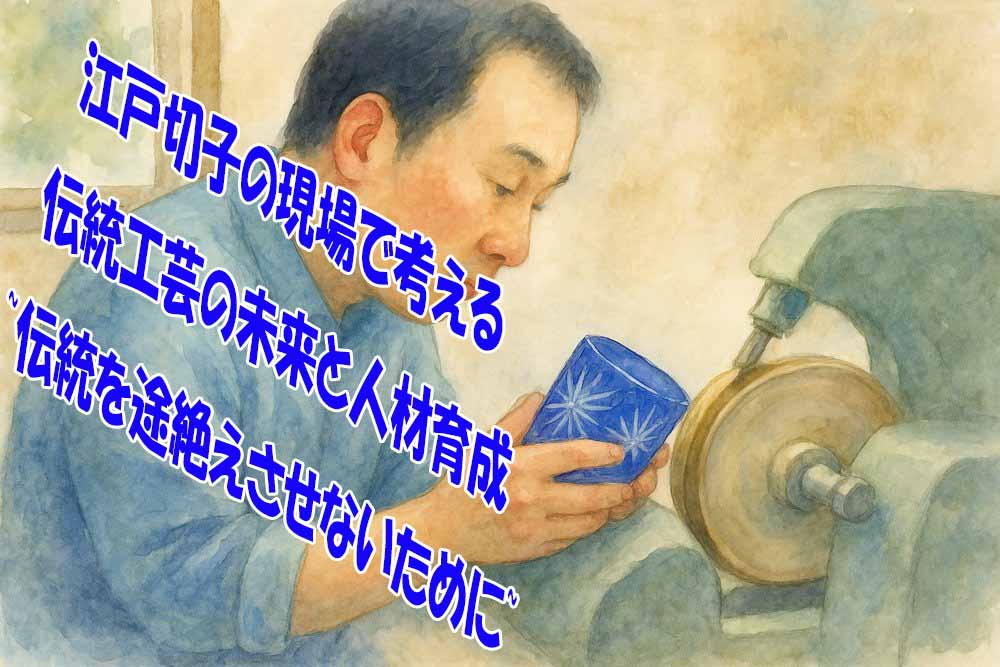
色ガラスに繊細な文様を刻み、光を受けてきらめく江戸切子。東京都墨田区にある「すみだ江戸切子館」では、その美しさだけでなく、職人の手仕事に直接触れることができる体験型の工房が開かれている。だが、こうした伝統の技も今、後継者不足と担い手の高齢化という大きな壁に直面している。体験の場を通じて伝統をどう守り、いかに次世代へつなぐか――その問いに対する一つの答えが、この小さな工房にある。
ガラスに刻む、日本の伝統技術
東京都墨田区。錦糸町駅から徒歩7分、蔵前橋通り沿いに位置する「すみだ江戸切子館」は、江戸時代から続く伝統工芸「江戸切子」の魅力を体感できる貴重な拠点である。館内では、煌びやかな切子グラスが並び、熟練の職人がダイヤモンドホイールを操る様子を間近に見ることができる。
江戸切子は、江戸時代後期の文政年間(19世紀初頭)に始まったとされるガラス細工である。西洋からもたらされたガラスに日本独自の文様美を刻み込んだこの技法は、やがて東京の地場産業として根づき、今日まで継承されてきた。
この館の特徴は、展示や販売にとどまらず、実際に「削る」工程を来訪者が体験できる点にある。職人の手ほどきを受けながら、自らの手で文様を刻む体験は、伝統工芸の奥深さと難しさ、そして完成の喜びを身体で味わえる稀有な機会だ。
減少する職人と「後継者不在」の壁
しかし、この美しい工芸の裏には、静かに進行する危機がある。
江戸切子の職人の高齢化と後継者不足は、ここ数年でますます深刻化している。伝統的工芸品産業振興協会の2024年の調査によれば、江戸切子の技術者の多くが60代以上であり、20代、30代の職人の数は全体の一割にも満たない。
切子の技術は一朝一夕には習得できない。文様を描く「割り出し」、粗削りから仕上げに至る多段階の加工、薬品を使わずに手磨きで仕上げるこだわり――いずれも高度な集中力と経験が求められる。習得までに10年以上を要するとも言われるこの職人技に、若年層がなかなか飛び込めない現実がある。
課題解決の鍵は「開かれた工房」と体験教育
こうした中、「すみだ江戸切子館」が担う役割は大きい。来訪者が体験を通じて技術の一端に触れ、工芸の世界に関心を持つきっかけとなる場を提供することで、潜在的な後継者や支援者のすそ野を広げている。
同館では、10年以上前から小学生高学年や中学生の職場体験、アート系専門学校との連携講座、地域イベントでの出張ワークショップなどを実施。さらに2023年からは、オンライン配信で職人の作業風景をライブ配信し、国内外に技術の魅力を発信する取り組みも始めた。
「最初は体験でいいんです。一度、ガラスに線を刻んでみて、そこから興味が芽生えたら、それが最初の一歩になる」。館長の川井更造氏はそう語る。
「使う伝統」から「続ける伝統」へ
さらに注目されるのは、江戸切子の“生活への応用”である。かつては酒器や食器が主流だったが、現在は照明器具や扉ガラス、店舗サインといった空間デザインにも用いられ、日常の中で「見る・触れる伝統工芸」へと進化しつつある。
観光施設「東京ソラマチ」や、日本橋の複合商業施設「コレド室町」などでも、江戸切子の装飾が随所に見られるようになった。伝統技術を現代のデザインと融合させることは、需要の拡大とともに若手作家の表現の場を増やす可能性を秘めている。
墨田区では、区を挙げてのクラフトツーリズム推進策も進行中であり、将来的には「すみだモノづくり回廊」として、江戸切子を含む伝統工芸全体を巡る体験型観光ルートの整備が検討されている。
継ぐ者がいて、続く文化がある
体験の終わりに、グラスの底に自ら刻んだ模様をのぞき込み、笑顔を浮かべる来館者たち。ガラス越しの文様の煌めきは、一つとして同じ形をしていない。
「すみだ江戸切子館」は、単なる観光施設ではない。ここで刻まれるのは、ガラスだけでなく、技を知る心、文化をつなぐ意志そのものである。伝統は、伝える者がいてこそ続く。そしてその第一歩は、誰かが「体験」するところから始まる。