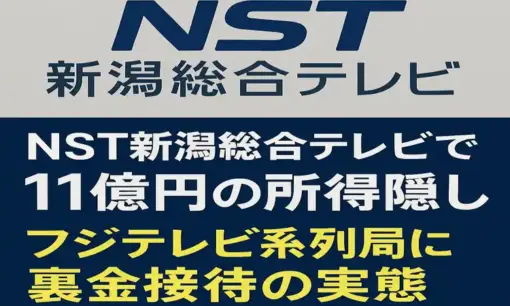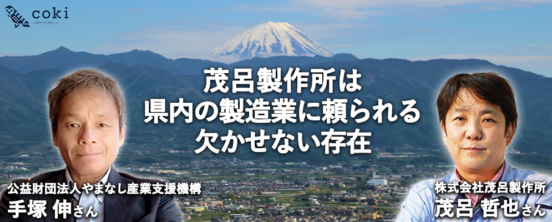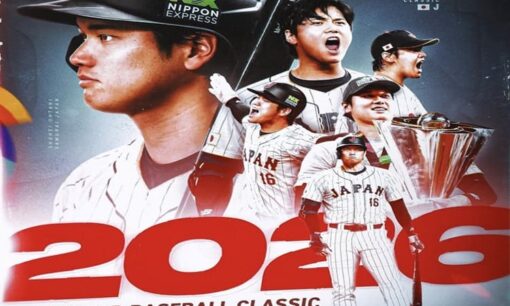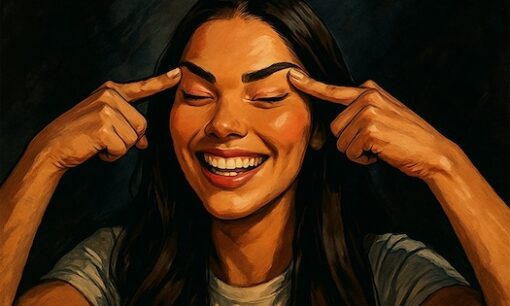専門学校29校、学生約7,000人が参加する一大イベント「NSGカレッジリーグ大運動会2025」において、SDGsをテーマにした新たな取り組みが実現した。きっかけとなったのは、国際こども・福祉カレッジに在学する1人の学生の「ペットボトルキャップを集めてワクチンを届けたい」という思いだった。
福祉を学ぶ学生の“ひと声”から始まった連鎖
2025年6月25日、デンカビッグスワンスタジアムで開催されたNSGカレッジリーグの大運動会では、例年の競技種目に加え、SDGsに基づく新競技「スポーツごみ拾い」が導入された。これは、国際こども・福祉カレッジの学生が教室内で始めたペットボトルキャップ回収運動が、やがてNSGグループ全体に広がった結果である。

同競技は、8チームから計80人の学生が45分間でスタジアム内の清掃活動を行い、ごみの重さとキャップの回収数を競うというもの。広い観客席エリアもフィールドに含めた競技は、スポーツの要素と社会貢献を融合させた斬新な試みとなった。
SDGs実践としての意義 回収から“洗浄・提供”まで
イベント終了後、集められた約1,600個のペットボトルキャップは、国際こども・福祉カレッジに持ち帰られ、学生の手で1つずつ丁寧に洗浄された。その後、ワクチン製造支援を行う業者へと引き渡される予定だという。「拾って終わり」ではなく、「衛生管理の上で届ける」という一貫した行動の中に、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」への具体的な貢献が見て取れる。
参加した学生からは、「楽しくSDGsに取り組めた」「一人では難しいことも、大人数なら実現できると実感した」といった声が寄せられ、学びと行動が結びついた経験となった。
学びと社会課題解決をつなぐ「行動する教育」
SDGs(持続可能な開発目標)は、2015年に国連で採択された17の目標で構成されており、環境・福祉・教育・貧困など多様な課題に向けた国際的な取り組みを求めている。今回のNSG大運動会における「スポーツごみ拾い」は、そうしたSDGsの理念を教育現場に実装する好例といえる。
NSGグループでは、単なる知識の習得にとどまらず、学生自身の声を起点に社会を動かす「行動する教育」を掲げている。今回のような取り組みは、教育と地域社会、そしてグローバルな課題解決をつなぐ架け橋となっている。
「声が社会を動かす」 気づきから始まる実践
「自分一人の声がここまで広がるとは思わなかった」。発案者である学生の言葉は、社会を動かす原点が“気づきと行動”にあることを物語っている。専門学校29校・約7,000人を巻き込むまでに至ったこのSDGs活動は、発信力と連携力の重要性、そして自らの学びを社会実装するプロセスの価値を示している。
国際こども・福祉カレッジでは、今後も学生の気づきを育て、社会変革の芽を支える教育を展開していく構えだ。