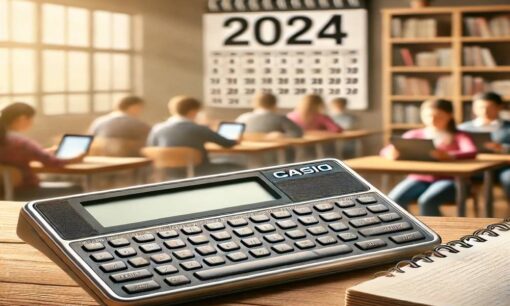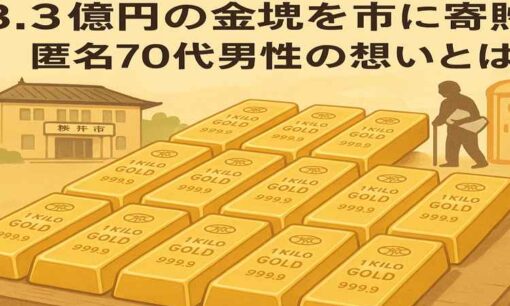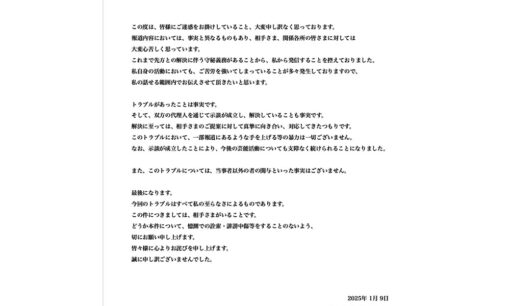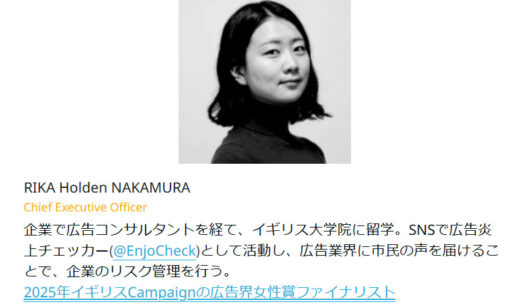高級ダウンブランドとして知られるカナダグースが、いま日本で“環境”を軸にした新たな挑戦を始めている。舞台は千葉県匝瑳(そうさ)市の農地。そこに広がるのは、農作物と太陽光パネルが共存する「ソーラーシェアリング」の風景だ。ブランドの枠を超え、地域と共に未来のエネルギーを考える姿勢は、ファッション産業が直面する課題と希望を映し出している。
カナダグースが千葉・匝瑳で進めるソーラーシェアリングとは
カナダグースは2022年9月、匝瑳市に「カナダグース ソーラーパワープラント」を設立した。市民エネルギーちばが運営する太陽光発電事業に出資し、農地の上にパネルを設置する「ソーラーシェアリング」へ参画したのだ。
この取り組みを「ブランドの責任」と語るのは、カナダグースジャパンの平井洋司社長だ。パンデミック下でファッション産業の環境負荷があらためて注目され、「自分たちがいかに情報不足であったかを痛感した」と振り返る。
その後、エシカル消費の第一人者である市民エネルギーちば代表・東光弘氏と出会い、匝瑳の現場を視察。葉脈になぞらえた「水脈」の発想に触れ、健康な土地が災害にも強いことを知ったことが出資の決め手になった。平井社長は「再エネは競争ではなく協業。学んだことをオープンに共有し、銀座からも現場の知恵を届けたい」と語る。
パタゴニアが先駆けた再生可能エネルギー投資と匝瑳モデル
匝瑳市でのソーラーシェアリングと聞けば、先駆者はパタゴニアである。同社は2017年から市内で約360kW規模の設備に投資。パネル下で育てた大豆を商品化し、食とエネルギーを結びつけるユニークな取り組みを行っている。
さらに兵庫・豊岡市など複数拠点にも出資し、関東・関西の直営店の電力を再生可能エネルギーでまかなう体制を築いた。国内スコープ1・2の排出量を前年比約60%削減し、2030年までに2017年比で55%削減を目指す。
篠健司・パタゴニア日本支社マネージャーは「長く使える製品づくりと再エネ投資でCO2削減を進めている」と説明。メガソーラーによる森林破壊や災害リスクを指摘しながら、「公正で地域と共生する形で再エネを広げたい」と語った。カナダグースもまた、この匝瑳モデルから大きな示唆を得ている。
ファッション業界と音楽業界が語る気候変動への危機感
銀座の「ソーラーシェアリングサロン」には、ファッション業界の若手リーダーや文化人も登壇した。ユニステップス共同代表の鎌田安里紗氏は、川上から川下までを見渡した視点から「工場は広く暑く、冷却には多くのエネルギーが必要。労働者自身も気候変動の影響を受けている」と訴えた。
また、ロックミュージシャンで「THE SOLAR BUDOKAN」を主宰する佐藤タイジ氏は「音楽は電気なくして成り立たない」と強調。東日本大震災をきっかけに再エネを選び、2012年には武道館で100%再生可能エネルギーによるロックフェスを実現した経験を語った。
ファッションと音楽という異なる業界から発せられる声は共通していた。「気候変動は遠い問題ではなく、私たちの現場そのものに影響している」という実感である。
カナダグースの循環型ビジネス「ジェネレーションズ」と政策背景
サロンの最後に発表されたのは、カナダグースの循環型ビジネス「ジェネレーションズ」の日本展開だ。製品を下取りし、認定中古として再販売する仕組みで、最終的にはダウン材の再利用まで視野に入れる。
平井社長は「フルプライスでの購入が難しい人にも製品を届けたい」と語る。9月から下取り、11月から販売開始を予定しており、資源の循環をビジネスに組み込む姿勢は環境負荷の軽減に直結する。
背景には、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」や「2030年温室効果ガス46%削減」の政策目標がある。森林伐採を伴うメガソーラーの弊害も問題視される中、農地と共生する匝瑳のソーラーシェアリングは、政策目標に沿った“現場発”の解決策といえる。パタゴニアやカナダグースの事例は、脱炭素を目指す企業事例の一つとして国内外から注目されている。
銀座から広がる再エネの学び 都市と農村をつなぐ挑戦
イベントの締めくくりには、参加者がソーラーパネル下で収穫された麦を使ったクラフトビールや枝豆を味わい、農業と電力の「地産地消」を体感した。ケータリングはサステナブルな食を提案する「ラベジ(LAVEG)」が担当し、持続可能な食とエネルギーの結びつきも示された。
銀座という都市空間と、匝瑳という農村をつなぐ「学びの場」。そこにはファッション企業が果たしうる新しい社会的役割が浮かび上がる。
まとめ ― ファッションと再エネが示す新しい当たり前
カナダグースの挑戦は、単なるCSRではなく、ファッションと再エネという異なる領域を融合させる社会実験だ。「私たちは自然の一部」という理念を軸に、都市と農村を結び、循環型社会を築こうとする姿勢は、気候危機時代における企業の新しい役割を示している。
匝瑳で芽吹いたソーラーシェアリングの取り組みは、銀座を経由し、さらに広く社会へ。これからの「新しい当たり前」をつくる一歩として注目されるだろう。