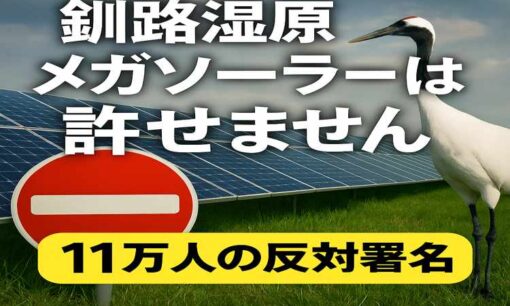2025年7月22日、環境省は石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)に基づき、独立行政法人環境再生保全機構から申請のあった医療費補助や特別遺族弔慰金に関する101件について、医学的判定を実施したと発表した。今回の審査は、7月10日までに4回開催された石綿健康被害判定小委員会での書面審議を経て行われた。
対象となったのは、医療費等の申請75件、特別遺族弔慰金等の請求26件の合計101件。うち医療費等の申請では46件が「石綿吸入による指定疾病にかかった」と認定された。内訳は中皮腫37件、肺がん5件、びまん性胸膜肥厚4件。非該当とされたのは9件、判定が保留されたものは20件にのぼった。
一方、特別遺族弔慰金等の請求に関する26件では、今回の判定で該当とされたものはなかった。さらに、いわゆる「未申請死亡者」に係る26件の審査も行われ、12件が該当、4件が非該当、10件が保留となった。
こうした結果は、救済制度の一端を明らかにする一方で、制度そのものの限界と課題を浮き彫りにしている。
制度の限界と法改正論議 問われる「予防原則」の軽視
今回の結果から明らかになったのは、「判定保留」とされた件数の多さである。特に医療費等の申請75件のうち20件が「判断不能」とされ、特別遺族弔慰金や未申請死亡者に関する判定でも合わせて20件以上が保留となっている。
石綿健康被害の特徴として、曝露から発症まで数十年を要するため、被害者の多くがすでに死亡していたり、当時の就労記録や医療記録が不十分な場合が少なくない。制度上、石綿吸入の証明や、指定疾病との因果関係を明示する資料の提出が求められるが、こうした条件を満たすことは決して容易ではない。
申請者側に課せられる立証責任が大きすぎるとして、被害者支援団体や研究者の間では「予防原則に基づいた制度改正」を求める声が強まっている。具体的には、死亡診断書に「中皮腫」や「石綿肺」等の記載がある場合には、医学的判定を経ずとも原則自動的に認定される仕組みや、就労履歴などから曝露リスクが推定される場合に一定の「推定認定」を可能とする枠組みが提案されている。
しかし、環境省は現時点で「現行法に則った適正な運用を行っている」との立場を崩していない。制度の硬直性が被害者や遺族の申請意欲を削ぎ、実質的な“門前払い”となっているケースも散見される。
制度設計においては、リスクの大小や資料の有無ではなく、「救済の必要性」そのものに基づいた柔軟な対応が求められている。
石綿訴訟との“ねじれ” 司法判断と行政認定の乖離
注目すべきは、司法判断とのズレである。近年、建設アスベスト訴訟をはじめ、複数の石綿関連訴訟において、最高裁や高裁は「国や企業に明確な責任がある」とする判断を下している。
2021年には、最高裁が建設作業員の被害に対して国と建材メーカーの賠償責任を認定し、2023年にも大阪高裁が元従業員の肺がんを石綿曝露によるものと判断し遺族に賠償を命じた。こうした判例は、被害の全体像を司法が広くとらえ、社会的背景や職場環境も含めて評価していることを示している。
一方で、石綿救済法に基づく行政認定では、こうした包括的な判断が難しい。審査は非公開で行われ、審議内容や理由の詳細な説明もほとんどない。結果として、**「裁判では救済されるが、制度では救済されない」**という矛盾が生じている。
この“ねじれ”は、遺族や支援団体にとって深刻な不信の温床となっている。とりわけ、制度による救済を断念した者が訴訟に踏み切り、結果的に司法で認定されるという事例は、制度の信頼性そのものを揺るがす。
今後、行政救済と司法判断の整合性をいかに確保していくかが、制度の持続可能性を左右する鍵となる。
形骸化する「救済」の名のもとに
石綿健康被害の救済制度は、2006年の制度創設以来、累計3万件超の判定を積み重ねてきた。しかし、申請者の高齢化、資料の不足、制度運用の硬直化により、「救済」という名のもとに、真に救われるべき人々が制度から零れ落ちている。
「過去を証明できなければ救えない」という姿勢を改め、「今ある証拠から最大限の判断を導き出す」という方向への転換が急務である。制度の再設計に向けた政治的・社会的議論が、本格化することが期待される。