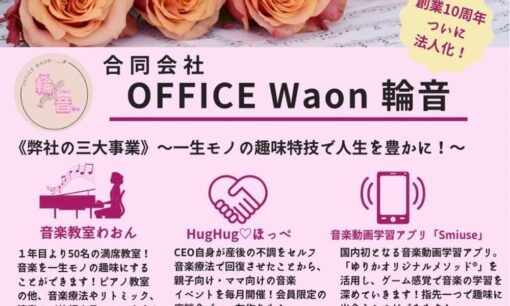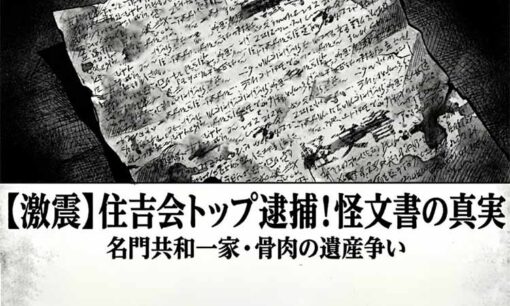ダイバーシティの実効性を問う:1.7万人の日本人正社員を調査

企業の多様性(ダイバーシティ)施策は、実際に社員の満足感向上につながるのか──この問いに、学術的な裏付けを与える調査結果がまとまった。一橋大学のGherghel Claudia氏が2025年3月末に発表したリクルートワークス研究所のディスカッションペーパー「職場におけるダイバーシティ風土と職務満足感の関連」は、日本の正社員約1万7千人を対象に、職場における多様性尊重の風土と職務満足感との因果関係を縦断的に分析している。
「多様な人材が活躍できる風土」が満足感を押し上げる
本研究は、リクルートワークス研究所が実施する「全国就業実態パネル調査(JPSED)」の2023年・2024年データをもとに構築されたものだ。特に注目すべきは、単なる多様性の「量」ではなく、多様性が尊重される「風土」に焦点を当てた点にある。
分析の結果、職場におけるダイバーシティ風土は翌年の職務満足感に有意な正の影響を及ぼしていることが示された。また、職務満足感が翌年のダイバーシティ風土評価にも影響を与えていることから、両者が双方向的に関連し合っている実態も浮き彫りとなった。
「協働」がカギ:チームワークが多い職場で効果が増幅
さらに重要な示唆として、社員同士の「協働」の必要性が高い職場ほど、ダイバーシティ風土が職務満足感に与えるポジティブな影響が強まる傾向が明らかとなった。業務で頻繁に他者と連携する職場では、異なるバックグラウンドをもつ同僚との接触機会が増え、多様性の価値が実感されやすいためと考えられる。
一方で、協働の必要性が低い職場では、多様な人材の存在や価値を十分に認識する機会が限られ、ダイバーシティ施策の効果も表れにくいという。
Gherghel氏はこの点を踏まえ、部署を超えたプロジェクト導入やメンタリング制度、社内交流イベントの実施などを通じて、協働の機会を意図的に設けることの意義を強調している。
「満足感の高い社員ほど職場を肯定的に見る」 ハロー効果も明らかに
研究では、満足感が高い社員ほど、自身の職場のダイバーシティ風土を肯定的に評価する傾向があることも判明した。これは、職務満足感が職場環境全体への評価に影響を与える「ハロー効果」や、感情の伝染による文化形成の影響を示すものである。
また、社員が多様な属性を「自分ごと」として認識する傾向もあり、自らが満足して働けていることで、職場のダイバーシティ環境を高く評価するというプロセスも推察される。
今後の展望と日本企業への提言
本研究は、日本におけるダイバーシティ研究において、対象者数の大きさや分析手法の妥当性から見ても、画期的な知見をもたらしている。一方で、主観的評価に基づく限界や因果関係の厳密な特定の難しさ、国際比較の必要性など、今後の課題も多く指摘されている。
それでもなお、企業がダイバーシティ施策を推進する際には、単に多様な人材を受け入れるだけでなく、協働を促す仕組みを通じて、その価値を活かす風土を育むことが求められる。
調査レポートを読む意義──実務にも活かせる知見が満載
本研究は、多様性推進の必要性が叫ばれるなかで、企業経営者や人事担当者に対し、単なる「多様な採用」ではなく、「多様性が尊重され、活かされる風土」づくりの重要性を再認識させる内容となっている。
ダイバーシティが本当に職場を良くするのか──その答えに近づくための一歩として、本ディスカッションペーパーを一読する意義は大きい。