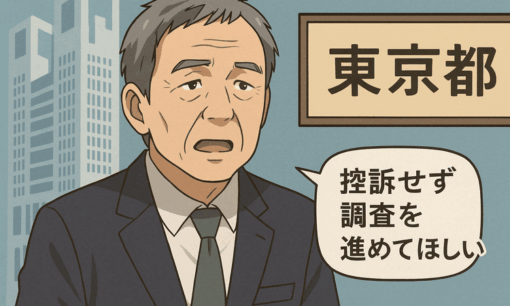スズキは12月27日、鈴木修相談役が12月25日に悪性リンパ腫のため94歳で死去したと発表した。鈴木氏は1978年に社長に就任、2015年に社長職を長男・俊宏氏に譲るまで、37年間にわたりスズキの舵取りを担った。
その辣腕ぶりと愛嬌のある様子から「中小企業のおやじ」と呼ばれ、軽自動車というニッチ市場でスズキを世界的企業に押し上げた立役者として知られる。
軽自動車へのこだわりと世界戦略
鈴木氏はもともと創業家の人間ではない。旧姓は松田という。中央大学卒業後、銀行勤務を経て、1958年にスズキに入社しているが、入社の経緯が面白い。スズキの2代目社長だった鈴木俊三氏が、東海銀行の頭取に、自分の娘の再婚相手を探してくれるよう依頼して、知人の中央相互銀行の頭取が同行の社員だった松田氏へ打診して受け入れたのが経緯だという。
これは、スズキ創業家特有の婿養子による経営継承の一環であった。2代目社長・鈴木俊三氏の娘婿としてスズキ一族に加わった鈴木氏は、常務、専務を経て社長に就任。低価格の軽自動車「アルト」や、ワンボックスカータイプの軽自動車「ワゴンR」など、数々のヒット商品を世に送り出した。誰もが気軽に所有できる軽自動車というコンセプトは、その後のスズキの成長を支える大きな柱となった。
また、鈴木氏は海外展開にも積極的だった。特にインド市場では、同国政府の国民車構想のパートナーに選ばれ、現在ではインド市場でトップシェアを誇るまでに成長。スズキのグローバル戦略を成功に導いた。
スズキのサステナビリティ
スズキのサステナビリティへの取り組みは、「小・少・軽・短・美」という同社の哲学と深く結びついている。必要最小限の資源で製品を作るというこの考え方は、環境負荷を抑えるというカーボンニュートラル社会の要請と合致する。スズキは軽自動車、グローバルではコンパクトカーを得意としており、その軽量化、効率化はCO2排出量削減に大きく貢献している。
さらに、スズキはインドでバイオガス事業を展開。牛糞を活用したバイオガス燃料の精製と有機肥料の生産を通じて、農村部の所得向上と環境問題解決の両立を目指している。これは、単なる自動車メーカーとしてではなく、「生活に密着したインフラ企業」を目指すスズキの理念を体現する取り組みと言えるだろう。
婿養子経営というスズキの系譜
スズキは1909年10月の創業以来、婿養子による経営継承を繰り返してきた企業である。創業者の鈴木道雄氏は、娘婿である鈴木俊三氏を2代目社長に指名。その後も、鈴木実治郎氏、鈴木修氏と、婿養子たちがスズキの経営を担ってきた。鈴木修氏自身も、2代目社長の娘婿という立場であった。
長寿企業には時々見られる、血縁にこだわらない経営スタイルだ。実は長寿企業では、この婿養子が継いでいくスタイルをとる企業が少なくない。自分の息子が不出来だったら、経営には携わらせず、財団や美術館の館長にでもさせといて、優秀な婿養子をとってでも家を承継させていくという、この価値観は日本独特のものであり、これが日本が世界に冠たる長寿企業大国になった要因の一つとなっている。
2015年、鈴木氏は社長職を長男の俊宏氏に譲り、会長に就任。トヨタ自動車との資本提携など、経営の第一線から退いた後も影響力を持ち続けた。2021年に会長を退任後も、財界のみならず、政治、文化など多方面で活躍。静岡県に本社と全工場を置くなど、地元への貢献も惜しまなかった。
鈴木氏の死去は、スズキのみならず、日本経済界にとって大きな損失と言える。その功績と哲学は、100年企業となった今後のスズキの経営、ひいては日本経済の発展に、長く影響を与え続けるだろう。