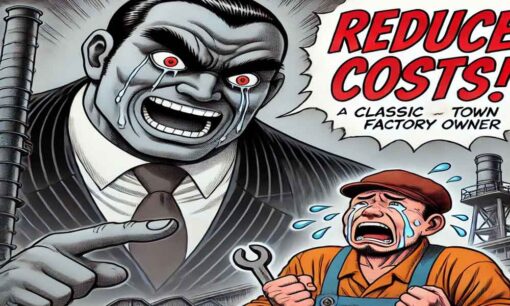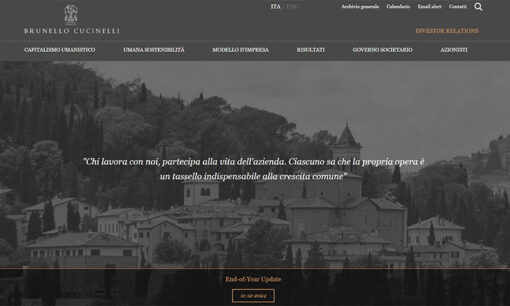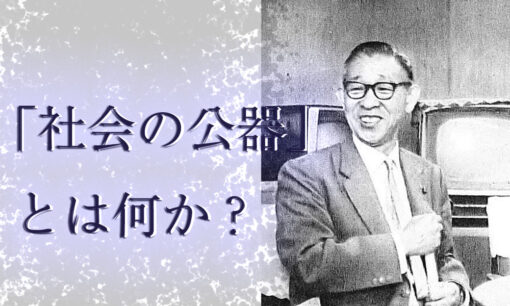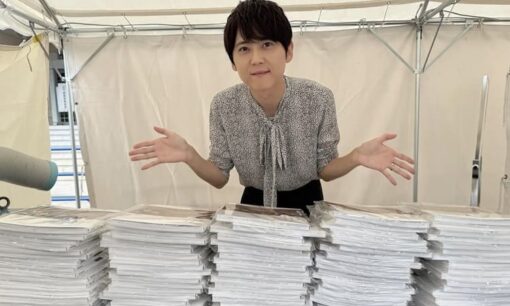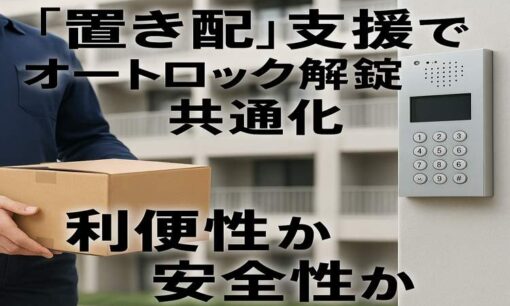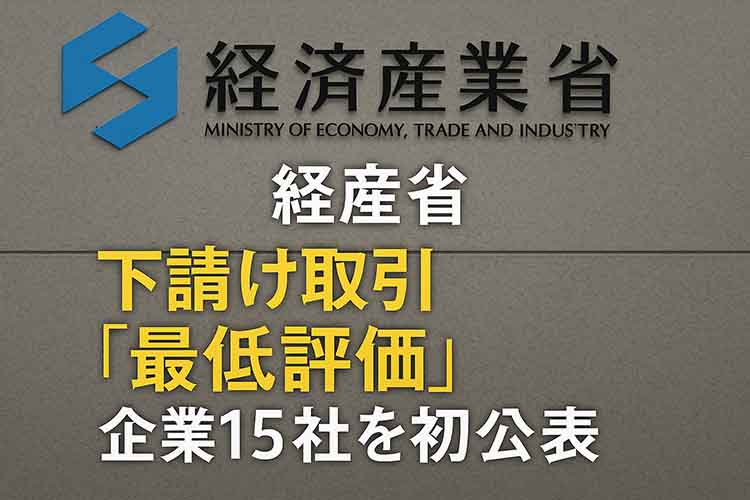
経済産業省は、中小企業への支払い条件が極めて不適切だとされた企業15社を、初めて実名で公表した。公表対象には、医療機器メーカーのテルモや食品大手のシャトレーゼ、文具メーカーの三菱鉛筆などが名を連ねる。
今回の公表は、下請け企業やサプライヤーに対し高圧的な取引条件を課す慣行の是正を狙ったもので、業界全体に波紋を広げている。
手形払いと資金繰りの負担
経産省は全国およそ6万6000社の中小企業に聞き取りを行い、発注元企業の支払い対応をランク付けした。その中で最低評価となった15社については、発注先企業から「手形を現金化する際の手数料まで負担させられた」といった証言も寄せられた。手形払いは来年1月から全面禁止となるが、現状では資金繰りを圧迫する要因として強い批判がある。
最低評価の企業は以下の通り。テルモ、シャトレーゼ、三菱鉛筆、三協立山、SMC、住友重機械工業、芝浦機械、牧野フライス製作所、パナソニックAP空調・冷設機器、一建設、セーレン、共和コンクリート工業、イワタボルト、新日本建設、古河産機システムズ。
公表で露呈する、上場企業の赤っ恥
経産省は今回の調査で、価格交渉や価格転嫁の分野における最低評価企業が前回調査の3社からゼロに減少したことも明らかにした。一方で「全体的に改善傾向はあるが、評価の芳しくない企業は依然として存在している」と指摘する。
評価基準には一定の解釈余地があるものの、公表に踏み切ったこと自体は大きな前進だ。ただし、公表されなかった企業の中にも悪質な事例は少なくなく、今回の基準では漏れた企業がこれまでの慣行を改めない可能性もある。基準の厳格化や継続的な調査が求められる。
今回名指しされた企業は、サプライチェーンの末端で支えるステークホルダーを軽視する、その卑小な姿勢を白日の下にさらされた。住友重機械工業やテルモ、芝浦機械、牧野フライス、三協立山、一建設の親会社である飯田グループホールディングス、さらにはパナソニックなど、統合報告書などのサステナビリティの任意開示レポートを「ご立派」に発刊する面々も含まれる。
統合報告書なんか出している場合?
しかし、その中核を成すべきサプライヤーへの誠実な対応という、最も基本的な責務をないがしろにしている現実が露わになったことで、報告書の美辞麗句は一層空虚に響く。自ら掲げた理念と現実との落差を、企業自らが「見苦しい」ほどに晒してしまった格好だ。
長寿企業の多くに取材をすると、最も重視すべきステークホルダーはサプライヤーであり、地域社会、金融機関であると語る経営者が多い。企業の持続ある活動を考える際に、サプライチェーンの持続性を考慮するという、本来の日本企業が持ち合わせていた三方よしな考え方をいつの間にか見失った企業たち。
サステナビリティ対応をしている企業にとってこれ以上ない赤っ恥であるから、本年度で鬼のように改善を行い、来年の顔ぶれからは外れてほしいものである。
海外の制度との比較
海外では、日本よりも透明性の高い仕組みが既に導入されている。英国では「Prompt Payment Code」により、大企業は中小企業への支払い期間を明示し、遵守しなければ違反企業として名前が公表される。EUでも「遅延支払い指令」により支払い期限は原則30日(最長60日)とされ、違反時には利息支払や損害賠償が義務付けられている。
こうした制度と比べると、日本は支払い期限の短縮や透明性確保の面で遅れが目立つ。経産省の今回の施策は一歩前進だが、国際水準に近づけるためには、期限や条件の法的拘束力を伴うルールづくりが課題になる。
ある中小企業の取引現場の声
公表されたリストを受け、ある金属加工業の経営者は「取引先の支払いが遅れると、こちらの仕入れ先や従業員への給与にも影響する。銀行借り入れで穴埋めすることもあり、長期的には経営体力を削られる」と語る。
また、食品関連の下請け企業の担当者は「単価を下げられたうえに、手形現金化の手数料まで求められた。表には出せないが、取引を失う恐怖から抗議できない」と吐露する。
こうした現場の声は、統計や評価ランクだけでは見えにくい実態を浮かび上がらせる。
消費者の視点も必要
今回名前が挙がった中には、消費者からは低価格やブランド力で高評価を得ている企業も含まれる。価格だけでなく、取引先との関係や支払い姿勢など、企業の本質的な評価軸を消費者自身が持つことが重要だ。行政の取り組みに依存するだけでなく、購買行動を通じた社会的監視が不可欠となる。
今後への期待
産業セクターを問わず、優越的立場を利用した取引慣行は根強い。経産省に限らず、監督権限を持つ他省庁も同様の調査と企業名公表を行えば、取引の透明性は一層高まるだろう。また、取引先企業に賃金引き上げや適正価格の支払いを行った企業の公表といった「ポジティブリスト」も有効だ。資金が末端まで循環する仕組みを整えることこそ、中小企業の商環境改善と持続的経済成長につながる。
トヨタの下請け泣かせな「かんばん方式」がアホみたいに長らく称賛されてきた一方で、サプライチェーン全体の持続性やステークホルダーとの信頼構築を優先する姿勢が問われている。今回の公表は、その方向転換を促す契機となる可能性がある。
さて。該当企業各社は、今年の統合報告書のステークホルダーエンゲージメントでどんな記載がされるのか、いまから楽しみである。