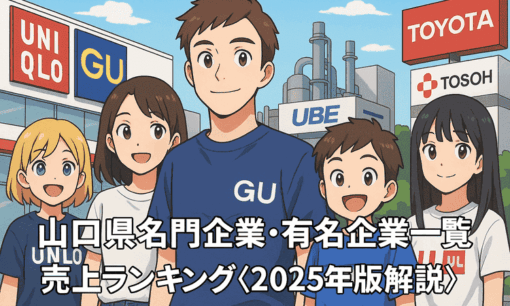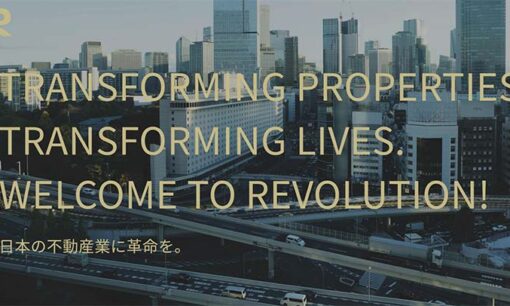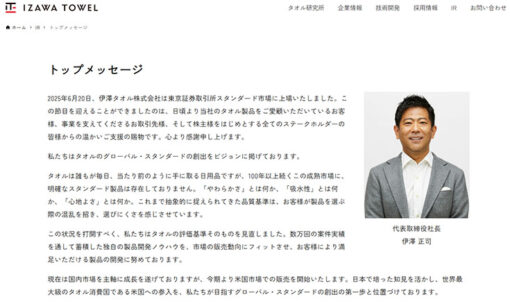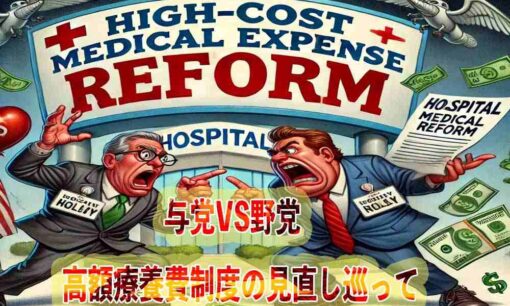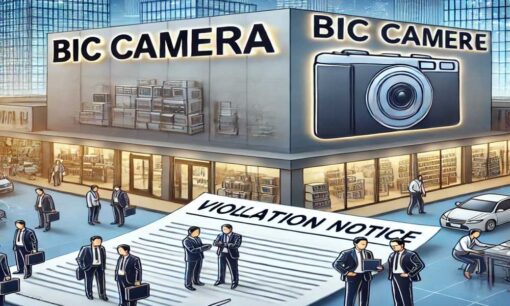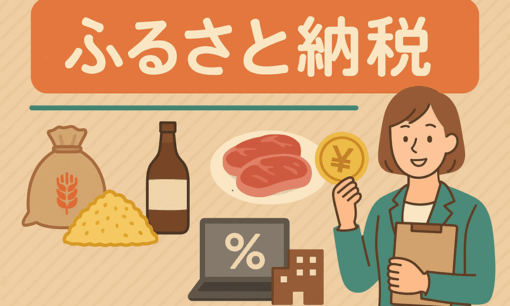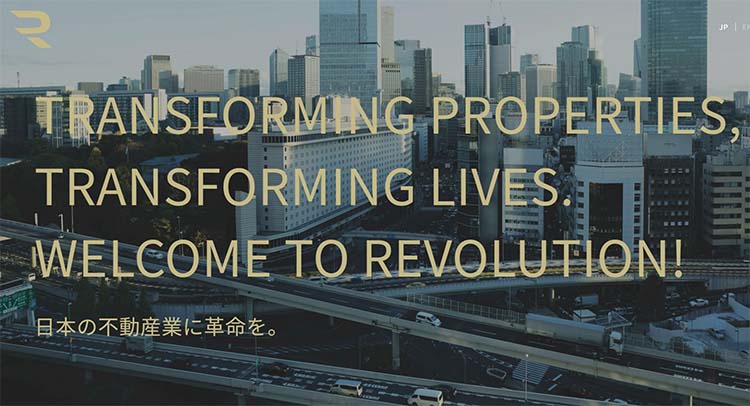
7月14日、東証スタンダード上場の株式会社REVOLUTION(証券コード8894)は、株主優待制度などをめぐる一連の混乱に関し、設置していた第三者委員会からの調査報告書を受領・開示したと発表した。
報告書は、年12万円相当のQUOカードPayを配布するという破格の株主優待制度がいかにして導入され、実施されることなく廃止に至ったのか、その過程を詳細に検証。経営判断の稚拙さ、内部統制の機能不全、さらには特定株主による実質的な経営関与に至るまで、異例づくめの事実関係が次々と明らかにされた。
「株価を吊り上げた優待」はどのように破綻したか
調査報告書が描いたのは、シンプルながらも複雑な連鎖だった。
はじまりは、REVOLUTIONによるWeCapital社の株式交付による買収だ。交付比率は固定とされ、REVOLUTION株が1:12,429の比率でWe社株主に割り当てられた。交付された株式のうち、50%にはロックアップ(譲渡制限)がかけられていたが、残り半分には一切の制限がなかった。
このタイミングで導入されたのが、年12万円のQUOカードPayを付与する株主優待制度だった。派手なインパクトとともに株価は急上昇し、投資家が殺到。ところが、ロックアップ対象外のWe社株主らが保有株を次々と市場で売却し、それを拾った新たな一般株主が優待の対象となっていく。
株主数は急増し、当初想定の1,100名程度から、2025年1月末時点では9,930名にまで膨らんだ。その結果、優待に必要な原資は11.9億円に達し、会社の預貯金残高(2.8億円)ではまったく足りないという事態に陥った。
制度は一度も実施されることなく廃止された。破綻は、仕組みが動き出した直後に、必然のように訪れていた。
“思い込み”と“期待”が支配した経営の論理
この設計破綻を主導したのが、当時の新藤弘章社長だった。報告書によると、前社長はロックアップ対象外株式の存在を把握していたにもかかわらず、「WeCapitalの経営陣が株を売るはずがない」という楽観的な思い込みを前提に制度を構築していた。
しかし、報告書はその姿勢を厳しく批判する一方で、「当初から優待を実施する意思がなかったとまでは認められない」とも指摘しており、制度導入時点におけるa氏の誠実性そのものを完全に否定してはいない。むしろ、検討の詰めの甘さと、経営陣の思考の偏りが問題の根幹であったことを浮き彫りにしている。
報告書が示した「ポジティブな評価点」も
報告書は、REVOLUTIONの経営を断罪する一方で、一定の事実に基づいて、誠実な部分や改善の兆しも丁寧に拾っている点が印象的だった。
たとえば、前社長が自ら新株予約権を放棄し、会社側と協議を重ねた末に辞任した経緯については、「辞任によって自己利益を放棄した」とし、強制行使条項を回避するという姑息な意図がなかったことを認めている。
また、第三者委員会は、会社としての連結会計処理や、優待シミュレーション時点での資金状況の見積もりなど、制度自体に一部の誠実さや実行可能性を担保する努力があったことも評価している。
さらに、決算期における会計上ののれん減損処理についても、適用基準に照らして「重大な違反はない」とする結論を導いており、REVOLUTIONが全面的に「粉飾的」「詐欺的」だったわけではないことを示している。
美山氏の存在と「会長」の名刺 ガバナンス崩壊の構図
それでも、報告書の核心はやはり、REVOLUTIONという上場企業が、筆頭株主の“非公式な影響力”によって動かされていたという事実に尽きる。
FO1合同会社の代表社員である美山俊氏は、社内では「会長」と呼ばれ、実際に名刺にもその肩書が印刷されていた。取締役でも役員でもない人物が、会社のオフィスに“会長室”を設け、LINEやTeamsを通じて経営指示を出す構図は、もはやコーポレート・ガバナンスの崩壊と言うほかない。
2025年2月、新藤社長の辞任、新株予約権の放棄、株主優待制度の廃止が一気に決まった「本会議」と呼ばれる場でも、指導権を握っていたのは美山氏だった。報告書には、美山氏が新藤氏に対して「辞めるか」「辞任でええか」と恫喝とも取れる発言をしていた録音記録まで掲載されている。
市場の反応は好意的、だが「課題のスタートラインに立っただけ」
7月14日の東京市場では、この報告書公開を受け、REVOLUTIONの株価が急騰。前日終値69円から、ストップ高の99円をつけて取引を終えた。PTS(私設取引システム)では一時100円台を回復するなど、短期的には「悪材料出尽くし」と見られた。
一方で、報告書が突きつけたのは、今後会社がいかに信頼を回復するかという“出発点”にすぎない。取締役会の再構築、主要株主との健全な距離、適正な経営判断プロセスの制度設計など、掲げられた再発防止策の実行がなされなければ、市場は再び不信に転じかねない。
さて、その社名が示す「革命」は、果たして現実のものとなるのか。旧社名「原弘産」時代から、不動産、M&A、投資、再生関連と、事業の看板を頻繁に変化させてきた異色の上場企業として、今回の混乱をどう乗り越えるのか、注視していきたい。