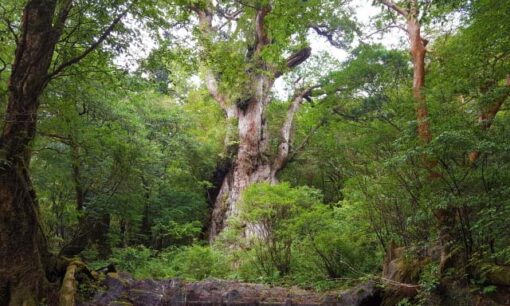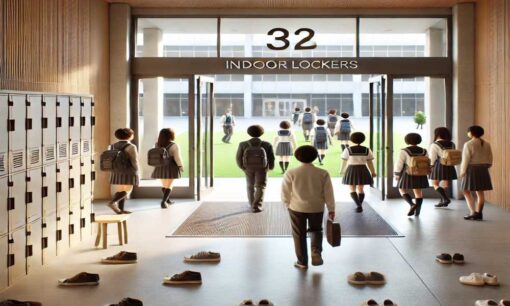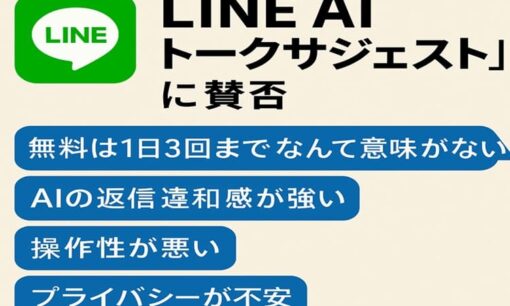日本生命から三菱UFJ銀行への出向者による内部資料の不正持ち出しが発覚した問題で、同社の社内調査により、類似の不正行為が過去6年間でおよそ600件に及ぶことが明らかになっている。複数の金融機関で同様の事案が確認されたことで、問題は一企業にとどまらない、業界全体に広がる深刻な事態へと発展している。日本生命は、この調査結果を金融庁に報告する方針を固め、12日には同社の赤堀直樹副社長らが公の場で説明責任を果たすと発表した。
不正発覚の経緯と問題の全容
2025年7月10日、日本生命は三菱UFJ銀行に出向していた社員が、同行の内部資料を不正に持ち出し、社内で共有していたことが外部からの指摘で把握した。持ち出された資料には、銀行の窓口で保険商品を販売する際の具体的な方針や、行員個人の業績評価に関する情報などが含まれていたという。これらの資料は「社外秘」と認識しながらも、写真撮影という手口で不正に取得され、日本生命社内の営業部署で共有されていた。
生命保険会社は、銀行の窓口を通じて自社の商品を販売する「銀行窓販」という形態でビジネスを展開しており、このビジネスモデルにおいて出向者は重要な役割を担っている。しかし、今回の不正は、出向者が出向先の機密情報を不正に利用し、自社の営業活動を有利に進めようとした疑いが強く、不正競争防止法の趣旨に照らして不適切であると指摘されている。日本生命は、不正が発覚した当初から問題の深刻さを重く受け止め、事実解明に向けて社内で調査チームを発足させた。金融庁から8月18日までに報告するよう求められていた事実関係の調査が終わらず、ほかに同じような事案がないかも含め調査を継続するとしていた。
類似事案600件が物語る常態化の実態
この問題は、三菱UFJ銀行での一件が氷山の一角に過ぎなかったようだ。日本生命が設置した60人体制の社内調査チームによる調査が進むにつれ、不正は特定の個人や組織に限定されたものではないことが判明した。関係者によると、調査の結果、2019年からの6年間にわたり、三菱UFJ銀行を含む7つの金融機関で、同様の内部資料の不正持ち出しが合わせておよそ600件にのぼることが明らかになったという。
これらの不正行為は、複数名にわたる社員によって行われていた可能性が高く、企業全体として不正行為が常態化していたのではないかとの見方も強まっている。金融機関から不正に持ち出された情報は、いずれも日本生命の保険販売の方針や戦略に直接関わるものであり、自社の営業成績向上を目的に行われていたと推察される。日本生命は、この調査結果を金融庁に報告する方針を固め、9月12日には同社の赤堀直樹副社長らが公の場で説明責任を果たすと発表している。