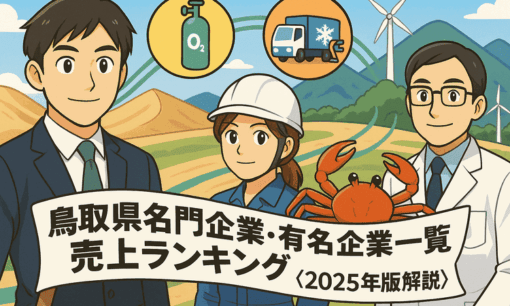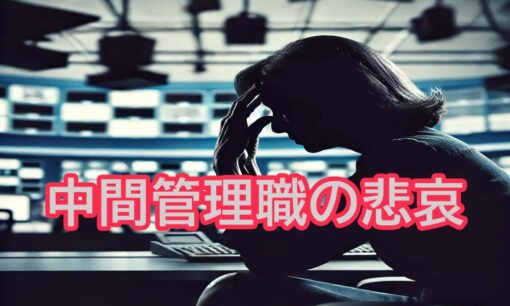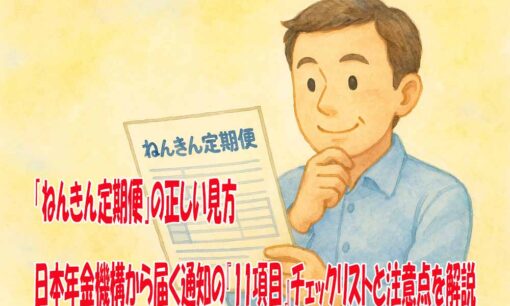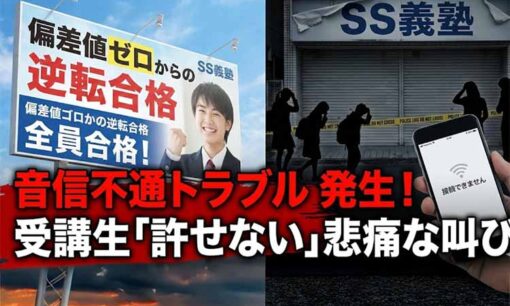愛知県の私立聖霊高校ソフトボール部で起きた主将の女子生徒の自殺事件は、強豪校の部活動指導がはらむ闇と、その後の学校側の不適切な対応を露呈させた。第三者委員会の調査報告書は、顧問の暴言が自殺の一因である可能性を指摘。しかし、学校側は遺族への配慮を名目に、生徒たちに事実と異なる説明をするなど、対応のまずさが次々と明らかになっている。
強豪校を襲った悲劇と「不適切指導」の認定
2022年4月19日、愛知県瀬戸市の私立聖霊高校に通う3年生で、ソフトボール部の主将を務めていた小林心彩(こいろ)さん(当時18)が、部活動を終えて帰宅した後に自ら命を絶った。彼女は、2021年夏のインターハイに初出場した強豪チームを牽引する、責任感の強いキャプテンであった。しかし、その裏では、顧問である男性教諭からの厳しい指導と、1年生の夏に痛めた腰の怪我によるプレーの不全感に人知れず悩んでいたという。
南山学園が設置した第三者委員会の報告書によると、自殺当日の打撃練習中、小林さんがミスをした際、男性顧問から「お前はもういらない」「キャプテンに向いていない」「他の選手に代わったほうがいい」「キャプテンじゃなければ試合に出していない」などの暴言を浴びせられていたことが認定された。顧問は「記憶にない」と発言自体を否定したが、複数の部員による証言が一致しており、第三者委はこれらの暴言があったと結論付けた。
報告書は、これらの発言が「自己の存在価値を否定されたと推認でき、相手を深く傷つける暴言にあたる」と厳しく指摘。文部科学省の定める部活動指導に関するガイドラインに照らしても「不適切」であると判断し、これらの指導が自殺の一因となった可能性を否定できない、と結論づけた。
遺族への配慮か、隠蔽か?学校側の不適切な対応
事件後、聖霊高校は遺族からの要望を受けて第三者委員会を設置。調査結果がまとまるにつれ、学校側の対応に次々と問題があったことが明らかになっていった。その最たるものが、他の生徒に対する説明である。
当時、学校側は他の生徒への影響を考慮し、遺族に対して「交通事故で亡くなったことにすることもできます」と提案していた。遺族が「そうですね」と答えたことから、学校側は同意を得たと判断し、生徒たちに事実と異なる「事故死」と伝えた。しかし、その後の葬儀の場で、母親は参列した部員たちに「自ら命を絶った」と公表した。
この事実について、第三者委員会の報告書は「遺族の思いに反し、不信感を抱かせることになった」と指摘。11日に開かれた記者会見で、同校の池田真一副校長は「隠蔽するつもりはなかったが、遺族の思いと乖離したものとなり、深く反省し、おわびしたい」と釈明した。一方で、この提案が「誘導」に当たるとは考えていなかったとし、代替案のつもりだったと語っている。
さらに、学校は事件後、速やかに愛知県私学振興室に自殺を報告していたが、第三者委員会の報告書については報告していなかった。これについて南山学園の担当者は「失念していた」と説明。この事態を受けて、愛知県の大村知事は定例会見で「一切報告が無く極めて遺憾」と述べ、県内の私立高校81校の校長に適切な報告を求める通知を出した。
処分なき顧問と不十分な再発防止策
第三者委員会の報告書は2024年9月に提出されたが、不適切指導と認定された顧問の男性教諭は、その後も指導を続けていた。学校側は、新チームの発足直後であったことから、生徒の動揺を避けるために適切な時期での体制変更を決めたと説明。しかし、顧問が部活動から外れたのは翌年8月であり、報告書提出から約1年が経過していた。顧問への処分についても、学校側は「プライバシーの観点から回答を差し控える」とし、明言を避けている。
自殺の報告を受けた後、学校は指導者の増員や、OGコーチ、ソフトボール経験のある女性教員の顧問への配置などの対策を講じた。また、全教職員を対象に、自殺予防やハラスメントに関する研修を計8回実施したという。しかし、第三者委の報告書を公開しない方針や、遺族との今後のやり取りを「これまで通りのやり方を継承したい」と、代理人弁護士を通じた形式的なものに留めようとする姿勢は、根本的な問題解決への消極的な姿勢と受け取られても仕方がない。
構造的な問題の克服は可能か
今回の聖霊高校の事件は、顧問による指導のあり方が問題であることは明らかだ。だが、それ以上に、危機管理に対する学校側の認識の甘さ、組織としての対応の不透明さが浮き彫りとなった。第三者委員会の報告書が指摘するように、顧問の発言は「不適切指導」であり、生徒の「存在価値を否定する」ものであった。それにもかかわらず、学校が顧問の指導力を優先し、指導を継続させたことは、何よりも「勝利至上主義」が根底にあることを示しているのかもしれない。
そして、自殺という重大な事態を「交通事故」と説明した学校側の対応は、たとえ「隠蔽」の意図がなかったとしても、遺族の感情を深く傷つけ、行政や社会からの不信を招く結果となった。真実を伝え、責任を果たすという基本的な姿勢が欠如していたことは否定できないだろう。
この事件は、単に一校の個別事案として片付けてはならない。部活動の指導者が「人格を否定する」ような指導を許容する文化や、生徒の心の健康よりも部の成績を優先する風潮、そして危機発生時の不透明な情報管理体制は、全国の多くの学校が抱える構造的な問題である。
今後、教育機関は文部科学省のガイドラインを遵守し、体罰やハラスメントを許さない明確な方針を打ち出す必要がある。また、万が一の事態に備え、遺族と真摯に向き合い、専門家の協力を得ながら適切な情報公開を行う体制を構築することが急務である。一人ひとりの生徒が安心して学園生活を送れる環境を整えるためには、社会全体でこの問題に目を向け、継続的に議論していくことが求められている。