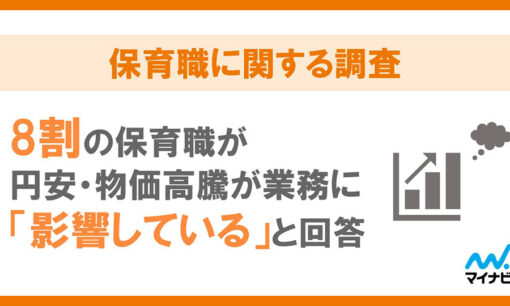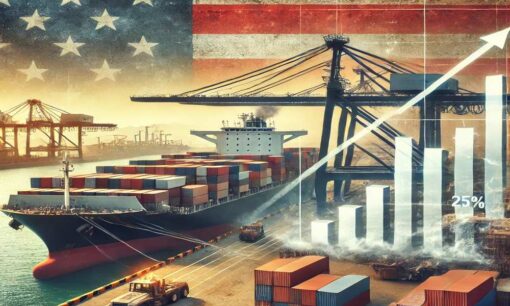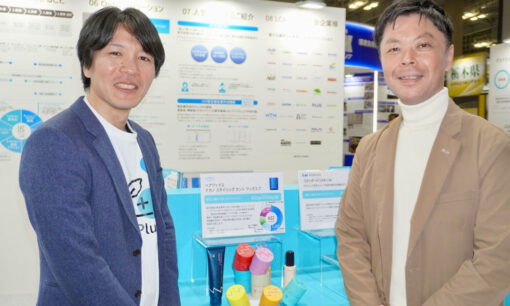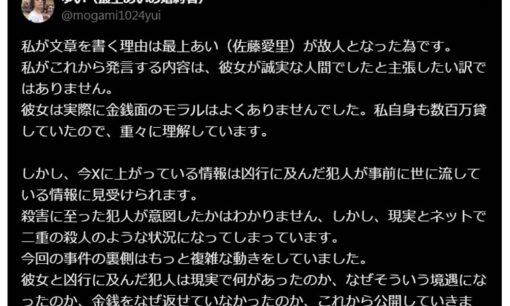南米原産の外来水草「ナガエツルノゲイトウ」が、日本各地で急速に広がり、農業や生態系に深刻な影響を及ぼしている。川や湖を覆い尽くすだけでなく、水田にまで侵入し、稲の生育や収穫に打撃を与えているのだ。農家は雑草管理や収量低下に苦しむ一方、行政や研究機関は駆除と有効活用の両面から対応策を模索している。
広がる脅威――コメ農家を直撃
南米原産の水草「ナガエツルノゲイトウ」が全国各地で繁殖し、コメの収穫に深刻な影響を及ぼしている。特定外来生物に指定されているこの植物は、川から田んぼにまで広がり、刈り取りが困難になるケースも出ている。
茨城県河内町のコメ農家・野澤拓哉さんは「増えすぎると刈り取りができないほ場ができてしまう。稲の肥料まで吸われ、品質や収量に悪影響が出る」と語る。農家にとって、雑草管理の負担が飛躍的に増し、農業経営を圧迫する事態となっている。
日本での侵入と拡散の経緯
ナガエツルノゲイトウが日本に持ち込まれたのは、1990年代後半とされる。観賞用の水草として輸入され、一部は園芸用やアクアリウムで流通した。その後、
- 観賞池や水槽からの流出
- 洪水や大雨による流下
- 鳥や船舶などによる断片の移動
といった経路を経て、各地の河川や湖沼に定着した。茎の断片から容易に再生する特性があるため、流出した一部が自然環境で繁殖を始め、瞬く間に全国に広がった。
環境省は2006年に「特定外来生物」に指定し、輸入や栽培を規制したが、すでに拡散した個体群の駆除は追いつかず、いまなお各地で被害が続いている。
改善策・対応策
- 物理的駆除
フェンス設置や水路遮断による侵入防止が進められている。刈り取りや除去作業は人力・機械を用いるが、茎の一部から再生する特性のため、完全駆除は困難を極める。 - 生態系管理
外来種対策の専門家は「定期的なモニタリングと早期対応が不可欠」と指摘。発生初期に小規模で対処すれば、被害拡大を抑制できる可能性が高い。 - 有効活用の試み
香川県鳴門市では、回収したナガエツルノゲイトウを堆肥化する取り組みが進む。農業資材として循環利用することで、コスト削減と環境対策を両立させる可能性がある。
農家への支援策
- 行政の補助金・支援制度
環境省や農林水産省は外来植物の駆除に一部補助を行っている。地方自治体でも駆除費用や機材導入への助成を進める動きがある。 - 共同対策の推進
農家単独での対応は限界があるため、農協や地域住民と連携し、合同で駆除・管理を行う体制づくりが求められる。 - 研究開発への期待
堆肥化やバイオマス燃料化など、新たな利用法の開発が進めば、「厄介モノ」から「資源」へ転換できる可能性がある。
展望
「地球上最悪の侵略的植物」と呼ばれるナガエツルノゲイトウは、農業と生態系に大きなリスクをもたらす存在だ。しかし同時に、活用の工夫次第で持続可能な農業や循環型社会の一助となる可能性もある。農家の苦労を和らげるには、行政・研究機関・地域が一体となった長期的支援が欠かせない。