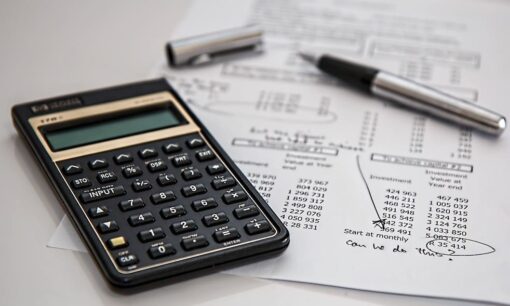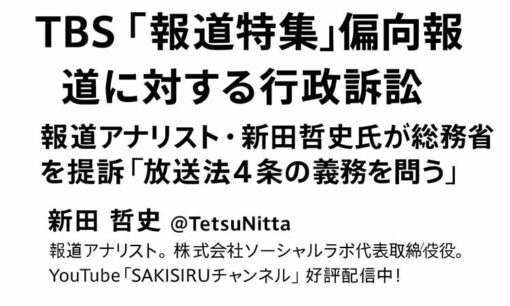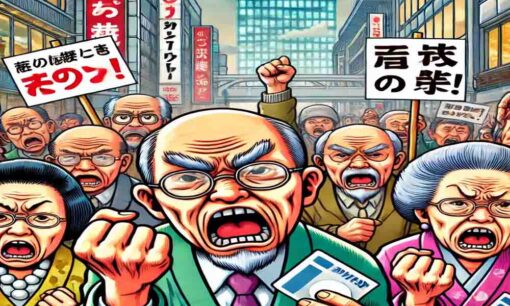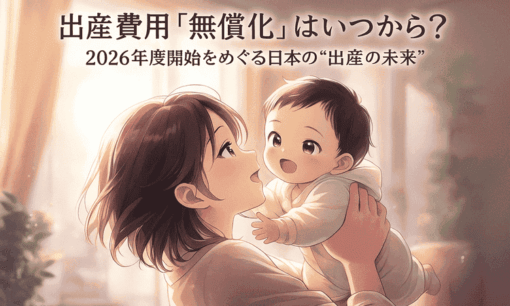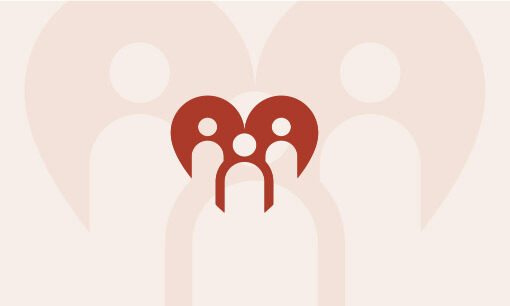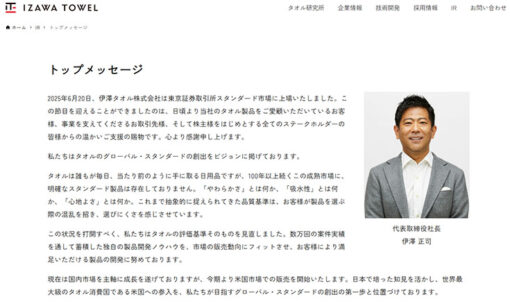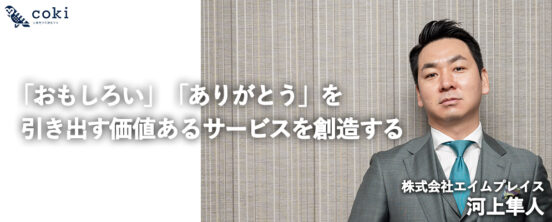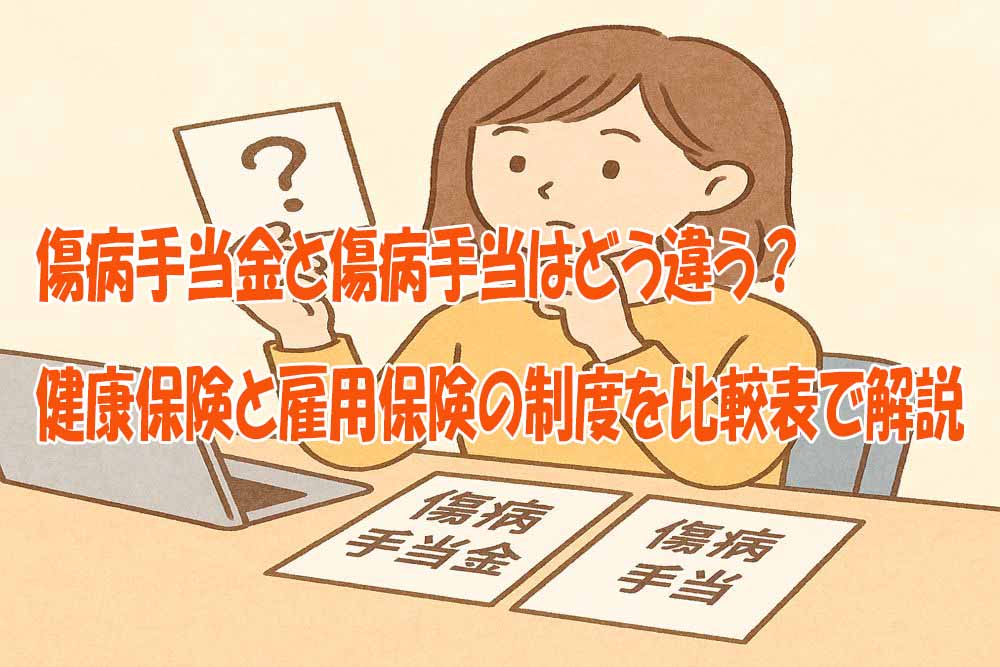
病気やけがによって働けなくなったとき、生活の支えとなる制度として「傷病手当金」と「傷病手当」がある。両者は言葉こそ似ているが、対象者や給付の目的は大きく異なる。厚生労働省やハローワークの制度説明によると、傷病手当金は健康保険制度の中で在職者を対象とし、傷病手当は雇用保険制度のもと失業者を対象とする制度である。
傷病手当金と傷病手当の違い
以下の比較表にまとめると、両制度の相違点が明確になる。
| 項目 | 傷病手当金 | 傷病手当 |
|---|---|---|
| 保険の種類 | 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など) ※国民健康保険は原則対象外だが、一部自治体で独自給付あり | 雇用保険 |
| 目的 | 在職中に病気やけがで働けなくなった人の給与補償 | 失業中に病気やけがで求職活動ができない人の生活費支援 |
| 利用できる人 | 健康保険に加入しており、業務外の病気・けがで働けなくなった人 | ハローワークで求職の申込みをした失業者 |
| 支給条件 | ①業務外の病気・けが ②仕事ができない状態 ③給与の支払いがない ④連続3日以上の待機を経て4日目以降 | ①失業手当の受給資格あり ②求職申込み後に病気やけが発生 ③30日以上就職できない状態 ④医師の診断書提出 |
| 支給金額 | 過去12か月の平均標準報酬月額÷30日×2/3 | 離職前6か月の平均賃金日額×給付率(45~80%) |
| 受給期間 | 最長1年6か月(通算制) | 失業手当の所定給付日数の範囲内(90~最大360日) |
健康保険に基づく「傷病手当金」
傷病手当金は、健康保険に加入する被保険者が業務外の病気やけがで働けなくなった場合に支給される。給与が支払われない期間に生活を補う制度であり、連続3日の待機期間を経て4日目から支給が始まる。支給額は標準報酬月額の3分の2相当で、受給期間は最長1年6か月である。
業務中や通勤中の災害は労災保険の対象であり、傷病手当金は適用されない。会社員やパートタイム労働者であっても、勤務先の社会保険に加入していれば対象となる。なお、国民健康保険には全国一律の制度は存在しないが、コロナ禍の際に導入されたように、一部自治体では独自に「国保傷病手当金」を給付する例がある。
雇用保険に基づく「傷病手当」
一方の傷病手当は雇用保険制度に属する。失業手当(基本手当)の受給資格を持つ人が、求職活動中に病気やけがによって就労不能となった場合に支給される。条件は「30日以上働けない状態」であること、医師の診断書を提出できることなどである。
支給額は失業手当と同額で、離職前6か月の給与を基に計算される。受給可能日数は失業手当の所定給付日数の範囲内であり、自己都合退職か会社都合退職かによって最大日数は異なる。
ケーススタディでみる両制度の活用例
会社員が長期療養を余儀なくされた場合
都内の企業で働くAさんは、健康保険に加入している会社員だ。病気により3か月間休職した。この場合は「傷病手当金」の対象となり、給与が支払われなかった期間に標準報酬月額の3分の2が補償される。
退職後に病気で入院した場合
自己都合で退職し、ハローワークに求職申込みをした直後に入院したBさんは「傷病手当」を申請できる。30日以上の療養を医師が証明すれば、失業手当の給付日数の範囲で生活費補償が受けられる。
退職日当日も病気療養中だった場合
退職日以前から療養していたCさんは、退職日も就労不能であった。この場合は退職後であっても「傷病手当金」を継続して受け取ることができる。
申請手続きの違い
- 傷病手当金:健康保険組合や協会けんぽに申請。本人・事業主・主治医の記入が必要。
- 傷病手当:ハローワークに申請。本人記入に加え、医師の証明が必要。不備があると受理されない。
いずれも申請期限が設けられている。傷病手当金は「支給対象となった日の翌日から2年以内」に申請しなければならず、期限を過ぎると受給できない。
論点と課題
両制度はそれぞれの立場に応じたセーフティーネットであるが、名称の類似から混同されやすい。特に退職前後の取り扱いや、アルバイト・パートの対象可否について理解が不十分なケースが多い。
また、傷病手当金の年間支給件数は協会けんぽの統計で約70万件(令和4年度)に達しており、利用者は少なくない。それにもかかわらず、手続きが煩雑であるとの指摘もある。制度周知と手続きの簡素化は今後の課題といえる。
まとめ
「傷病手当金」は健康保険に基づき在職中の所得を補償し、「傷病手当」は雇用保険に基づき失業中の生活を支える。いずれも働けなくなったときの重要な支援制度であり、自身の立場に応じて適切に活用することが求められる。