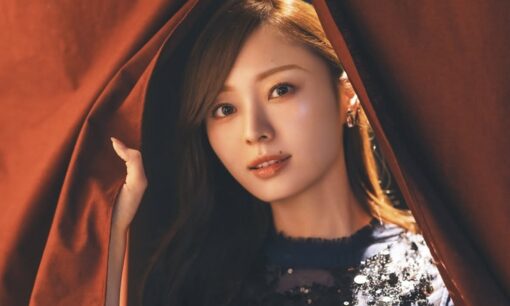子どもたちの「睡眠不足」が深刻な問題となっている。
東京大学と理化学研究所による最新調査では、全ての年代で推奨される睡眠時間を満たしていない子どもが8割を超え、小学生や高校生では9割以上が慢性的な睡眠不足に陥っている実態が明らかになった。背景には、塾や部活動の過密スケジュール、そして就寝前のスマートフォン利用などがある。発達や健康、学力への影響が懸念されるなか、家庭や社会に求められる対応とは何か。
子どもの睡眠、全年代で「不足」傾向 成長への影響懸念
「睡眠不足」が子どもの間で広がっている。東京大学と理化学研究所が共同で実施する「子ども睡眠健診プロジェクト」によると、厚生労働省が推奨する睡眠時間を満たしていない子どもの割合が、ほぼすべての年代で8割を超えていることが明らかになった。特に小学校高学年から高校生にかけては9割近くが不足しており、専門家からは発達や学力、心身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があると指摘されている。
推奨される睡眠時間と実態の乖離
厚労省は、以下のように年代別の適切な睡眠時間を示している。
| 年齢層 | 推奨睡眠時間 |
|---|---|
| 1~2歳児 | 11~14時間 |
| 3~5歳児 | 10~13時間 |
| 小学生 | 9~12時間 |
| 中高生 | 8~10時間 |
だが、今回の調査では、例えば中学3年生では87.8%が、小学6年生では94.6%がこの基準を満たしていない。特に高校生では「6時間未満」の子どもが2割を超え、「削られやすい日課」としての睡眠が慢性的に圧迫されている現状がうかがえる。
背景にあるのは「部活・塾・スマホ」
睡眠時間が確保されない背景には、習い事や学習塾、そして近年増加するスマートフォンの利用などがある。中学生の一例では、部活から帰宅後に塾へ向かい、帰宅は21時。その後に食事や入浴、就寝準備を終えると、眠りにつくのは深夜0時過ぎになってしまう。起床時間は午前7時で、睡眠時間は7時間を切る。
保護者からも「帰宅後に食事・宿題・入浴で手一杯」「共働きで理想的な生活リズムを保てない」といった声が上がっており、家庭内でも葛藤がある。
教育アドバイザーの清水章弘氏は、「部活後に始まる塾も多く、授業終了が22時を超える場合もある。高校受験を控える中学生には特有の多忙さがある」と述べる。
子どもの成長と睡眠の深い関係
睡眠は、子どもの脳と身体の発達にとって極めて重要な役割を果たす。睡眠中には成長ホルモンが分泌されるだけでなく、記憶の定着や情緒の安定にも深く関わる。
睡眠コンサルタントの友野なお氏は、「子どもの心と体、そして脳の発育に欠かせない時間。削ってはならない基本的な生活習慣」と警鐘を鳴らす。
年代別にみる「適切な睡眠の工夫」
睡眠時間の確保には、年齢ごとに応じた工夫が求められる。以下は家庭でできる主な対応策である。
| 年齢層 | 睡眠確保の工夫 |
|---|---|
| 幼児(~5歳) | 寝る前のルーティンを作り、19~20時には就寝できるよう心がける。テレビや動画視聴は18時までに制限する。 |
| 小学生 | スマホやゲーム機は21時までに使用を終了させ、学習も早めに切り上げる。夜更かし習慣の是正が重要。 |
| 中高生 | スケジュールを見直し、21~22時には寝床につけるよう調整。スマホは就寝1時間前には手放す。オンライン塾やタブレット学習の活用で移動時間を削減することも有効。 |
また、休日に寝溜めをする「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」も、睡眠の質を下げるため注意が必要とされている。
学校や社会全体での支援が不可欠
家庭の努力だけでなく、学校や地域社会の理解と支援も欠かせない。授業開始時間の見直しや、塾のオンライン化、地域ぐるみでの子どもの生活リズム改善など、持続可能な支援体制の構築が今後の課題である。