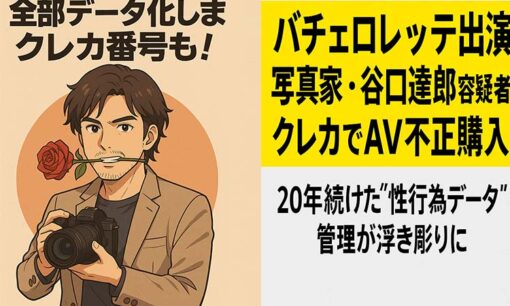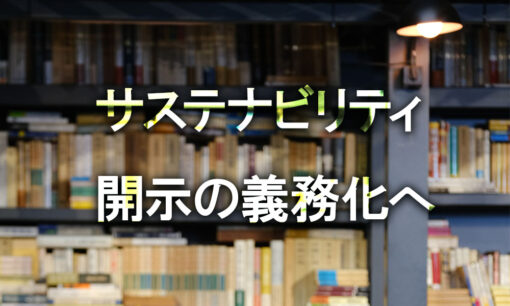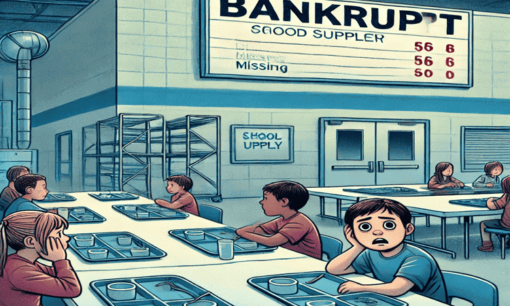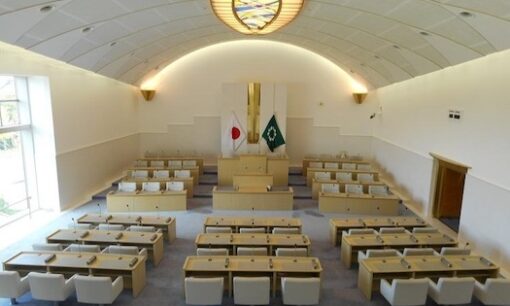近年、大手企業を中心に「賞与の給与化」が進みつつある。これは、これまで年に数回に分けて支給されてきた賞与(ボーナス)を、毎月の給与に組み込む形で定額支給とする制度である。その動きの背景には、賃上げ圧力や人材確保、企業の報酬制度見直しといった現代的課題があるが、そもそも「賞与」とは何か、そしてそれが持つ本来の意義と問題点はどういったものであろうか。
賞与とは何か
賞与とは、通常の月例給与とは別に、企業が一定のタイミングで従業員に支給する特別な報酬である。一般的には年2回、夏季と冬季に支給され、支給額は企業の業績や個々の評価に応じて変動する。賞与は「固定給」とは異なり、労働契約に基づく義務的な支払いではないケースもある。企業側が「業績に応じて支給」としている場合、その支払いはあくまで裁量の範囲内とされる。
賞与の意義と効果
賞与が持つ最大の特徴は、成果や業績に応じた報酬であるという点にある。このため、従業員に対しては「インセンティブ(動機づけ)」として機能し、努力や成果が直接的に報われるという認識が形成されやすい。企業にとっても、好業績時には報いる手段となり、不況期には柔軟に人件費を調整する仕組みとして活用できる。
賞与を給与に組み込むことで得られるメリット
労働者側の利点
- 毎月の収入が安定する
収入が月々に均されることで、生活設計がしやすくなる。家計の見通しを立てやすくなり、住宅ローンや育児費用など固定支出の計画も立てやすい。 - 見かけの給与が高くなり、金融審査にも有利になる可能性
固定給のベースが高くなることで、クレジットやローンなどの信用審査において評価が向上する場合がある。 - 社会保険の給付水準に好影響を与える場合もある
給与が高くなると、傷病手当金や育児休業給付など、一部の給付の算定基準が引き上がることがある。
企業側の利点
- 採用競争力の向上
「初任給30万円」などの高水準提示が可能になり、若手人材の確保に有利に働く。 - 報酬制度の簡素化
毎月の支給に一本化することで、賞与査定・支給基準作成の手間が軽減され、人事制度全体のスリム化が可能となる。 - 中長期的な人材定着につながる
給与の安定性は、従業員の離職抑制にも寄与する。
多くの企業が賞与をあえて残す理由
経営側の判断要素
- 業績に応じた人件費調整機能が失われる
賞与は景気や業績に応じて柔軟に調整できる「変動費」の側面を持つ。これを給与に組み込むと、業績悪化時にも高い固定給を維持する必要があり、経営負担が大きくなる。 - 報奨金としての意味が薄れ、従業員のモチベーションに影響
賞与には努力や成果への直接的な報酬という性格があり、それがなくなるとインセンティブが弱まる恐れがある。
従業員側の意識
- ボーナスの「一括支給」が家計の節目として機能している
進学や車の購入、住宅ローンの繰り上げ返済など、まとまった支出に備える役割としてボーナスは生活に根ざしており、月給化されるとその計画性が崩れる懸念もある。 - 企業文化としての根強さ
特に日本型雇用においては「夏冬の賞与」は生活慣習にも組み込まれており、その廃止や変更には一定の心理的抵抗が伴う。
総括
賞与制度は、企業の業績や従業員の評価を柔軟に反映させる報酬体系として、企業経営において重要な役割を果たしてきた。一方で、賞与の給与化による収入安定や採用力強化といった利点も近年注目されている。今後は、企業の業種・財務体質・雇用戦略に応じて、多様な制度設計が併存していくと見られる。経営者・人事部門には、自社に最適な報酬体系を見極める力が求められる。