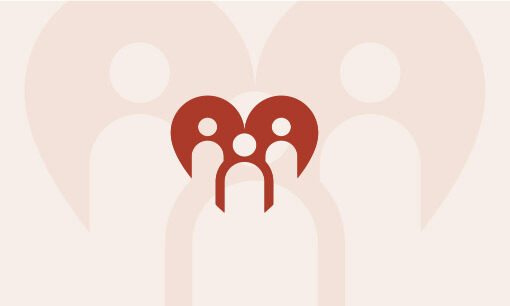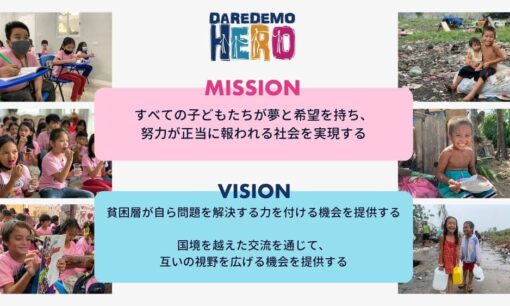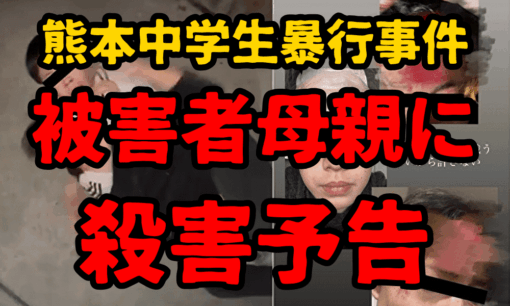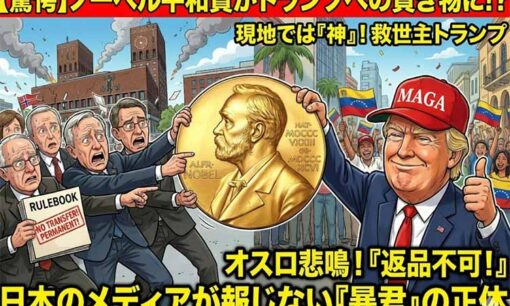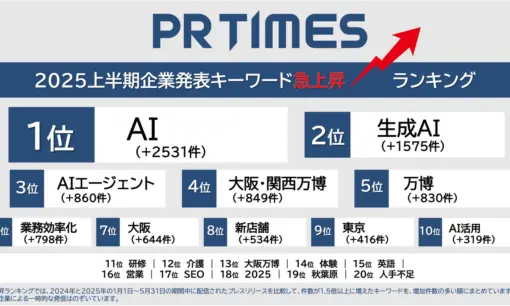“バズ狙い”の軽率行為がSNSで拡散

大阪市中央区にある牛丼チェーン「すき家」の店舗で、16歳の少女2人が備え付けのお茶用ピッチャーに直接口をつけて飲む様子を撮影し、その動画をSNSに投稿したとして、大阪府警が威力業務妨害容疑で書類送検した。警察は店の業務を妨害したと判断し、店舗の防犯カメラ映像やSNS上の情報から当該少女らを特定。供述をもとに裏付け捜査を進めていた。
ピッチャーに口をつけた一部始終がSNSに投稿され、炎上拡大
事件が起きたのは2025年2月1日。2人は「すき家」店内でお茶を直飲みする姿を撮影し、X(旧Twitter)やInstagramに投稿。動画は瞬く間に拡散され、衛生面での問題に加えて、店舗の通常業務を著しく妨げる行為として社会的な非難を集めた。
すき家側はこの動画の拡散を受け、対象のピッチャーを回収・洗浄し、再発防止策を検討するなどの対応を迫られた。投稿された動画には1人が飲み、もう1人が撮影する様子が収められており、共謀していたことがうかがえる。警察は、この行為が業務に具体的な支障を及ぼしたとして、威力業務妨害にあたると結論づけた。
威力業務妨害容疑が適用された理由とは何か
近年、飲食店を舞台にした迷惑行為が相次いでおり、2023年には回転寿司店で醤油差しを口に含む動画を投稿した少年が逮捕されたほか、栃木県ではラーメン店でニンニクスプーンを口に入れて戻す動画の投稿者が摘発されている。今回のすき家の事案も、いわばその延長線上にある。
背景には、SNS上で注目を浴びたいという若者の承認欲求や“バズ狙い”の文化がある。目立ちたい一心で他人に迷惑をかける行為を“ネタ”として拡散する行動が常態化しつつあるが、それが明確に法的責任を伴う行為であることを、今回の事案は改めて社会に突きつけた。
店舗名非公表の判断、その裏にある配慮と現場の混乱
被害が発生した店舗の詳細は公開されておらず、これは関係者への誹謗中傷や風評被害を避けるためとみられる。企業側は再発防止を掲げつつも、こうした行為に対して毅然とした姿勢を貫く必要がある。
一方で、こうした迷惑動画に対して、企業側が十分な法的措置を講じていないという指摘もある。実際、SNS上で大炎上する事案であっても、企業は訴訟を起こすことでの逆風や、メディア報道の再燃を懸念して、被害届提出のみに留まるケースが目立つ。
“泣き寝入り”が加害者の罪悪感を鈍らせる構図
すき家を展開するゼンショーグループも、これまでの類似事案で「厳正に対処する」とコメントしているが、損害賠償請求など民事手続きにまで踏み込む事例は稀である。専門家は「企業が法的対応を控える“泣き寝入り構造”が、加害者側の罪悪感の欠如を招いている」と指摘する。
店舗現場の対応コストや精神的負担は無視できず、企業にとっても風評リスクと顧客体験の毀損という重大なダメージをもたらす。迷惑行為が繰り返される背景には、こうした“訴えられないだろう”という認識の甘さが横たわっている。
「イタズラでは済まされない」迷惑行為の先にあるもの
企業としては、モニタリング強化や掲示物による啓発に加え、毅然とした対応と社会的発信が必要となる。さらに、プラットフォーム事業者との連携や法制度の整備によって、加害行為に対する社会全体のリテラシーを高めていく必要がある。
今回の一件は、単なる“イタズラ”では済まされない。SNS社会における責任の所在と、それに対する社会的・法的な歯止めの重要性をあらためて突きつけた。