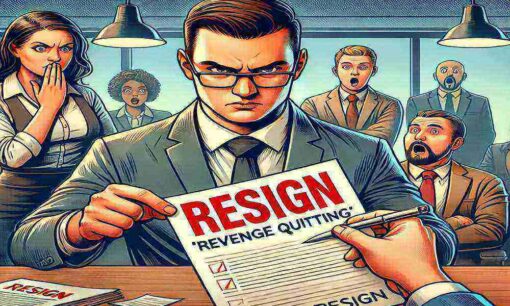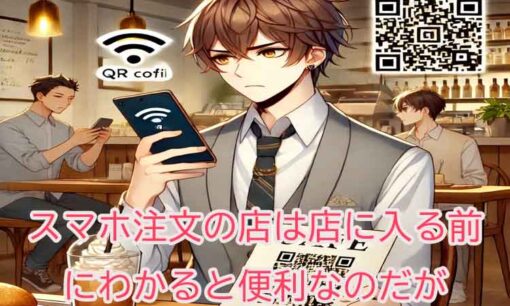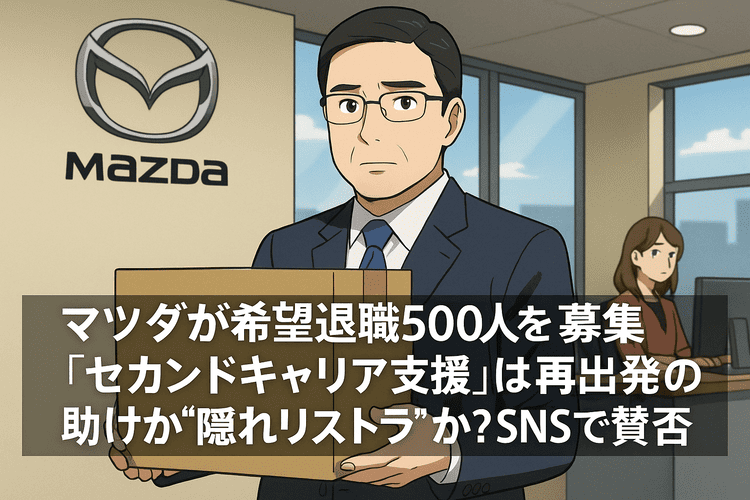
マツダは4月22日、50~61歳の正社員を対象に、500人の希望退職を募集すると発表した。過去の早期退職制度とは異なる新制度「セカンドキャリア支援」の狙いと今後の展望に迫る。
マツダが希望退職500人を募集 未来志向の制度か、それとも“選別”か
広島・マツダ本社の会見室。2025年4月22日午後、竹内都美子執行役員はオンライン会見で淡々と語った。「社員のキャリア形成を支援する制度であり、早期退職とは異なる」。発表されたのは、勤続5年以上かつ50~61歳の正社員を対象とした500人規模の希望退職募集である。
対象となるのは製造現場を除く間接部門の社員。2025年6月から翌年末にかけて最大4回の募集が行われ、退職金の割増と再就職支援を伴う。制度の名称は「セカンドキャリア支援制度」。企業と個人がともに新たな選択肢を模索するための仕組みとして打ち出された。
竹内氏は会見の中で、「現状の業績に起因するものではなく、2022年の経営方針に基づいて導入準備を進めてきた制度」と説明した。
2001年の早期退職制度とどう違うのか
マツダが過去に行った最大規模の人材整理といえば、2001年の早期退職制度が挙げられる。当時は経営危機に瀕していた同社が1800人の退職を募ったところ、実際には2200人を超える応募があり、労務費削減効果は190億円に達した。制度の設計も、コスト削減を主眼に置いたものだった。
これに対し今回の「セカンドキャリア支援制度」は、制度の名称からして明らかに「外への移行支援」に焦点が置かれている点が特徴的だ。企業の人件費抑制策でありながらも、再就職や自律的なキャリア設計への誘導が前面に出ている。背景には、定年延長やジョブ型雇用など、これまでの“終身雇用的前提”が崩れつつある現代的な労働市場の変化がある。
EV投資と米国関税 事業環境の急変にどう対応するか
マツダの今回の判断の裏には、業界全体を覆う構造転換の波がある。EVへの投資は開発費と研究体制を一変させるほどの負担となっており、同時に、トランプ前政権が導入した米国の輸入関税政策が再び現実味を帯びている。
マツダは米国市場での販売比率が3割を超え、2024年の販売台数は約42万台。そのうち国内生産比率は10万台程度にとどまり、輸出依存が高い構造だ。関税措置が強化されれば、収益構造に深刻な打撃を受ける可能性がある。
そのような背景において、柔軟な人材再編とコスト最適化は、経営戦略上の“必要な選択”とも言える。
制度が問う“50代以降の働き方” SNSでも賛否
発表直後からSNS上では、多様な声が飛び交っている。
「再出発を支援する制度としては理想的」「マツダらしい誠実なやり方」と評価する声がある一方で、「50代で再就職できるのは一部だけでは?」「“希望”退職という名の選別ではないか」と懐疑的な意見も見られる。
とくに注目されたのは、制度の対象が「50代以上」である点だ。あるユーザーは「役職定年後のキャリアが日本企業で曖昧なままになっている。こうした制度で可視化するのは悪くない」と投稿した。一方で「退職金の割増があっても、地方都市では再就職先がない。再就職支援の質が問われる」と現実的な課題を指摘する投稿もあった。
また、「“第二の人生”を後押しする制度なのに、制度導入の背景に経営リスクがあることを正直に説明しないのは不誠実」とする意見も目立った。制度の“建前と本音”に敏感に反応するビジネスパーソンが多い印象だ。
こうした声は、マツダに限らず多くの企業が直面する“働き方の選択”に対する関心の高さを物語っている。制度の評価は、その運用と成果によって真価が問われることになるだろう。
今後の日本企業における応用可能性と展望
マツダの制度は、特定の年齢層に限定したうえで、キャリア形成の“出口”と“新たな入口”の双方を支援するものである。このアプローチは、今後の日本企業の人材戦略のモデルケースとなる可能性を秘めている。
すでに他業種でも「キャリア自律支援制度」や「社外出向制度」などが導入されており、年功序列と終身雇用が揺らぐ中での“新しい労働観”の形成が進んでいる。
マツダのこの選択は、変化に対応するための「静かなイノベーション」かもしれない。企業の生存戦略と個人のキャリア選択が、交差する時代が本格的に到来している。