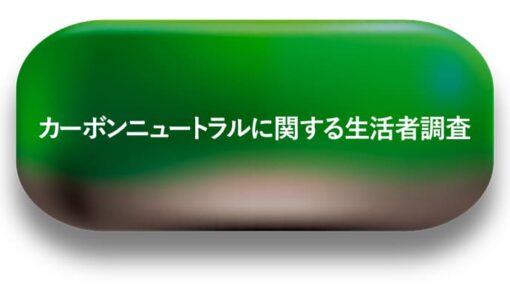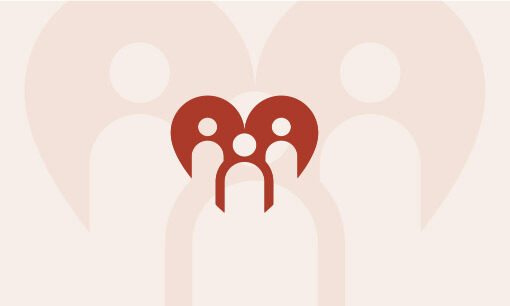高齢者住宅市場が拡大 全国で約64万人が入居

日本社会の急速な高齢化に伴い、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の施設数と入居者数が過去最高を更新している。厚生労働省老健局が2025年4月14日に発表した調査資料によれば、2024年6月時点で全国の有料老人ホームは1万6543施設、定員は約64万5845人に達した。サ高住は5179施設で、定員数は約31万2285人にのぼる。
特に大都市部での増加が著しく、大阪府が施設数で全国最多となっているほか、岐阜県は過去5年で約45%もの施設数増加を記録した。一方、東北地方や四国地方では施設整備が遅れており、地域格差の広がりが顕著となっている。
入居者は90歳以上が最多 介護度の重度化が進行
入居者像にも大きな変化がみられる。2014年と2024年の比較では、いずれの高齢者住宅類型でも90歳以上の入居者が最も多い層となった。住宅型有料老人ホームにおける要介護3以上の割合は48.9%から55.9%に上昇しており、入居者の重度化が進んでいる。
この傾向は、介護や医療ニーズの高い高齢者の受け皿として、施設運営側に求められる機能やサービスの高度化が必要であることを示している。
地域格差と都市集中が深刻化 地方の供給不足が顕在化
地域別の施設状況をみると、都市圏では施設の供給過多や競争激化が課題となる一方、地方では施設そのものの不足が問題視されている。都市圏では特別養護老人ホーム(特養)の整備が困難な状況が背景にあり、民間主導による有料老人ホームやサ高住が急増した。厚労省は「大都市圏での施設乱立」と「地方での受け皿不足」という二極化構造を指摘している。
囲い込み問題と指導監督強化 厚労省が今後の論点を提示
厚生労働省は今後、有料老人ホームの運営実態に関する問題点として、「囲い込み行為」への対策を重要課題としている。これは、住宅型有料老人ホームやサ高住において、特定の介護事業者と契約を限定し、入居者が他のサービスを利用しにくくする事例があることから指摘されている。
今後の政策論点として、厚労省は次の3点を示した。
- 有料老人ホームの運営・サービス提供の在り方
- 有料老人ホームの指導監督の在り方
- 囲い込み対策の強化と指導体制の整備
具体的には、入居者の選択権を尊重しつつ、自治体と連携した早期実態把握や事業者への適正な指導を行う体制の強化が求められている。
未来志向の提案 地域と共生する高齢者住宅へ
厚生労働省の資料では、これからの有料老人ホームやサ高住は、医療機関との連携強化にとどまらず、地域コミュニティとの交流や多世代共生を取り入れた「地域開放型住宅」が主流になる可能性があると指摘されている。東京都中野区の「グランドマスト江古田の杜」では、賃貸マンションや学生寮と隣接し、世代を超えたコミュニティ形成が進められている事例も紹介された。